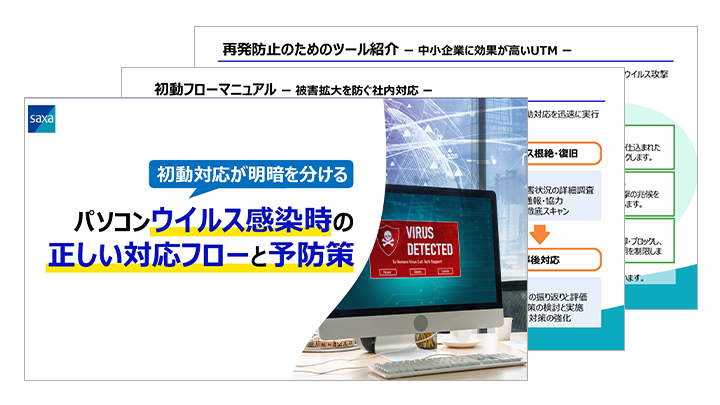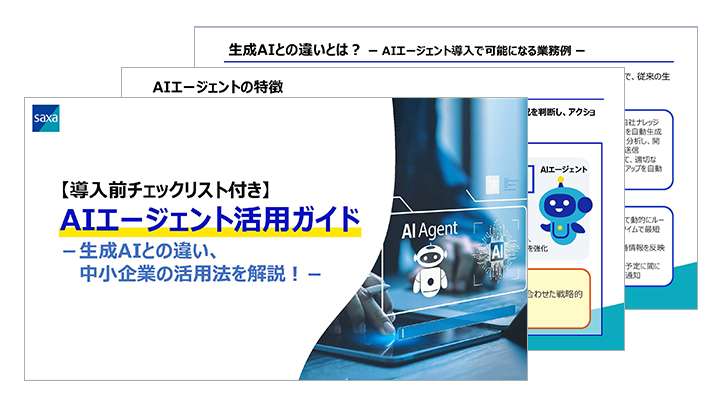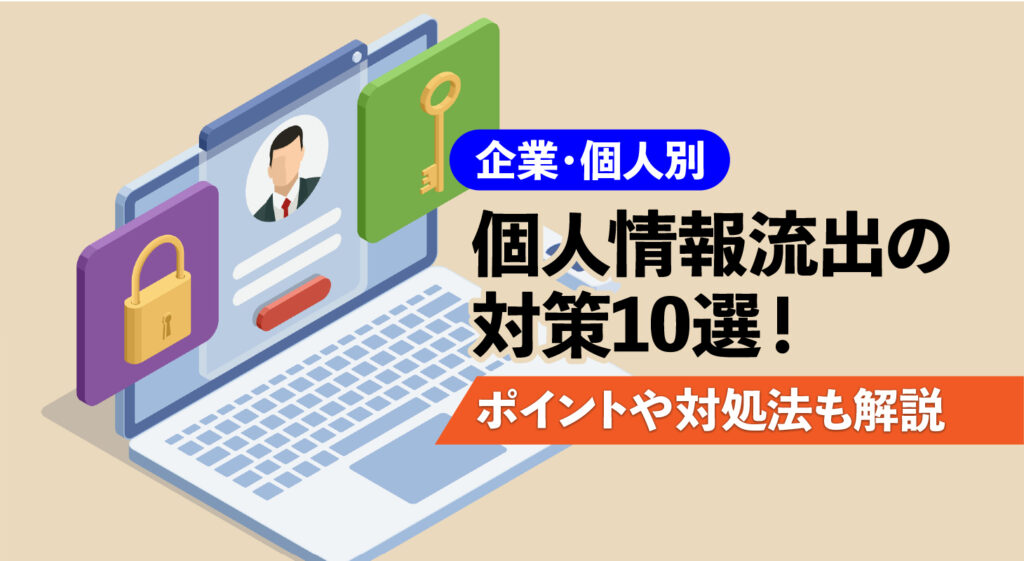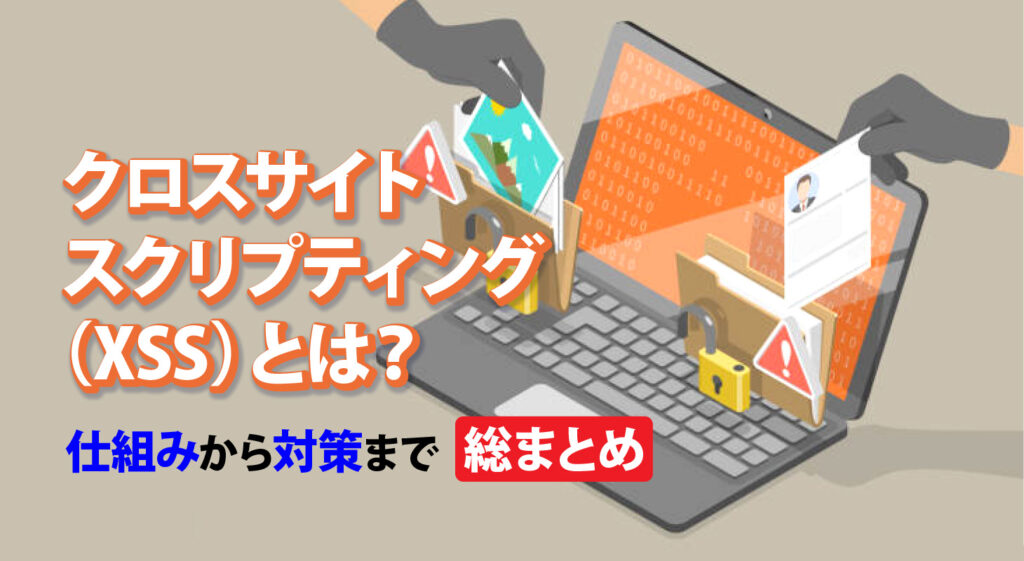Webサービスへのアクセス、アプリ導入などのたびに設定が求められるパスワード。しかし、使うサービスが増えるにつれ、パスワードの数も増え、「管理が面倒」「つい使い回してしまう」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。特に、パソコンやスマートフォンなど複数のデバイスやアカウントを利用していると、パスワード管理がさらに複雑になります。
安易なパスワードを設定したり、管理が甘いと、不正アクセスや情報漏洩といった深刻なセキュリティリスクにつながります。重要なサービスでのパスワード管理を怠ると、復元が難しくなるケースもあります。
そこで今回は、安全なパスワードの設定や管理方法について、具体的な手順を交えながらわかりやすく解説します。使い勝手がよく、安全性を高めるためのコツもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

今回のお悩み
Web上のさまざまなサービスの導入に伴い、管理するパスワードが増えて困っている。どのようなパスワードが危険なのか、また、安全に管理する方法を知りたい。

私が解説します!
便利なサービスを導入することで、当然ながら管理するパスワードも増えていきます。しかし、使いやすさを優先してパスワードを使い回したり、簡単に推測できるものを設定するのは危険です。不正アクセスやデータ流出を防ぐためには、安全性の高いパスワードを設定することが大切です。本記事では、安全なパスワードの設定方法や管理方法をわかりやすく解説します。
目次
( 1 ) 「安全なパスワード」とは?
そもそも「安全なパスワード」とはどのようなものでしょうか?
「安全なパスワード」とは、外部からの推測や機械的解析に耐える堅牢な認証情報を指します。特に、複数のアカウントを持つ場合、安全なパスワード管理が欠かせません。
総務省が示す基準に加え、NIST(米国国立標準技術研究所)のガイドラインSP800-63Bでも、パスワードの安全性を高めるためには「長さ」「複雑さ」「推測困難性」の3つが重要であるとされています。特に短いパスワードは総当たり攻撃(ブルートフォース※)に対して脆弱であるため、最低でも10文字以上が推奨されています。
サービスごとにパスワードを使い回さず、アカウントごとに異なるパスワードを設定することも、情報漏洩リスクを最小限に抑えるために欠かせません。また、Face
IDやTouch
IDといった生体認証を併用することで、パスワード自体が盗まれても安全性が保たれやすくなります。パスワード管理アプリを活用すれば、パスワードを忘れるリスクを軽減しつつ、セキュリティを強化できます。
強力なパスワードを設定し、適切に管理することが、自身のアカウントと情報を守るための基本です。普段から安全なパスワード作成を心がけ、セキュリティリスクを最小限に抑えましょう。
( 2 ) 不正アクセスや情報漏洩を招く原因とは
多くのWebサービスやシステムでは、IDとパスワードの組み合わせによって本人認証を行っています。しかし、サービス利用が増えるにつれて管理するパスワードの数も増え、その管理が不適切である場合、不正アクセスのリスクが飛躍的に高まります。特に、複数のサービスで同じパスワードを使い回す行為は、「パスワードリスト攻撃」と呼ばれる手法に対して脆弱です。
パスワードリスト攻撃とは、攻撃者が1つのサービスから漏洩したIDやパスワードを利用し、他のサービスにも不正ログインを試みる手口です。たとえば、あるSNSから流出したパスワードが、メールアカウントやクラウドストレージに使われていた場合、連鎖的に被害が拡大する恐れがあります。
他にも以下のようなパスワード設定や管理方法は、不正アクセスのリスクを高めるため注意が必要です。
- 安易なパスワードの設定:短い、単純、推測されやすいパスワードを設定する。特に「123456」「password」といった単純な組み合わせは避けるべきです。
- 不適切な保管:パスワードを付箋に書いてデスク周りに貼ったり、テキストファイルとしてPCやスマートフォンに保存したりすると、他人の目に触れやすく危険です。特にアカウント情報をメールで送信するのもリスクが高い行為です。
- デバイスのロック設定不足:スマートフォンやタブレットの画面ロックを設定していないと、端末を紛失した際に情報流出の危険が増します。Face IDやTouch IDを使って、万が一の場合でもセキュリティを確保できるようにしましょう
- デバイス間での使い回し:PC、スマートフォン、タブレットなど複数の端末で同一パスワードを設定していると、一つのデバイスが侵害された際に、他のデバイスへのアクセスも許されてしまいます。
このような「なんとなく使っている」「多分、大丈夫」という油断が、不正アクセス、アカウント乗っ取り、さらには個人情報や企業機密の漏洩といった重大なセキュリティインシデントを引き起こす原因となります。警察庁の統計でも、不正アクセスの手口として最も多いのは、IDやパスワードの不適切な管理や利用であり、令和5年における不正アクセス行為検挙件数のうち「識別符号窃用型」(IDやパスワードなどの情報を不正に利用すること)が全体の90%を占めていると報告されています。
特に、メールアカウントが乗っ取られると、アカウント復元や二段階認証の解除に使われるため、被害が広がるリスクが高まります。メールパスワードには特に注意が必要です。
( 3 ) 安易なパスワード設定がもたらす危険性
「自分だけは大丈夫」という思い込みから、安易なパスワード設定や使い回しを続けていませんか?先述の通り、パスワードに対する認識が甘いと、深刻なセキュリティリスクを引き起こします。
総務省「国民のためのサイバーセキュリティサイト」では、危険なパスワードとして以下のような例を挙げて注意を呼びかけています。

個人情報に関連するもの
自分や家族の名前、ペットの名前、生年月日、住所、車のナンバーなど、個人を特定しやすい要素を含むパスワードです。
- (例)yamada、tanaka、taro、hanako(名前)
- 19960628、h020315(生年月日)
- tokyo、kasumigaseki(住所)
- 3470、1297(車のナンバー)
- ruby、koro(ペットの名前)
一般的な単語
辞書に載っているような英単語ひとつだけを使ったパスワードは非常に危険です。
- (例)password、baseball、soccer、monkey、dragon
単純な文字列
同じ文字の繰り返しやわかりやすい並びの文字列は簡単に突破されやすいです。
- (例)aaaa、0000(同じ文字の組み合わせ)
- abcd、123456、abc123(単純な英数字の並び)
- asdf、qwerty(キーボードの配列)
- sms、passcode(よく使われるデバイス用語)
短すぎる文字列
10文字未満のパスワードはブルートフォース攻撃に対して非常に脆弱です。短すぎると、数秒で解析される危険性があります。
その他推測しやすいもの
電話番号や社員コード、ユーザーIDと同じ文字列など、公開されている情報や第三者が入手しやすいデータを含むパスワードは特に注意が必要です。メールアドレスそのものをパスワードにするケースも避けましょう。
参照:総務省/国民のためのサイバーセキュリティサイト「安全なパスワードの設定・管理」このような危険なパスワードが使われていないかをチェックし、同じパスワードを複数のサービスで使い回さないことを徹底しましょう。また、セキュリティ対策として、パスワード管理アプリを利用して強力なパスワードを生成し、安全に管理することをおすすめします。
( 4 ) 定期変更の必要なし? 安全性の高いパスワード設定と管理方法
安易に設定したパスワードがいかに危険かご理解いただけましたか?では、具体的にどのように安全なパスワードを設定し、管理すればよいのでしょうか。最新の動向を踏まえ、重要となるポイントを解説します。
安全性の高いパスワードの設定方法のコツ
安全なパスワードを作成するためには、推測されにくく、機械的な解析にも強い構造が必要です。以下に、安全性を確保しつつ管理しやすいパスワードを作成するためのポイントをまとめました。
1.覚えやすく、強力なコアパスワードを作成する
まず、基本となる「コアパスワード」を設定します。コアパスワードとは、覚えやすさと安全性を兼ね備えた基盤となるパスワードです。
<設定方法のポイント>
- 意味のあるフレーズを変形させる:好きなフレーズやことわざを、一部英語にしたり、数字や記号を挿入して作成します。
- 英大文字・小文字・数字・記号を組み合わせる:最低でも10文字以上の長さにすることが推奨されます。
例:
- 好きなフレーズ:「日曜はピザ」 → 「NichiPizza@2025」
- ことわざ:「石の上にも三年」 → 「3YearsOn@Stone」
コアパスワード自体は覚えやすく、どのサービスでも使える形にすることで、基本の負担を減らします。
2.サービスごとに異なる要素を付加する
コアパスワードを基本に、サービスごとの識別子を追加することで、パスワードの使い回しを防止します。
<設定方法のポイント>
- サービス名や用途を追加:コアパスワードに「Ml」「Ec」などの短縮名を加えます。
- 位置をランダムに変える:毎回同じ位置に追加するとパターン化されやすいため、前後や中間に挿入する工夫をします。
例:
メール(Mail)サービス用 → 「NichiPizza@2025Ml」
ECサイト用 → 「Ec3YearsOn@Stone」
サービス名だけでなく用途や年号を変えることで、セキュリティをさらに高めます。
3.生成ツールを活用して、ランダムなパスワードを作成する
手作業で複雑なパスワードを作るのは大変なので、パスワード生成ツールを利用して、安全かつランダムなパスワードを作成しましょう。パスワード生成ツールの自動生成機能を使うと、英大文字・小文字・数字・記号を含めたパスワードを簡単に生成できます。
<ツールの使い方のポイント>
- 長さと構成を指定:12〜20文字で英大文字・小文字・数字・記号を含める
- 覚えにくい場合はフレーズ形式で生成:単語をつなげた形にすることで、少しでも覚えやすくする
例:
- 自動生成パスワード:「vH9#xR!3pQ8w@M1Z」
- フレーズ形式:「Red!Horse!79%Blue!Sky」
参照:IPA/情報セキュリティ「使い回しを回避するパスワードの作成方法」
パスワードの管理
安全なパスワードを設定しても、その管理がずさんでは意味がありません。以下に、安全かつ効率的にパスワードを管理する方法を紹介します。
-
メモの保管
パスワードをメモした場合、他人の目に触れない安全な場所に保管することが大切です。手帳など、常に携帯するものに記載するのも一つの方法ですが、紛失リスクを考慮し、鍵付きの引き出しや金庫に入れるとより安全です。
-
パスワード管理ツールの活用
マスターパスワードを1つ覚えておくだけで、各サービスのIDやパスワードを安全に保管し、自動入力してくれるため便利です。また、パスワード管理をより安全かつ効率的に行うためには、アクセシビリティを考慮した管理ツールを選ぶことが大切です。これにより、操作ミスを減らし、誰でも使いやすくなります。さらに、不要になったパスワードや古いアカウント情報は速やかに削除し、リスクを減らしましょう。
-
ブラウザの記憶機能
ブラウザのパスワード記憶機能は便利ですが、共用PCや職場のパソコンでは特に注意が必要です。ブラウザデータが残っていると、他人がログインするリスクがあるため、マスターパスワードを必ず設定しましょう。定期的にブラウザデータをクリアし、信頼できない環境では使用を避けましょう。また、セキュリティ強化のため、利用しなくなったアカウントのパスワードは必ず削除してください。
-
多要素認証 (MFA) の活用
パスワードだけでなく、SMS認証コードや認証アプリを使った多要素認証(MFA)を活用することで、より強固なセキュリティを実現できます。特に、サインイン時に追加の認証ステップを求めることで、パスワードが漏洩しても不正アクセスを防ぐことが可能です。例えば、Face IDやTouch IDも、スマートフォンやタブレットのロック解除に使うだけでなく、特定のアプリやデータへのサインイン時に利用することで、さらなる安全性を確保できます。
パスワードの定期変更は必要なし!?
かつては「パスワードは定期的に変更すべき」という考え方が一般的でした。しかし、頻繁に変更を強制すると、かえって覚えやすい単純なパターン(例:Password01→Password02など)を使ってしまい、セキュリティが低下するという問題があります。特に、スマートフォンやPCなど複数デバイスで利用するパスワードの場合、変更後の更新が煩雑になりがちなため、パスワードが単純化してしまうケースが少なくありません。
そのため、近年では「定期的な変更」よりも、「十分に長く、複雑で、固有のパスワードを設定し、漏洩しない限り使い続ける」方がセキュリティ上有効だという考え方が主流になっています。パスワード自体が強固であれば、頻繁な変更は不要です。
ただし、パスワードを変更すべき重要なタイミングも存在します。特に以下の場合は、速やかにパスワードを更新しましょう。
- 利用しているサービスで情報漏洩事故が発生した、またはその疑いがある場合
-
特定のサービスがサイバー攻撃を受けたというニュースがあった場合
SNS、金融機関のアカウントなど、重要なサービスでの攻撃情報があれば、情報漏洩の発生有無にかかわらずパスワードを変更するのが無難です。
-
自分のパスワードが他人に知られた可能性がある場合
例えば、パスワードが書かれたメモを紛失したり、SNS上でパスワードを共有してしまった場合などです。スマートフォンやPCを盗まれたときも、端末に保存されているパスワードを変更する必要があります。
-
フィッシング詐欺サイトに誤ってパスワードを入力してしまった場合
偽のログインページにパスワードを入力してしまったと気づいたら、すぐにパスワードを変更し、二段階認証を有効にしてセキュリティを強化しましょう。
例えば、サクサのUTM「SS7000Ⅲ」はウイルスのデータパターンを自動更新することで最新のネットワークウイルスに対応。不正アクセス、ウイルス侵入など、インターネットから来るさまざまな脅威から統合的に社内ネットワークを守ります。また外部からの攻撃を防ぐだけでなく、内部からの情報漏洩リスクも抑えることができます。 さらにウイルス感染時は無料でPCウイルス駆除サービスが受けられます。専任の情報システム担当者を置く余裕がない会社でも、UTMを導入することで複雑化するサイバー攻撃のリスクに対応が可能です
( 5 ) 企業向け:セキュリティ強化のためのパスワードポリシー
企業の情報システムは、日々多数のアクセスを受けており、適切なパスワード管理を行わなければ、不正アクセスや情報漏洩のリスクが高まります。特に、社員が複数のデバイスを使って業務を行う場合、パスワードポリシーを徹底することが不可欠です。ここでは、企業として導入すべきパスワード管理ルールや運用ガイドラインを紹介します。
企業がセキュリティを強化するためには、安全なパスワードポリシーを策定し、全社員に徹底することが重要です。特に、クラウドストレージや社内システム、メールアカウントなど、業務で頻繁に利用するアカウント管理には、最新のセキュリティ基準を反映させましょう。
安全なパスワードポリシーを策定する際には、以下の基準を守ることが求められます。
パスワードポリシーの運用ガイドライン
安全なパスワードポリシーを策定した後は、従業員が適切に運用できるようサポートすることが重要です。以下のポイントを確認し、徹底を図りましょう。またパスワードポリシー導入後も、定期的に社員からのフィードバックを受け、実効性を確認しましょう。
1.セキュリティ研修の実施
全従業員がパスワード管理の重要性を理解し、適切な運用ができるように、定期的にセキュリティ研修を実施しましょう。研修を通じて、具体的なリスクや対策を共有し、実践力を高めることが大切です。
研修内容の例
- 不正アクセスの事例紹介
- フィッシング詐欺の手口と回避策
- パスワードの適切な設定と管理方法
2.IT管理者による定期監査
企業のセキュリティを維持するためには、IT管理者が定期的に監査を行うことが重要です。パスワードの強度チェックや不審なログイン履歴の確認、アクセス権限の適切な管理を定期的に実施し、問題を早期に発見できる体制を整えましょう。
3.緊急時対応マニュアルの整備
パスワードの漏洩や不正アクセスが発生した際には、迅速な対応が求められます。万が一の事態に備えて「緊急時対応マニュアル」を整備し、従業員に周知しておきましょう。マニュアルには、インシデント発生時の報告手順、影響範囲の特定、対応策の実施手順などを明確に記載しておくと安心です。
( 6 ) 「情報セキュリティ現状診断」でリスク対策
安全なパスワード設定と管理は、情報セキュリティ対策の重要な要素ですが、パスワード対策だけでは不十分です。セキュリティリスクを最小限に抑えるためには、従業員一人ひとりのセキュリティ意識を高めるだけでなく、組織全体でルールを整備し、適切に運用できているかを定期的に見直すことが不可欠です。
そこで役立つのが、サクサが提供している「情報セキュリティ現状診断」です。セキュリティに関する簡単な20の質問に「はい」「いいえ」で答えることで、自社の情報セキュリティ対策への取り組み状況がわかり、対策を講じるべき問題点が見えてきます。
診断結果を踏まえ、必要なツールのご提案なども行いますので、自社の現状把握の一環としてご活用ください。

( 7 ) まとめ
オンラインサービスの利用が不可欠となった現代社会では、パスワードポリシーを含む情報セキュリティ対策が、企業の規模を問わず重要課題の一つとなっています。サイバー攻撃の手法は日々進化しており、安易なパスワード設定や管理の甘さを突いた不正アクセスが増加しているのが現状です。
安全なパスワードの基本は、「長く」「複雑で」「使い回さない」ことです。パスワード管理ツールや多要素認証を活用し、組織全体でパスワードセキュリティへの意識を高めることが、大切な情報資産を守るための第一歩となります。適切なパスワード設定と管理を徹底し、日頃からセキュリティ対策を徹底する姿勢が重要です。
サクサでは「情報セキュリティ現状診断」をはじめ、中堅・中小企業の大切な情報を守る製品・サービスをご提案しています。ぜひお気軽にご相談ください。
課題解決に役立つ資料はこちら!
経営課題におけるトレンド情報や課題解決にお役立ていただける資料をまとめております。
ぜひ一度お読みください。