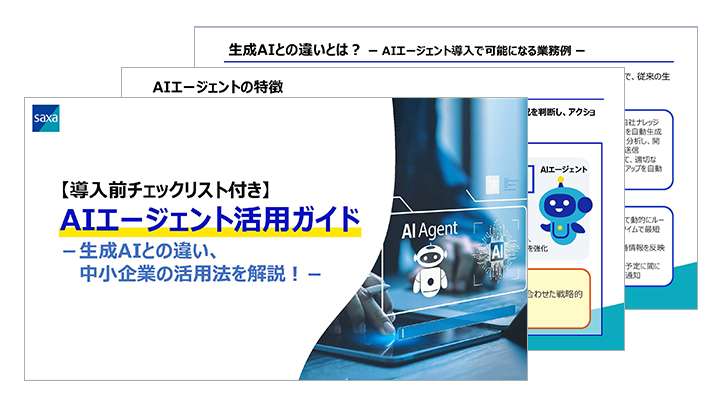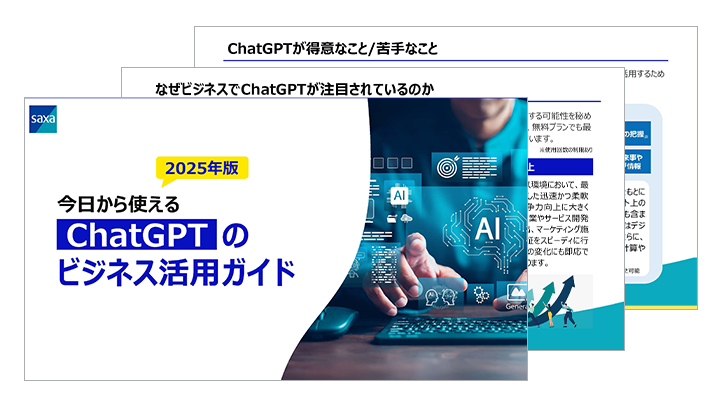▼課題解決に役立つ資料ダウンロードはこちら▼
→ 【導入前チェックリスト付き】AIエージェント活用ガイド → 有望な人材を確保する!中小企業のための人手不足解消ガイド → 2025年版今日から使えるChatGPTのビジネス活用ガイド現代の製造業界では、技術の高度化とグローバル競争の激化により、従来の自社完結型の製造形態では対応が難しくなりつつあります。そこで注目されているのが、ODM(Original Design Manufacturing)、OEM(Original Equipment Manufacturing)、EMS(Electronics Manufacturing Services)といった外部パートナーに製造を委託する形態です。この記事では製造委託を検討されている方に向けてODM、OEM、EMSのコスト構造やメリットの違い、最適な選び方までわかりやすく解説します。

今回のお悩み
新しい製品のアイデアはあるものの、開発や製造の専門家が社内にいない。製造を外部に委託したいけれど、ODM、OEM、EMSの違いがわからず、どの製造形態が自社に適しているのか判断が難しい。

私が解説します!
製造委託の主要な形態であるODM、OEM、EMSについて、その根本的な違いから、それぞれのコスト構造やメリットをわかりやすく解説します。さらに、自社の状況に合った最適なパートナーを見つけるための具体的なステップもご紹介します。
目次
( 1 ) ODM(Original Design Manufacturing)とは?製造委託の基本概念と具体例
ODM(Original Design Manufacturing)とは、製品の企画・設計から製造まで一貫して外部に委託する製造形態のことです。自社で製品のアイデアはあるけれど、設計や開発のリソースが足りない場合に最適です。ODMを提供する製造パートナーが保有する設計・製造のノウハウにより、短期間で製品開発が可能です。
ODMの具体例
スマートフォン業界
多くの世界的なスマートフォンブランドが、ODMを提供する製造パートナーと連携して製品開発を行っています。製造パートナーに「こういうコンセプトのスマホがほしい」と伝え、技術仕様の検討から設計、試作、量産まで一貫して委託します。製品開発を委託することで、ブランド側は市場戦略やマーケティングに集中することができます。
IoT機器開発
近年急成長しているIoT市場では、多様な業界の企業が自社のIoT機器の開発・製造を外部パートナーに委託しています。センサー技術、無線通信技術、クラウド連携機能など、複数の専門技術を組み合わせた製品開発において、ODMの包括的なサービスが威力を発揮しています。
ODMの最大の特徴は、設計段階から製品開発を委託できる点にあります。これにより、自社では企画・マーケティングに集中でき、製品開発のスピードアップと市場投入までの期間短縮が実現できます。
では、ODMとよく比較されるOEMやEMSはどのような製造委託形態なのでしょうか。それぞれ異なる特徴と適用場面がありますので、以下で詳しく解説します。

( 2 ) OEM・EMSとは?具体例でわかる違いと使い分け
OEM(Original Equipment Manufacturing)の具体例
OEMは自社で設計した製品の製造のみを外部に委託する、最も基本的な製造形態です。自社の技術を守りつつ、製造設備を持たなくても製品を大量生産できるので、自社ブランドにこだわりのあるメーカーや、独自の技術・ノウハウを生かしたい場合に最適です。例えば、精密機器メーカーが自社で開発した製品の量産を、OEMを提供する製造パートナーに委託するケースなどが該当します。
EMS(Electronics Manufacturing Services)の具体例
EMSは主に電子機器分野において、部品調達から実装・検査まで一連の製造工程を外部に委託する製造形態です。製品設計は自社で担いつつ、製造工程の効率化とコスト削減したい場合に最適です。自動車部品メーカーが電子制御ユニットの製造をEMSを提供する製造パートナーに委託するケースなどが代表的です。
ODM、OEM、EMSの比較表と適用場面
| 項目 | ODM | OEM | EMS |
|---|---|---|---|
| 委託範囲 | 企画・設計・製造 | 製造のみ | 製造・部品調達・実装 |
| 設計・開発の主体 | 受託側(製造パートナー) | 自社 | 自社 |
| 適用場面 | 新規参入・迅速な製品開発 | ブランド重視・独自技術活用 | 製造効率化・コスト削減 |
| コスト構造 | 高い初期投資 | 中程度の初期投資 | 低い初期投資 |
( 3 ) ODM、OEM、EMSにおけるコスト構造のポイント
ODMのコスト構造
ODMは設計から製造までを一貫して委託するため、設計・開発にかかわるコストが高くなります。具体的には、設計のためのエンジニアの人件費や設計ツールの費用などの研究開発(R&D)コスト、製造に必要な部品調達コスト、組み立てや生産ラインの運用にかかわる製造コスト、製品検査のための品質管理・テストコストなどが挙げられます。初期投資としては高くなりがちですが、自社は設計・開発の手間が省けるので、技術力がない場合や製品を迅速に市場に投入したい場合は最適です。
OEMのコスト構造
OEMは製造のみの委託のため、設計・開発は自社で行います。製造に特化したコスト構造のため、一般的にODMより費用は抑えやすい傾向があります。部品調達コストや製造コストが主な費用になります。ODMほど複雑なテストは不要な場合が多く、品質管理・テストコストも抑えられる傾向にあります。ただし、コストは発生しませんが、自社で設計をする必要があり、自社に技術力やリソースが必要になります。
EMSのコスト構造
EMSは電子機器を効率的に製造することに特化しているため、初期投資は最も低く抑えられます。設計は自社が用意する場合もあれば、ODMのように製造パートナーが設計支援まで行うケースもあります。電子機器は精密さが求められるため、品質管理・テストは専門のスタッフが対応をします。EMSを提供する製造パートナーはグローバルな生産ネットワークを持つため、物流コストがやや高くなる場合もあります。
( 4 ) ODM、OEM、EMS における活用の実践的メリット
ODMを活用するメリット
設計の専門知識が不要
ODMは設計から製造までを製造パートナーが担当するため、自社で設計の専門知識や技術力を持たなくても製品を開発することができます。製造パートナーに依頼をすれば、専門家がデザインや機能の提案をしてくれるので、自社にリソースがなくても新製品を製造、販売することができます。
開発期間の大幅短縮
製造パートナーが持つ設計・開発のノウハウと実績を活用することで、例えば従来6ヶ月~1年かかっていた製品開発期間を、3〜4ヶ月程度に短縮することが可能です。これにより自社で設計・開発を行うより早く市場に製品を投入できます。
コストの最適化
設計と製造を一括で管理するため、効率的なコスト管理が可能です。設計・製造を製造パートナーが行うため、仕様の変更や調整がスムーズで、追加コストが発生しにくい点も大きな強みです。
スケーラビリティの向上
ODMを提供する製造パートナーは大量生産のノウハウ、能力を有しているので、需要の変化に柔軟に対応することができます。大規模な生産ラインやサプライチェーンを管理しているので、少数生産から大量生産まで対応ができ、市場での売れ行きに応じて生産量を調整できます。
OEMを活用するメリット
製品の独自性の維持
OEMでは自社で設計や仕様をコントロールするので、ブランド独自の製品を実現しやすくなります。ODMでは製造パートナーが設計を行うため、競合他社と似た製品になってしまう可能性がありますが、OEMでは自社独自のデザインや機能を反映することができます。これにより、自社ブランドの個性や差別化を図ることが可能です。
高い品質管理のコントロール
OEMでは、自社が仕様や品質基準を細かく指定できるため、自社の意図した品質を維持しやすくなります。製造パートナーは、あらかじめ設定された基準にもとづいて製造を行うため、品質管理も高い水準で実施されやすいのが特徴です。これにより、製品の安定供給や顧客満足度の向上、ブランド価値の維持にもつながります。
自社リソースの集中
製造のみをアウトソーシングするので、自社は設計、マーケティング、販売などのコア業務のみにリソースを集中させることができます。特に中小企業や新興企業にとっては、限られたリソースを効率よく使用することで、自社のブランド戦略などに注力できます。
EMSを活用するメリット
電子機器製造の専門性
EMSは電子機器の製造に特化した製造パートナーへの委託により、高度な技術力と専門知識を生かした高品質な生産が可能です。回路基板の組み立てや精密な電子部品の配置、ソフトウェアのインストールなど電子機器に特化した製造技術を有しているため、特に技術的に複雑な製品(医療機器やIoTデバイスなど)で、その専門性を生かすことができます。
グローバルサプライチェーンの活用
EMSを提供している製造パートナーの多くは世界中のサプライヤーや生産拠点とのネットワークを持ち、部品調達や物流を最適化できます。複数の生産拠点を持っていることが多いため、地域ごとの生産戦略が提供できるのも魅力の一つです。地域ごとの需要に応じて生産拠点を切り替え、コストを削減することで自社のグローバル市場での競争力を高めることができます。
技術革新への対応力
EMSを提供している製造パートナーは最新の製造技術や業界トレンドに精通しており、技術革新を迅速に製品に反映することができます。電子機器業界の最新技術・情報を常にアップデートしているため、自社に専門的な知識が不足していても、トレンドに追随することが可能です。
( 5 ) 自社に最適な製造パートナーを選定する5つのステップ
新しい製品を世に出すとき、どの製造形態のパートナーと組むかは大きな決断になります。ODMは設計から製造まで任せられる製造形態、OEMは自社で設計した製品を製造してもらう製造形態、EMSは特に電子機器の効率的な生産に特化した製造形態です。これらから最適なパートナーを選ぶには、計画的なアプローチが必要です。

ステップ1:自社の現状分析
まず、自社では何ができて、何が足りないのかを見極めます。製品をつくるには、設計のスキル、製造の設備、資金力、そしてビジネス戦略が重要です。例えば、自社の技術者がどれくらいのスキルを持っているか、設計ツールや過去の開発経験があるかを確認します。製造面では、工場や生産ラインの有無、品質を保つ仕組み、コスト競争力があるかを考えます。さらに、経営の視点では、どの市場に製品を投入したいか、どれくらい早く製品を発売する必要があるか、予算はどの程度かを整理します。
この現状分析で、自社に足りない部分(設計力や生産能力など)を明確にすることで、どのタイプのパートナー(ODM、OEM、EMS)が必要かを判断する材料にできます。
ステップ2:製品特性の分析
次に、つくりたい製品の特性を分析します。製品開発がどれくらい技術的に複雑なのか、市場での需要量はどのくらいなのかを考える必要があります。例えば、最新のAI機能を持つスマートフォンをつくるなら、高度な技術が必要なため、設計のプロに任せられるODMが向いているかもしれません。一方、シンプルなデザインの家電なら、自社で設計してOEMを提供するパートナーに製造を依頼する方がよい場合もあります。市場投入のスピードも重要です。競合他社が似た製品を出す前に発売したいなら、迅速な生産が可能なパートナーが必要です。また、売れると予想される数量(例えば1万台か100万台か)も、パートナーを生産能力から判断する材料になります。
ステップ3:最適な製造形態を選ぶ
製品や自社の状況に応じて、ODM、OEM、EMSのどれが最適かを決めます。ODMは、設計から製造まで任せたい場合に最適です。製造業が初めてのスタートアップや、技術者が少ない中小企業、いち早く製品を市場に投入したい企業、設計のノウハウを学びたい企業にはODMが適しています。一方、OEMは、自社で独自の技術や特許を持ち、ブランドの個性を強調したい企業に向いています。例えば、独自のデザインで差別化したいアパレル企業や、特許技術を使った家電メーカーはOEMを選ぶことが多いです。EMSは、電子機器の生産に特化しており、設計が完成していて大量生産やコスト削減を目指す場合や、グローバル市場を狙う企業に最適です。
ステップ4:パートナー選定基準の設定
このステップではパートナー選びの基準を具体的に設定します。まず、過去に似た製品をつくった実績があるか、最新技術に対応できるスキルやスタッフがいるかを確認します。例えば、スマートウォッチをつくりたいなら、ウェアラブルデバイスの製造経験があるパートナーが理想です。
次に、品質管理の能力も重要です。ISO9001のような品質基準の認証を持っているか、不良品を減らすための検査設備や取り組みがあるかをチェックします。次に大量生産が可能か、急な増産や減産に対応できる柔軟性があるか、納期を守れる実績があるかを確認します。最後に、円滑なコミュニケーションができるかも重要です。プロジェクトの進捗をしっかり報告してくれるか、問題が起きたときに迅速に対応してくれるかを確認します。
ステップ5:パートナー評価と選定
最後に、候補となるパートナーを検討し、最適な企業を選定します。そして、自社で提案依頼書(RFP)を作成します。これは、パートナーに「こんな製品をつくりたい」と伝える書類で、技術仕様、品質の基準、納期、コストの目標を明確に書きます。プロジェクトの管理方法や、改善提案の姿勢も評価ポイントに含めるとよいでしょう。
複数の候補企業から提案を受け取り、技術力、品質、コスト、納期を総合的に比較します。安さだけで選ぶのではなく、長期的な信頼関係を築けるかも重要な判断材料です。最終決定前には、工場の見学をして実際の生産環境を確認したり、既存の顧客からの評判を聞いたり、企業の財務状況や災害時の事業継続計画(BCP)が整備され、実効性のある内容かどうかを慎重に精査します。
( 6 ) 製造委託を成功させるための実践的アプローチ
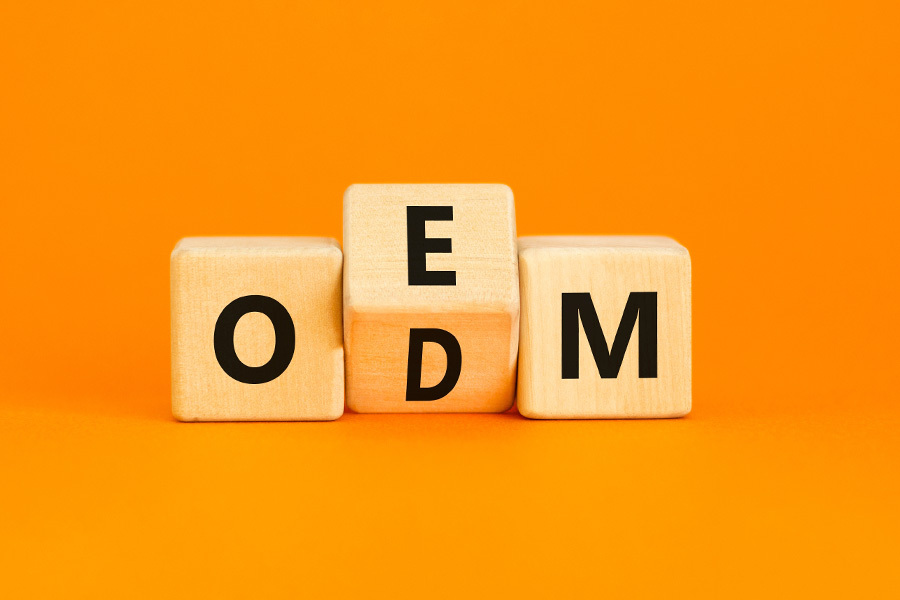
パートナー選定の後、製造委託(ODM、OEM、EMS)を成功させるには、効率的なプロジェクト管理、技術情報の戦略的活用、継続的改善の仕組みが欠かせません。これらは、製品の品質を高め、コストを抑え、市場競争力を強化するための鍵です。以下では、専門的な手法を解説し、製造委託を成功に導く実践的なアプローチを紹介します。
プロジェクト管理で効率と品質を両立
製造委託を成功させるには、自社と製造パートナーとの間でプロジェクト管理を徹底することが重要です。プロジェクト管理とは、製品開発のスケジュール、コスト、品質を計画通りに進めるための仕組みです。例えば、スマートフォンの製造を委託する場合、設計から生産、納品までの各段階を明確に管理することで、遅延や品質トラブルを防げます。
具体的には、プロジェクト管理ツールを活用して、主要なマイルストーン(例:設計完了、試作品完成、量産開始)を設定します。これにより、進捗が一目でわかり、遅延のリスクがある工程を早めに発見できます。
さらに、製造パートナーとの定期的な進捗会議を開催し、課題を迅速に解決する仕組みを整えることが効果的です。例えば、週1回のビデオ会議で、部品調達の遅れや品質テストの結果を共有し、問題が小さいうちに対策を講じます。これにより、スムーズなプロジェクト進行を実現します。結果として、開発期間を短縮しつつ、期待通りの品質を確保できます。
技術情報管理によるコスト最適化
製造委託では、技術情報の適切な管理がコスト削減と効率化の鍵です。技術情報とは、製品の設計図、仕様書、部品リストなど、製造に必要なデータの総称です。この情報を製造パートナーと正確かつ効率的に共有することで、設計変更や仕様ミスによる追加コストを防げます。スマートウォッチの製造を委託する場合、設計図の細部(例:バッテリーの配置や素材の指定)が曖昧だと、製造中に修正が必要になり、時間とコストが増大します。これを防ぐには、PLM(Product Lifecycle Management)システムのようなツールを活用し、設計データや変更履歴を自社で一元管理します。
PLMシステムは、製品の企画から設計、製造、販売、廃棄に至るまでのライフサイクルを管理するためのシステムで、製品の情報を製造パートナーとリアルタイムで共有できます。これにより、部品の仕様変更が必要になった場合、すぐに全員が最新情報にアクセスでき、無駄なやり直しを減らせます。さらに、過去のプロジェクトのデータを蓄積することで、次回の製品開発で同様のミスを防ぎ、効率を高められます。
継続的改善による競争力強化
製造委託の成功には、製造パートナーとの継続的な改善活動が欠かせません。電子機器の製造では、生産ラインでの小さな非効率や不良品の発生を減らすことで、大きなコスト削減が可能です。そのためには、製造パートナーと共同で改善提案の仕組みを構築します。具体的には、製造現場の作業員やエンジニアからの提案を収集し、定期的に評価する制度を設けます。
例えば、月に1回の改善会議で、生産ラインのレイアウト変更や検査プロセスの簡略化を議論し、実行可能なアイデアを採用します。
さらに、最終目標を達成するためのプロセスにおける中間目標KPI(Key Performance Indicator)を設定し、改善の成果を数値で評価します。例えば「不良品率を1%から0.5%に下げる」「生産時間を10%短縮する」といった目標を立て、達成度を追跡します。このように、製造パートナーとの協力的な改善活動は、単なるコスト削減を超え、自社の長期的な競争力強化につながります。
( 7 ) 製造業界のトレンドと今後の展望
2025年の製造業界は、デジタル技術の進化、環境への配慮、企業間の新たな協力関係によって大きな変革を迎えています。ODM、OEM、EMSといった製造委託形態も、これらの変化に適応し、競争力を高めています。ここでは、DX(デジタルトランスフォーメーション)、サステナビリティ、戦略的パートナーシップという3つの主要なトレンドを、詳しく解説します。
DX(デジタルトランスフォーメーション)による製造革新
製造業界は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の波に乗り、劇的な進化を遂げています。DXとは、デジタル技術を活用して業務や製品を効率化・高度化する取り組みで、Industry 4.0(第四次産業革命)の核となる考え方です。AI(人工知能)は、生産ラインのデータを分析して機械の故障を事前に予測します。また、IoTは、工場内の機器をリアルタイムでつなぎ、生産状況を一元的に監視する「スマートファクトリー」を実現しています。近年ではデジタルツイン技術も注目を集めており、製品や生産ラインの仮想モデルをデジタル空間に構築し、設計や製造のシミュレーションを行うことで、製造・生産の効率と品質を向上させています。
ODMなどを提供する製造パートナーは、こうした技術を積極的に取り入れ、設計から生産までのプロセスを最適化しています。今後、生成AIやエッジコンピューティングの進化により、リアルタイムでのデータ分析や意思決定がさらに進み、製造の柔軟性と競争力が一段と高まると予測されます。
サステナビリティへの対応
最近では環境への配慮が、製造業界の最重要課題として浮上しています。サステナビリティ(持続可能性)は、地球環境を守りながらビジネスを続けるための戦略で、ESG(環境・社会・ガバナンス)の枠組みにもとづいて推進されています。また、廃棄物の削減やリサイクル材料の使用も進んでいます。スマートフォンの筐体にリサイクルプラスチックを採用したり、生産過程で出る金属スクラップを再利用したりする企業も増えてきています。
さらに、サプライチェーン全体での環境負荷低減も求められています。部品調達から物流、廃棄までを見直し、環境に優しいプロセスを構築することで、自社は顧客や投資家からの信頼を得ることができます。サステナビリティは、長期的な成長と社会的責任を両立させる取り組みです。今後は、カーボンニュートラル(CO2排出実質ゼロ)を目指す企業が増え、グリーン認証(例:ISO14001など)を取得する製造パートナーが競争優位性を得ると思われます。製造パートナーを選ぶ際はサステナビリティへの対応ができているかも基準のひとつとして検討しましょう。
新しい製造パートナーシップ
製造業界では、従来の発注者と受注者の関係を超えた、戦略的なパートナーシップが主流になりつつあります。これは、単なる製造委託ではなく、技術やリスクを共有する密接な協力関係を築くアプローチです。例えば、自社と製造パートナーが共同で新技術を開発したり、市場リスクを分担したりすることで、競争力を高めています。具体的には、AIチップの開発において、EMSを提供する製造パートナーが部品調達や生産だけでなく、設計段階から技術提供に参加するケースも増えています。
このようなパートナーシップは、双方の強みを最大限にいかします。需要予測が難しい新製品の場合、自社と製造パートナーが共同で在庫管理や販売戦略を立てることで、リスクを軽減できます。今後、データ共有プラットフォームやブロックチェーン技術を活用した透明性の高いパートナーシップがさらに進化し、迅速な意思決定と技術革新が期待されています。
( 8 ) まとめ
ODM、OEM、EMSは、それぞれ異なる特徴と適用場面を持つ製造委託サービスです。自社の状況と製品特性を正確に分析し、最適な製造形態とパートナーを選定することで、競争力の向上と事業成長を実現できます。
サクサ株式会社では、通信機器からクラウドサービスまで幅広い領域で、独自のODMサービスを展開し、中堅・中小企業のDX推進を支援しています。ハードウェア、ソフトウェア、およびシステム設計も含めた総合的な開発力により、「モノをつくる」だけではなく、「サービス・システムもつくる」(=モノづくりas a Service)を実現します。
中堅・中小企業のDX推進を支援し、高品質なモノづくりと顧客要望に応える確かな技術力・国内一貫生産体制を強みとして、お客さまのビジネス成功に貢献しています。製造委託をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
課題解決に役立つ資料はこちら!
経営課題におけるトレンド情報や課題解決にお役立ていただける資料をまとめております。
ぜひ一度お読みください。