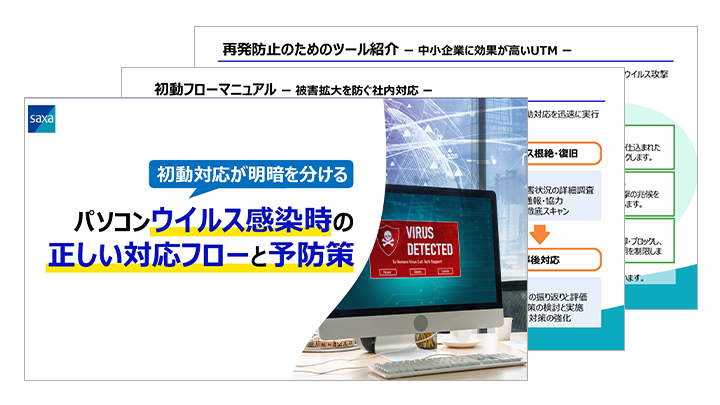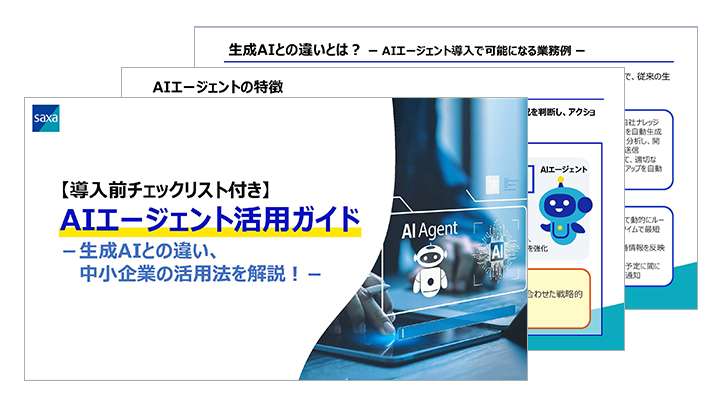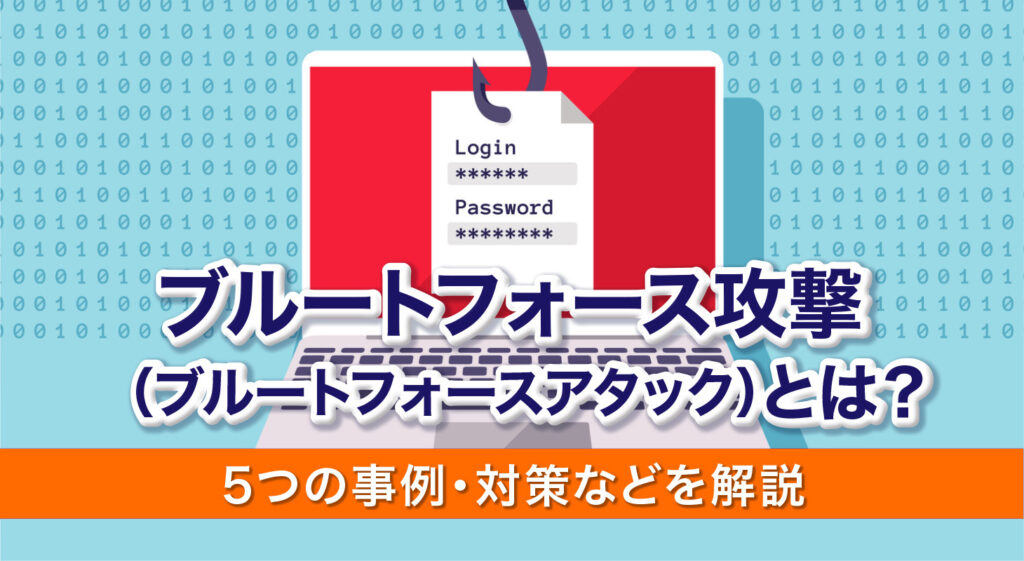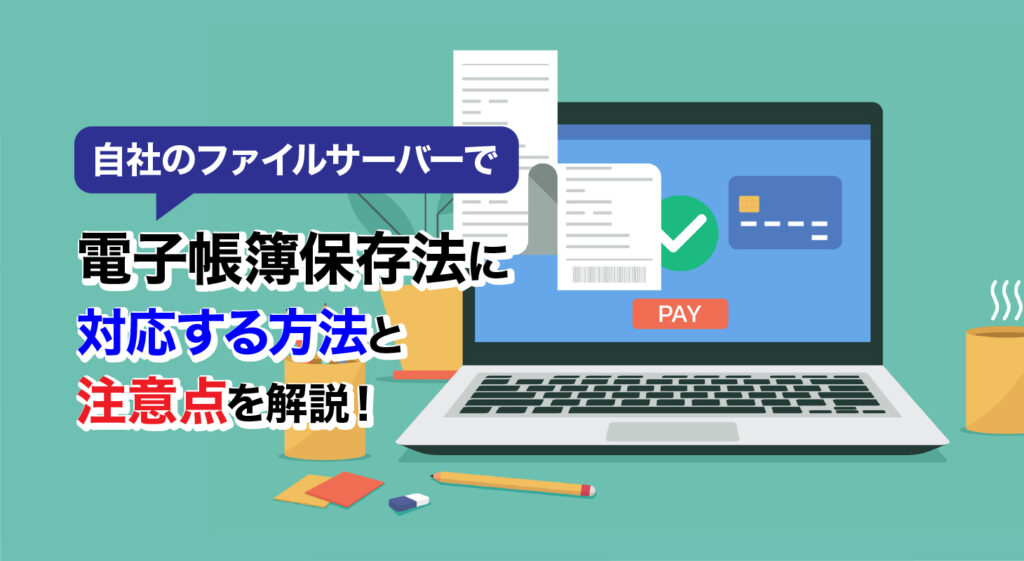2022年1月に施行された電子帳簿保存法では、帳簿書類の電子保存について、大幅な要件緩和が行われました。翌年3月には「令和5年度税制改正」が公表され、保存要件のさらなる規制緩和が進みました(2024年1月1日施行)。今回は改正のポイントから電子化するうえで必要な対応、効率的な対応ツールまでをわかりやすく紹介します。

今回のお悩み
電子帳簿保存法の改正を受けて、業務効率を上げるためにシステムの導入と社内のワークフローを整備したい。導入に向けて気をつけるポイントや必要な対応を知りたい。

私が解説します!
急速なデジタル化に伴い、電子取引や関係書類などが日々増加しています。電子帳簿保存法の改正によって、要件の緩和が行われる一方で罰則が強化されています。改訂のポイントを理解し、電子取引データの適切な取り扱いとその対策を行いましょう。
目次
( 1 ) 電子帳簿保存法の改正ポイント
電子帳簿保存法は、規制緩和などの要請を受けて2015年から順次改正されています。要件が大幅に緩和された2021年および2023年の主な変更点とポイントは以下の通りです。
■2021年(2022年1月1日施行)の改正ポイント
| 主な変更点 | 改正前 | 改正後 | 対象区分 |
|---|---|---|---|
|
事前承認制度の 廃止 |
開始3か月前までに税務署長への申請が必要 | 事前申請が不要 |
電子帳簿保存 スキャナ保存 |
|
タイムスタンプ 要件の緩和 |
受領者の自署後、3営業日以内にタイムスタンプを付与 |
・自署…不要 ・タイムスタンプ…付与期間を最長2か月に延長 |
スキャナ保存 電子取引 |
| 検索要件の緩和 | 「取引年月日」「取引金額」「勘定科目」項目の複雑な検索要件あり | 「取引年月日」「取引金額」 「取引先」のみに大幅緩和 |
電子帳簿保存 スキャナ保存 電子取引 |
| 紙保存の廃止 | 出力して紙での保存も可 | 紙保存は認めず、電子データ保存を義務化 | 電子取引 |
|
適正事務処理 要件の廃止 |
相互牽制、定期検査の要件あり | 適正事務処理が不要 | スキャナ保存 |
|
不正に対する 罰則強化 |
通常の重加算税 | 通常の重加算税に10%を加算 |
スキャナ保存 電子取引 |
■2023年(2024年1月1日施行)の改正ポイント
| 主な変更点 | 改正前 | 改正後 | 対象区分 |
|---|---|---|---|
|
優良な電子帳簿の 対象範囲を明確化 |
①仕訳帳 ②総勘定元帳 ③その他必要な帳簿(全て)が対象 | ③その他必要な帳簿の 対象範囲を明確化 |
電子帳簿保存 |
|
スキャナ保存の 要件緩和 |
・入力者等の情報が必要 ・データ情報(解像度・階調・大きさ)を保存 ・全ての保存書類と帳簿との相互関連性が必要 |
・入力者等の情報不要 ・データ情報の保存不要 ・相互関係性を求める書類を重要書類に限定 |
スキャナ保存 |
| 検索機能の全てを不要とする措置の対象者を拡大 | 基準期間の売上高が「1,000 万円以下」の保存義務者が対象 | 基準期間の売上高が「5,000 万円以下」の保存義務者に拡大 |
電子帳簿保存 スキャナ保存 電子取引 |
|
猶予措置を 新たに整備 |
宥恕措置を設置(適用期限:2023年12月31日) | 宥恕措置は適用期限の到来をもって廃止、猶予措置を設置 |
電子帳簿保存 スキャナ保存 電子取引 |
( 2 ) 改正電子帳簿保存法に対応しなかった場合の罰則
電子帳簿保存の要件が緩和され、帳票類の電子化を進めやすくなった一方で、違反や不正行為が行われた場合の罰則は強化されています。2024年1月以降、保存要件に対応しなかった場合には、罰則の対象となる可能性があります。
●青色申告の取り消し対象になる
電子帳簿保存法に違反すると、青色申告の承認が解除される場合があります。最大65万円の特別控除などの特例が適用外となり、青色申告では対象外の「推計課税」が適用される可能性もあります。
●重加算税を課せられる
税務調査により、電子取引データの記録事項に悪質な改ざんや隠蔽などが発覚した場合、通常の追徴課税35%に10%を加重された重加算税を収めなければなりません。さらに帳簿書類に不備や誤記が多い場合も、推計課税が課せられる可能性があります。
●会社法により過料を科せられる
電子帳簿保存法の違反は、同時に会社法に抵触する可能性があります。保存義務に違反や不正が認められた場合、会社法の規定により100万円以下の罰金が科せられます。
( 3 ) 改正電子帳簿保存法で必要な対応
宥恕措置が適用される2023年12月末までは、電子取引データを出力して紙で保存しても、税務調査時に対応できれば問題ありませんでした。しかし、2024年以降は電子データ保存が義務化され、保存要件に従ったデータ保存が求められます。
改正電子帳簿保存法への適切な対応を行うための対策として、以下の2点が挙げられます。

●改正電子帳簿保存法に対応した経理システムの導入
電子帳簿保存法の保存区分は、大きく3種類(電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引)に分けられます。各区分には細かい保存要件があり、保管期間なども異なるため、管理には多くの手間を要します。経理業務の負担軽減のため、改正電子帳簿保存法に対応したシステムの導入が必要です。
●社内のコンプライアンス教育の実施
電子取引データを正しく保存し、不正や漏洩が起こらないようにするためには、運用ルールの見直しと社員教育によるコンプライアンス意識の強化が重要です。ルールの徹底とコンプライアンス教育は、電子データを扱う担当者だけでなく、社員全員に対して定期的に行いましょう。
( 4 ) 電子取引データの保存・管理に最適なツール
帳簿書類の電子化やデータ保存には、適切なシステムの導入が重要なポイントになります。ここからは、サクサの製品による具体的な対策例をご紹介します。サクサでは、改正電子帳簿保存法に対応した各種機能を搭載した、電子データ管理ゲートウェイ「DG1000」を提供しています。
●電子取引データを簡単保存・検索
電子取引データに定められている検索要件では、取引日や取引先、取引金額の各属性から検索できることが求められます。「DG1000」は検索要件に加え、インボイス番号、分類(請求書・領収書・その他)による検索が可能です。
●インボイス制度にも対応
電子帳簿保存法では、請求書および領収書にインボイス登録番号の記載が必要です。「DG1000」は索引簿エクスポート機能により、インボイス登録番号の記載漏れを簡単に抽出できるため、仕入れ税額控除の記載漏れを防止できます。
●改ざんや不正処理を抑止
電子取引データの訂正や削除を行う場合、訂正や削除をした日付・内容・理由・担当者名等を残す必要があります。「DG1000」は、電子取引データの登録や訂正、削除の操作履歴を記録できます。「誰が・いつ」操作したのかを確認できることで、改ざんや不正の抑止にもつながります。
( 5 ) まとめ
今回は電子帳簿保存法の改正ポイントや対応しなかった場合の罰則、必要な対策について解説しました。電子帳簿保存法の改正によって用件が緩和された一方、不正や悪用を防ぐための罰則は厳しくなっています。気づかない間に違反してしまわないよう、法改正に関する情報は定期的に確認が必要です。また、改正電子帳簿保存法に対応した社内環境を整備することにより、電子取引データを簡単かつ安全に保存・管理することができ、業務の効率化にもつながります。
記事の中でご紹介したサクサ電子データ管理ゲートウェイ「DG1000」をはじめ、さまざまなソリューションを通して、中堅・中小企業の課題解決をサポートさせていただきます。ぜひ気軽にお問い合わせください。
課題解決に役立つ資料はこちら!
経営課題におけるトレンド情報や課題解決にお役立ていただける資料をまとめております。
ぜひ一度お読みください。