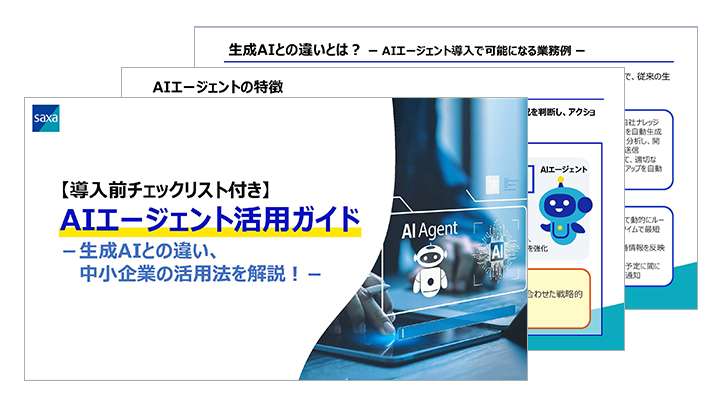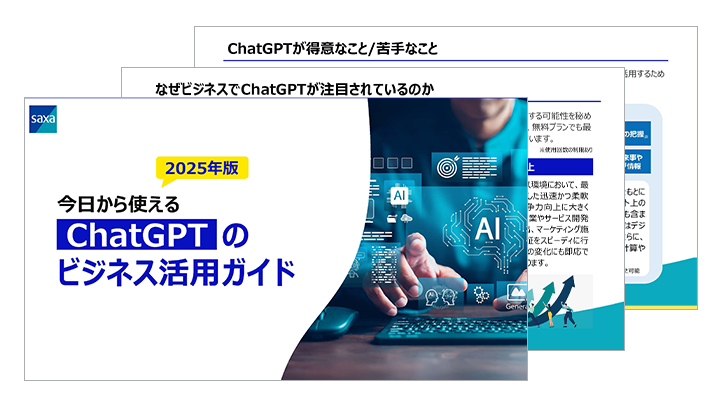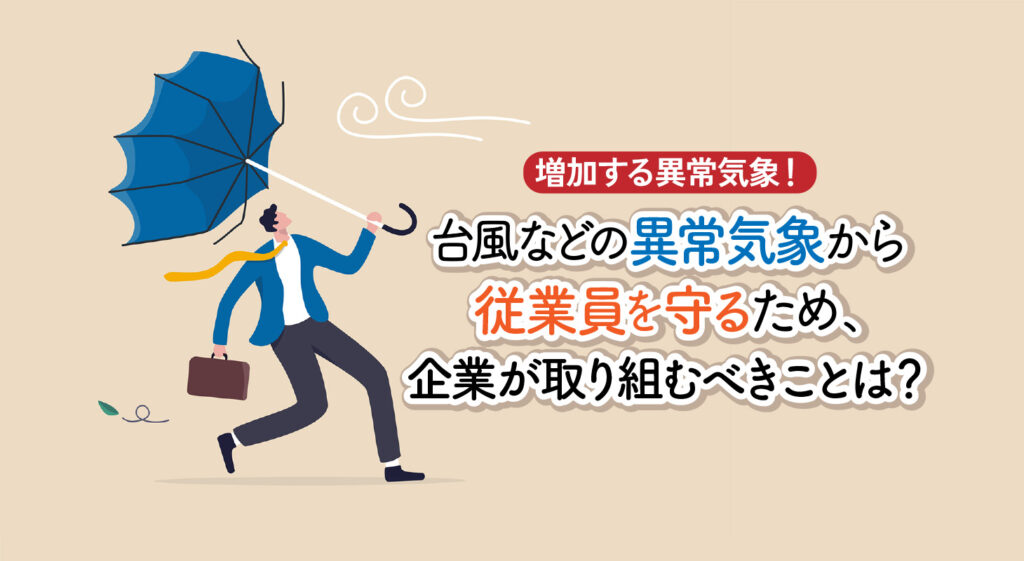▼課題解決に役立つ資料ダウンロードはこちら▼
→ 【導入前チェックリスト付き】AIエージェント活用ガイド → 2025年版今日から使えるChatGPTのビジネス活用ガイド → 中小企業のIT担当向け今日から始めるランサムウェア対策実践ガイド社員のモチベーションは、会社の業績をアップさせる重要な要素の一つです。継続的なモチベーション管理は全社で取り組むべき課題ですが、社員のモチベーション向上に悩む経営者や管理職の方も多いのではないでしょうか。社員が高いモチベーションを維持しつつ、働きがいを持って仕事に取り組むようにするにはどうすればよいのか、押さえるべきポイントや効果的な具体策を紹介します。

今回のお悩み
部下の仕事に対する意欲が感じられず、どのような方法でやる気を引き出せばよいか悩んでいる。社員のモチベーションを向上させるためのポイントや具体的な方法を知りたい。

私が解説します!
社員のモチベーションは業務の質や生産性向上に直結しやすく、モチベーションが低い状態を放置すると、業績の悪化や離職にもつながりかねません。今回は、社員のモチベーションが低下する原因、モチベーションを向上させるために役立つポイントや方法、企業の取り組み事例を紹介します。
目次
( 1 ) 社員のモチベーションが下がる原因
社員のモチベーションが下がる主な原因として、以下の4つが挙げられます。モチベーションの低下は、複数の要因によって生じる場合もあります。
待遇や働き方への不満
給与や労働時間などに対する不満は、社員のモチベーションに大きな影響を与えます。給与が低いと正当に評価されていないと感じやすくなり、長時間労働が常態化している場合は、心身ともに疲弊してモチベーションの維持が難しくなります。
仕事内容によるストレス
仕事に対して不満やストレスを感じている状況では、やりがいを感じられなくなります。自分の能力やスキルを活かせない、適性に合わない業務を任されることは不満につながります。また、過度なノルマや責任が重すぎる業務はストレスの原因になります。
人間関係の問題
社員同士や上司との関係性がよくない、さらにはパワハラやモラハラが起きている職場は、社員の精神的な負担が増大します。また、不安や悩みを相談できる相手がいない状況では、孤立感や孤独感が生まれやすくなり、仕事への意欲が低下します。
将来性に関する不安
会社の成長や業界の先行きに不安を感じると、将来に希望が持てなくなり、仕事に対する意欲が低下します。会社の経営方針に共感できない場合も、会社や仕事に対する不信感の要因となり、モチベーションの低下や喪失につながる可能性が高くなります。
( 2 ) 社員のモチベーション向上・管理で押さえるべき3つのポイント
モチベーション向上を図るには、多角的な視点からのアプローチが有効です。社員のモチベーションの向上・管理を行う際に効果的なポイントを3つ紹介します。
〈ポイント1〉2種類のモチベーションの特徴を知る
モチベーションを「外発的動機付け」と「内発的動機付け」に分ける考え方があり、これを適切に活用することで、社員のモチベーション向上や持続的な効果が期待できます。
| 外発的動機付け | 内発的動機付け |
|---|---|
| 給与、評価、昇進など、外部要因によって生じる。業績や成果に基づく給与体系や明確な評価制度などが該当し、短期間で効果が出る。慣れによって時間とともに効果が薄れるため、長期的な維持には限界がある | 興味・関心、自己成長など、内部要因によって生じる。適性に合った職責、研修や異動などによるスキルアップが該当し、効果が出るまで時間がかかる。やりがいが原動力となるため、長期的な効果が期待できる |
〈ポイント2〉「ハーズバーグの二要因理論(※1)」から考える
ハーズバーグの二要因理論では、仕事に対する満足と不満足は、それぞれ異なる要因によって引き起こされると考えられています。
| 動機付け要因 | 衛生要因 |
|---|---|
| 満足感をもたらす要因で、「達成感」「承認」「やりがい」「責任」「昇進」などがある。満たされなくても不満にはつながらないが、満たされると仕事への意欲やモチベーションが向上する | 不満足を引き起こす要因で、「給与・待遇」「福利厚生」「経営理念・経営方針」「人間関係」などがある。不足すると不満が生じるが、満たされてもモチベーションには大きく影響しない |
〈ポイント3〉社員のやりがいを尊重する
社員が自身の役割にやりがいを感じ、主体的に取り組める環境を整えることが重要です。社員の働きを適正に評価することにより「会社から認められている」という実感が得られます。表彰制度による評価は、会社全体のモチベーション向上にもつながります。
※1 ハーズバーグの二要因理論:アメリカの臨床心理学者フレデリック・ハーズバーグが提唱。仕事に対する欲求を2つの要因に分類したモチベーション理論( 3 ) 社員のモチベーションを向上させる5つの方法
社員のモチベーションを向上させるには、どのような方法があるのでしょうか。効果的な5つの方法を紹介します。

| 明確な目標設定 | 目標を明確化し、仕事への意欲を高める。会社のビジョンと個人の目標を紐づけ、業務が組織や社会にどう貢献するのかを理解する。目標は具体的かつ達成可能なものとし、定期的なフィードバックなどのサポート体制を整える |
| 報酬と評価制度の見直し | 現状の制度が適切な報酬と公正な評価制度になっているかを見直すことで、貢献度や成果を適切に評価し、それに見合った報酬を提供する。評価制度はプロセスも評価対象に含め、丁寧にフィードバックを行う |
| 社員の自主性を尊重 | 社員の意見やアイデアを積極的に取り入れ、挑戦の機会を与える。必要に応じてサポートできる体制を整え、業務の具体的な進め方を社員に任せる。自らの判断で行動できる環境構築により、社員の自律的な行動や成長を促す |
| 社内コミュニケーションの活性化 | 円滑なコミュニケーションを促す職場環境を整え、社員のモチベーションやパフォーマンスの向上を図る。必要なときにすぐ相談を受けられるようにするほか、テレワークでも交流可能なツールも活用する |
| 個別のニーズに応じた支援 | 個人面談やアンケートなどで社員の声を収集し、個々のニーズを把握する。在宅勤務や時短勤務など柔軟な働き方や、スキルアップのための研修制度を導入するなど、社員のワークスタイルやキャリアプランに合わせた支援を行う |
( 4 ) 社員のモチベーション向上に成功した事例3選
社員のモチベーション向上に成功した3つの企業の取り組みを紹介します。
〈CASE 01〉仕事と育児を両立できる制度を導入
大手化粧品メーカーでは、子育て中の美容部員が早めに退店できる制度を導入しました。夕方から閉店までの業務は、アルバイトスタッフに接客や美容の知識などの事前研修を実施して対応しています。アルバイトスタッフの確保や教育にコストがかかるものの、販売力の高い人材の流出を防ぐことで、結果的にコストの抑制が期待されています。
〈CASE 02〉スタッフ同士が感謝を伝え合う取り組み
外資系ホテルチェーンでは、スタッフ同士が感謝の気持ちをカードで伝え合う制度を導入しています。カードには具体的なエピソードを記入し、そのコピーを人事部に提出する仕組みで、人事評価に反映されます。信頼関係の構築やモチベーション向上に役立つほか、社員食堂にも提示され、スタッフへの刺激や顧客対応の参考にもなっています。
〈CASE 03〉独自の教育システムでスキルアップを支援
大手飲料メーカーでは、社員の自己啓発を支援する場として企業内大学を開設しています。営業、財務、マーケティングなど多様なカリキュラムがあり、社員は自身のキャリアプランに合わせて学びたい分野を選択し、課題やグループ討議に取り組みます。より実践的な経営感覚を養うための大学院も設置し、社員の主体的な学習を促進しています。
( 5 ) まとめ
ここまで、社員のモチベーションが低下する理由や、モチベーションを高めるための方法、成功事例などを紹介してきました。社員が意欲的に業務に取り組める環境を整えることは、企業にとって非常に重要であることがおわかりいただけたのではないでしょうか。
SAXA-DX Naviでは、企業におけるコミュニケーションの失敗例や解決策についてまとめた資料や、部下の成長を促すミーティングで効果を上げるためのチェックシートなど、さまざまなお役立ち資料をご提供しています。ぜひ、ご活用ください。
課題解決に役立つ資料はこちら!
経営課題におけるトレンド情報や課題解決にお役立ていただける資料をまとめております。
ぜひ一度お読みください。