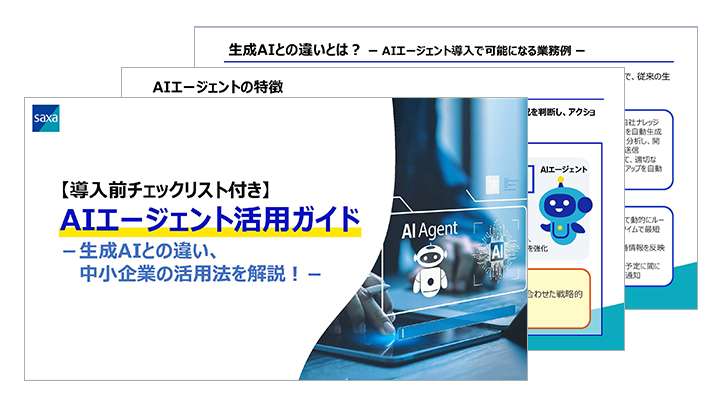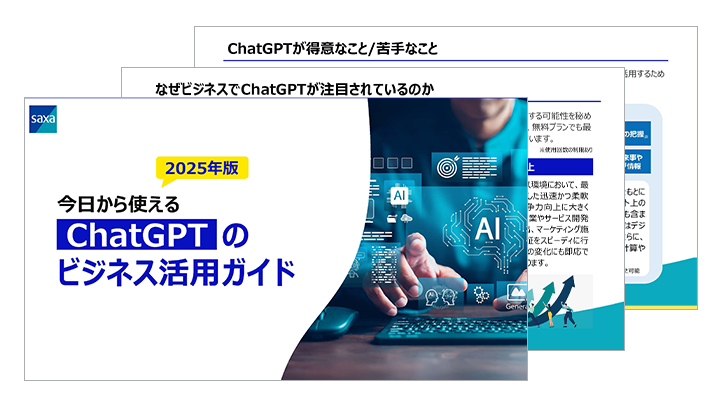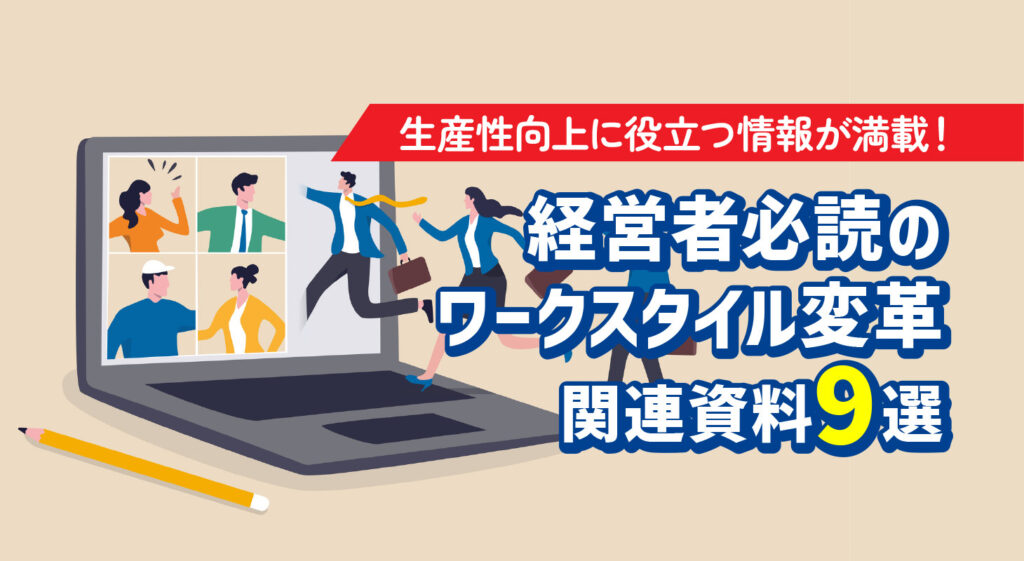▼課題解決に役立つ資料ダウンロードはこちら▼
→ 【導入前チェックリスト付き】AIエージェント活用ガイド → 2025年版今日から使えるChatGPTのビジネス活用ガイド → 中小企業のIT担当向け今日から始めるランサムウェア対策実践ガイド最近よく聞くようになった、モラハラ。「パワハラとは何が違うの?」と思っている方もいるでしょう。今回は、職場におけるモラハラについて、特徴や対策などを詳しく解説します。快適な職場づくりのためにお役立てください。

今回のお悩み
職場のモラハラとは何かを知りたい。モラハラの加害者や被害者の特徴、モラハラを放置した場合のリスク、企業や組織としての適切な対策や対処法などについても理解を深めたい。

私が解説します!
さまざまなハラスメントが問題となっている昨今、今回は「モラハラ」について、どのようなものがモラハラにあたるのか、特徴や具体例などを紹介します。モラハラについて知ることで、防止策や起きたときの対処法がわかります。
目次
( 1 ) 職場におけるモラハラとは?
モラハラとは「モラルハラスメント」の略で、モラル(倫理・道徳)に反するハラスメント(嫌がらせ)のことを言います。
厚生労働省の「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
こころの耳」では、職場におけるモラハラを以下のように定義しています。
言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせること
参照:厚生労働省_働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト:こころの耳
パワハラとの違い
パワハラとモラハラには重なる部分もありますが、大きな違いとしてはパワハラには必ず上下関係のような力関係が存在しており、モラハラはその限りではないという点です。例えば対等の立場であったとしても、モラハラは起こり得ます。それだけに被害が見えにくく、知らないうちにストレスを抱え込んでしまうケースも少なくありません。
( 2 ) 職場でモラハラする人、受けやすい人の特徴
一般的にモラハラを行う人(加害者)には、以下のような特徴が見られます。
- 自信過剰(または自信がない)
- 自分に甘い
- 失敗を認めない
- 承認欲求が強い
- 自己愛が強い
そのうえで人を操ろうとする傾向があり、精神的に支配しやすい人をターゲットにして優位に立とうとします。
逆に被害者になりやすい人には、人の言うことを鵜呑みにしやすい、人への依存度が高い、といった傾向が見られます。
( 3 ) 職場でモラハラにあたる具体例
職場でのモラハラにはいくつかのパターンがあります。どのようなものが該当するのかを解説します。
●人格否定
相手に精神的ダメージを与える典型的なモラハラです。「だからダメなんだよ」などという言葉の暴力、あるいはわざとらしいため息や舌打ちも該当します。
●人間関係からの切り離し
あいさつやメールを無視する、ランチや飲み会に誘わないなどを繰り返し、職場の人間関係から切り離すような行為もモラハラにあたります。
●過度なプライベートへの介入
相手への尊重もないまま、「なんで結婚しないの?」「子どもはまだ?」など、プライベートな事柄に踏み込むのも要注意です。
●仕事の押し付け
自分の仕事や私的な用事を押し付けて帰ってしまうような、その人の業務に支障が出る妨害行為もモラハラとみなされます。
( 4 ) 職場でのモラハラを放置するリスク
モラハラが企業にもたらす影響は少なくありません。モラハラを放置することで起こるリスクは、おもに以下の3点が挙げられます。

●生産性の低下
モラハラは被害者だけでなく、社内の雰囲気を悪くするなど周りにも悪影響を与えます。社内全体のモチベーションが下がり、生産性の低下を招きます。
●健康被害
被害を受けた人はメンタルヘルス(※1)の不調など健康被害をきたし、休職や退職に至るケースもあります。抜本的な解決がなければ別の被害者が生まれることになります。
●損害賠償問題へ
企業には安全配慮義務(※2)があります。このため会社として対策を怠ると訴訟や損害賠償問題へと発展する恐れがあり、企業イメージも著しく低下します。
※1 メンタルヘルス:心の健康状態を指す。世界保健機関(WHO)では、「自らの可能性を認識し、日常のストレスに対処し、 生産的かつ効果的に働き、コミュニティに貢献できる健全な状態」と定義している。※2 安全配慮義務:企業が従業員の健康と安全に配慮する義務のこと。労働契約法のもとで明文化されている。
( 5 ) 職場でのモラハラを防ぐ対策
職場でのモラハラを防止・抑止するにあたって有効な方法を紹介します。
●就業規則として明文化
就業規則にハラスメントに相当する事項や、加害者に対する処分などを明記します。会社としての断固とした態度を示すことで、抑止力になることが期待されます。
●ハラスメント研修の実施
パワハラやモラハラに関する共通理解を深めるために、ハラスメントに関する研修を実施しましょう。できれば継続的に開催することをおすすめします。
●相談窓口の開設
被害者が一人で抱え込んでしまう状況を防ぐために、ハラスメントに関して気軽に相談できる窓口を開設し、被害者へのフォローやアドバイスを行いましょう。
●社内コミュニケーションの円滑化
防止や抑止だけでなく早期発見のためには社内の円滑なコミュニケーションも欠かせません。風通しの良い職場の人間関係づくりを意識しましょう。
( 6 ) 職場でモラハラが起きたときの対処法
対策していてもモラハラが起きてしまった場合には、以下の対処法を実践してみましょう。
●事実確認
被害者の了承のもと、事実確認を行います。証拠となる画像や音声、メールの有無、第三者による目撃証言、被害者へのヒアリングなど、広範にわたって調べます。
●ルールに則って対処
モラハラの事実が明らかになれば、就業規則に記した内容に従って適切な措置(謝罪、配置転換、減給、出勤停止、懲戒解雇など)をとります。
●再発防止への取り組み
今後こうした事態が起きないよう、すべての従業員に注意喚起し、研修を強化するなど再発防止に向けて取り組みます。必要に応じて被害者へのケアなども行います。
( 7 ) まとめ
ここまで、職場におけるモラハラについて、具体例や対処法などを解説してきました。モラハラによるリスクは従業員個人だけでなく、部署や会社全体に悪影響を及ぼすものであることがおわかりいただけたのではないでしょうか。
モラハラは早期発見に努めることが重要であり、会社としてモラハラを防止する対策が必要です。従業員が安心して働ける職場環境を構築することで、業務効率化や生産性向上も図れます。
また、ご紹介しましたようにモラハラの防止や早期発見のためには社内の円滑なコミュニケーションも欠かせません。社内コミュニケーションと一口に言っても有効なものもあれば、逆効果になってしまうものもあるので注意が必要です。
サクサでは、社内コミュニケーションの失敗例と解決方法についてまとめた資料をはじめ、さまざまなお役立ち資料をご提供しています。ぜひ参考にしてください。
課題解決に役立つ資料はこちら!
経営課題におけるトレンド情報や課題解決にお役立ていただける資料をまとめております。
ぜひ一度お読みください。