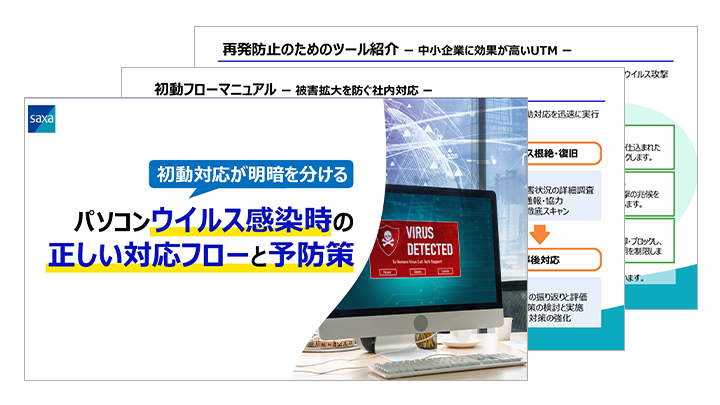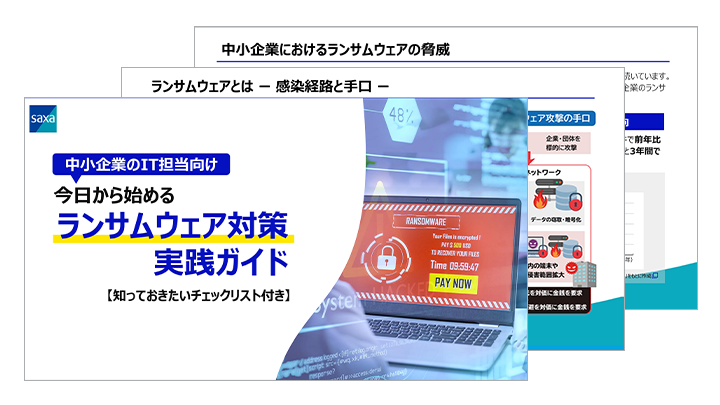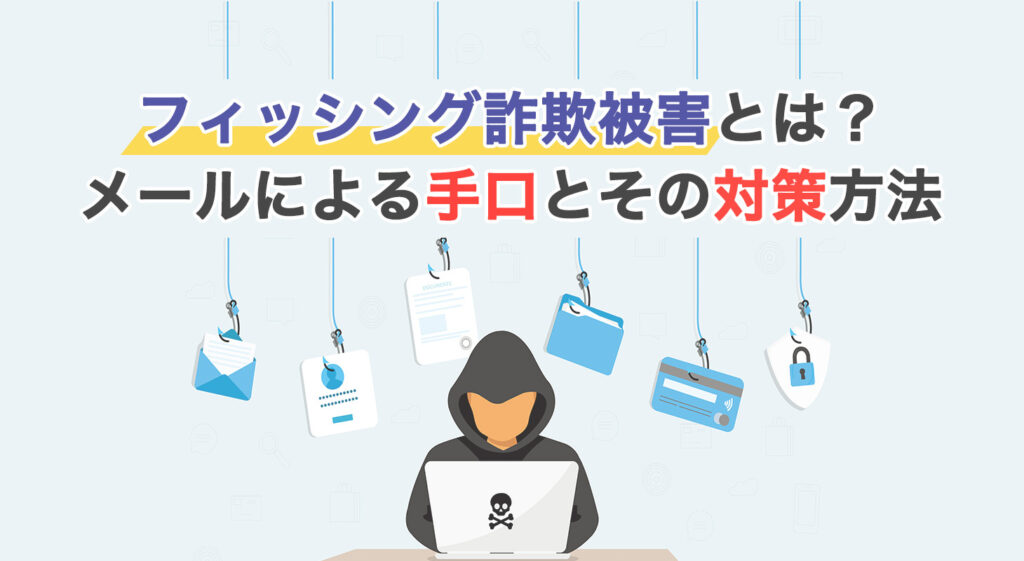ChatGPTという言葉を、ニュースなどでよく聞くようになりました。何となく便利なものらしいということはわかるのですが、「具体的に説明できるのか?」と言われると、多くの方が言葉に詰まってしまうのではないでしょうか。本記事では、ChatGPTの基本から、中小企業での具体的な活用事例、さらにセキュリティ対策まで、2025年6月の最新情報をもとにわかりやすく解説します。業務の効率化や生産性の向上に役立つヒントとして、ぜひご活用ください。
※本記事の内容は、2025年6月現在のものです。

今回のお悩み
最近、連日のようにChatGPTのニュースが流れているけれど、どのようなものかを知りたい。便利だということは何となく理解できるのだが、利用に際してリスクや気をつけるべきことはあるのだろうか?

私が解説します!
最新のテクノロジーを賢く活用するためには、まずはどのようなものなのか、そのメリットや留意点などをしっかり理解しておくことが大切です。従業員のITリテラシー向上を図るためにも、ChatGPTについて知識を深めましょう。
目次
( 1 ) ChatGPTとは?
AI環境が劇的に変化!?
ChatGPT(チャット・ジーピーティー)とは、テキストベースでユーザーが入力した質問に対して、高度な言語処理により、人間と変わらないような自然な回答をAI(人工知能)が行うというチャットサービスです。GPTは「Generative
Pre-trained
Transformer」の略で、「生成可能な事前学習済み変換器」という意味です。
このサービスを提供しているのは、アメリカで2015年に設立されたOpenAI(オープン・エーアイ)という企業です。OpenAIはAI分野の開発によって、世界のすべての人たちに有益なAGI(汎用人工知能)の普及・発展を目標としています。
2022年11月にChatGPTが一般公開されて以降、2023年の「GPT-4」、2024年の「GPT-4o」と急速に進化を遂げ、2025年6月現在では、画像生成から音声対話まで多彩な機能を備えた統合型AIプラットフォームへと発展しています。
突出した精度のチャットボット
対話型のAIは、これまでにもさまざまなところで活用されてきました。企業において顧客からの問い合わせに対応するチャットボットなどを思い浮かべる方も多いでしょう。
しかし、ChatGPTの精度と柔軟性は、従来のチャットボットとはまったく次元が異なります。特に「GPT-4o」では、人間に近い言語理解能力を備え、より自然な対話体験を実現しています。一度に理解できる文字数(コンテキスト長)も最大128,000トークン(日本語で約10万語相当)まで拡張され、長文の分析や複雑なタスク処理精度が飛躍的に向上しています。
( 2 ) ChatGPTの特徴
インターネット上のあらゆる情報を駆使

ChatGPTは膨大なデータから学習することが特徴の一つとして挙げられます。インターネット上のあらゆる情報、例えばウェブサイト、ニュース記事、書籍、論文など、多岐にわたるテキストデータから学習し、多様なユーザーの質問やタスクに対応します。
その実力を示す一例として、ペンシルベニア大学ウォートン校の調査では、ChatGPTがMBA(※2)の最終試験に挑戦し、B評価の合格点に達したと報告されています。さらに2025年には、医師国家試験の模擬テストで人間の医師を上回る成績を収めるなど、専門分野でも高い能力を発揮しています。ChatGPTの大きなポテンシャルを知らしめたエピソードの一つと言えるでしょう。
自然な回答が可能
通常のチャットボットは、設定されたプログラムの範囲内でしかユーザーに返答できません。ChatGPTは、膨大なデータから学習するとともに、多くのユーザーと対話を続けることで賢くなっていきます。例え曖昧な質問であっても、ユーザーの意図を読み取り、文脈を理解しながら自然な会話を継続できる点が、ChatGPTの大きな特徴です。なかでもGPT-4oでは日本語処理能力が飛躍的に向上し、日本語特有のニュアンスや文化的背景も考慮した高品質な応答が可能になっています。
そのため小説や詩、メールマガジン、文章の要約・添削・校正、翻訳、プログラミングなどのテキストを高い精度で生成することもできる柔軟性を持ち、企業のさまざまな文書作成業務を効率化しています。
誰でも利用できる
ChatGPTは企業や個人を問わず誰でも利用できる「開かれた技術」として、オープンソースの形で提供されています。
使い方もシンプルで、公式サイトからログインするだけで利用を開始できます。現時点では英語版のサイトのみですが、日本語で入力すれば、日本語の回答が自動的に返ってきます。このような革新的サービスでありながら、基本的には無料で利用できます。リリースからわずか2カ月で、ユーザー数は1億人を突破しました。さらに2023年3月には、精度が向上した「GPT-4」がリリースされ、有料プランも登場。これにより、多くの企業や個人がChatGPTを活用し、サービス開発やビジネスチャンスの創出を試みるなど、大きな盛り上がりを見せています。
( 3 ) ChatGPTの業務効率化に役立つ活用アイデア10選
中小企業が持続的に成長していくためには、業務効率化は欠かせない課題のひとつです。ここでは、ChatGPTを活用して業務の効率化に役立つ10のアイデアをご紹介します。2025年6月現在の最新機能も踏まえた内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。
1.営業資料・提案書の作成支援
ChatGPTは、単なる生成ツールにとどまらず、顧客の業界や企業規模、過去の取引履歴、競合他社の動向などの情報をもとに、パーソナライズされた営業資料や提案書を効率よく作成できます。GPT-4oでは、非構造化データ(例:顧客からのフィードバック、業界レポート、商談議事録など)も解析でき、「競合他社との差別化を強調した提案書」など、戦略的なニーズにも柔軟に対応可能です。
2.社内マニュアル・FAQ作成の自動化
業務マニュアルやFAQの作成・更新は、企業の知識マネジメントにおいて不可欠ですが、多大な時間とリソースを要します。ChatGPTは、社内文書やチャットログ、メールのやり取りといった暗黙知を収集し、短時間で体系的な形式知に変換するのが得意です。
3.カスタマーサポート効率化
ChatGPTは、顧客からの問い合わせに対して、過去の対応履歴やFAQ、製品情報などをもとに、個別最適化された回答案を迅速に生成できます。2025年のGPT-4oは、企業独自のトーンやマナー、ブランドボイスを学習し、より自然で人間らしい応対を実現。企業の個性を反映したカスタマーサポートを支援します。
4.市場調査・競合分析の効率化
ChatGPTは、Web上の膨大な情報から、市場トレンドや消費者行動、競合他社の戦略などを効率的に収集・整理・分析できます。これにより、企業はSWOT分析やPESTEL分析に必要な材料を素早く把握し、データにもとづいた戦略的な意思決定を進めやすくなります。
5.SNS・ブログコンテンツの作成
中小企業にとって、一貫性のあるデジタルコンテンツの発信は、ブランド認知の向上やリード獲得に欠かせません。ChatGPTは、ターゲット層の特性やプラットフォームのアルゴリズムに配慮しながら、コンテンツのアイデア提案から魅力的なキャッチコピー作成、ブログ記事の下書きまで、コンテンツマーケティング全体を幅広く支援します。
6.契約書・法務文書のレビュー支援
契約書や各種法務文書のレビューは、専門知識と時間を要するため、中小企業にとって大きな負担になりがちです。ChatGPTは、文書内の矛盾点や不利な条項、抜けている重要事項を検出し、リーガルリスクを軽減するための迅速な初期レビューを支援します。
7.データ分析・レポートの作成
2025年6月現在のGPT-4oは、テキスト処理にとどまらず、高度なデータ分析にも対応しています。ExcelやCSVなどの構造化データから、売上・顧客行動・在庫状況などのビジネスインサイトを抽出することができ、複雑な統計処理の実行や、結果を視覚的にわかりやすいレポート形式で出力することも可能です。
8.多言語対応・翻訳業務
グローバル市場への展開を目指す中小企業にとって、多言語対応は避けて通れない課題です。しかし、専門の翻訳サービスはコストが高く、継続的な運用には負担がかかります。ChatGPTは、高精度な機械翻訳を提供し、ビジネス文書やメール、ウェブサイトコンテンツの多言語化を支援します。
9.採用・人事業務の効率化
採用広告の作成や求職者への初期対応、面接質問の準備など、人事業務は定型的でありながら多くの労力を必要とします。ChatGPTは、企業のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)や職務要件にもとづき、魅力的な求人原稿や、候補者の資質を引き出すための面接質問を自動で生成します。2025年のGPT-4oでは、企業文化にマッチした採用戦略の立案にも貢献できます。
10.アイデアの発想・問題解決の支援
新規事業開発や業務改善は、既存の枠にとらわれないイノベーションが求められます。ChatGPTは、豊富な知識とパターン認識能力を活かして、異なる業界の成功事例や、未発見のニッチ市場、潜在的な顧客ニーズを提案。ブレスト(※3)の強力な支援ツールとして、創造的なアイデアの発想や課題解決を支援します。
※3 ブレスト:ブレインストーミング。複数人で自由に議論し、アイデアをどんどん出すことで新しい考え方や解決策を見出す手法。( 4 ) ChatGPTのメリットと留意点
ChatGPTをはじめとする生成AIツールは、その革新性から多くの分野で注目を集めています。一方で、まだ比較的新しい技術であることから、「本当に業務に導入して問題ないのだろうか?」と、不安を感じる担当者も少なくありません。
ここでは、2025年時点の最新情報や動向を踏まえながら、ChatGPTを業務で活用する際のメリットと、注意しておきたいポイントを具体的に解説します。
ChatGPTを利用するメリット
-
業務の効率化と生産性の向上
ChatGPTを使うメリットとして、「調べもの」にかかる時間を短縮することができるなど、会社業務の効率化を挙げることができます。「調べもの」に手間がかかってしまうのは、インターネット上に「知りたい情報」がまとまって存在していないためですが、ChatGPTは、ユーザーの検索意図を的確に読み取り、関連性の高い情報を整理・要約して提示します。そのため、必要な情報に素早くたどり着けることが大きな特長です。この機能により、企画書やレポートの作成、市場調査といった幅広い業務のスピードを大きく向上させることができます。
-
アイデア出しにも有効
働き方改革などのアイデア出しにも、ChatGPTは役立ちます。例えば「経費を削減するためのアイデアを教えて」などと質問すれば、「出張の頻度を減らす」や「紙の使用量の削減」といった具体的なアイデアを膨大なデータの中から提案してくれるのです。
また販売戦略・商品企画などにおいても、多くの人の時間と手間を必要とするブレストに頼ることなく、ChatGPTと対話することでこれまでにない新たなひらめきや解決策が生まれる可能性を秘めています。 -
文章・プログラミング作成もお任せ
ユーザーの質問に応じてさまざまな文章作成が可能なため、ちょっとした文章ならChatGPTに任せてもよいでしょう。例えば社内用のマーケティング資料、メールマガジンやSNSに載せる短文の作成など多様なビジネス文書の作成は、ChatGPTの得意分野です。またプロンプト(※4)から質問することで「Python(パイソン)」、「Java(ジャバ)」などのプログラミング言語によるプログラミングも可能で、開発業務の効率化にも貢献します。
※4 プロンプト:コンピュータへの入力を促す表示。ここではChatGPTに送る文章、命令のこと。
利用時の留意点
-
情報セキュリティとプライバシーの保護
ChatGPTは、インターネット上の膨大な情報を学習して回答を生成しています。そのため、会社の機密情報や個人情報、顧客データなど、秘匿性の高い情報をそのまま入力することは避けるべきです。入力内容が学習データとして利用され、意図せず外部に漏洩するリスクがゼロとは言えないからです。現在では、多くのプロバイダーが「学習への利用をオフにできる設定」や「セキュリティを強化した有料プラン・API」を提供しています。
こうした選択肢を活用することでリスクを軽減できますが、利用規約をよく確認し、自社に合った社内ルールやガイドラインを整備することが重要です。 -
オフィシャルな利用には注意が必要
ChatGPTの回答はあくまでインターネット上の情報がベースであるため、情報の正確性は保証されていません。時に、事実と異なる情報や誤った情報をあたかも真実のようにもっともらしく提示してしまう「ハルシネーション(Hallucination)」と呼ばれる現象が起こることが知られています。
これは、古い情報や誤ったデータをもとに回答を生成してしまうことが原因です。そのため、AIが出力した内容をそのまま鵜呑みにせず、業務での活用にあたっては人間による事実確認が欠かせません。特に、法務・医療などの専門性が高い情報や、企業の意思決定に関わる内容については、必ず専門家の確認を行うようにしましょう。 -
著作権侵害の可能性も
OpenAIの利用規約を日本語で要約すれば、「ユーザーが規約を遵守している限り、OpenAIは出力に対するすべての権利・利益をユーザーに譲渡する」という内容になりますが、注意しなければならないのは、ChatGPTが生成した文章自体に著作権侵害が含まれている場合です。生成された文章が既存の著作物の表現に酷似し、知らないうちに著作権を侵害してしまう可能性もあるため、慎重を期すならChatGPTで作った文章は利益目的での外部公開は避け、私的な利用にとどめるほうが無難です。商用利用を検討する場合は、生成されたコンテンツのオリジナリティを十分に確認し、専門家の意見を求めることも検討すべきです。
参照:「OpenAI_利用規約」 -
なくなる業務も出てくる!?
将来的にChatGPTを顧客の問い合わせ対応などに活用するという流れになれば、コールセンター、カスタマーサポート、データ入力などの業務の在り方が変わると予想されるため、対応が求められる部署も出てくるかもしれません。企業がAIを導入する際には、業務の変化に対応できるよう、従業員に対するリスキリング(再教育)や、新たなスキルセット(例:効果的なプロンプト作成能力)の習得支援が不可欠です。例えば「効果的なプロンプトの作成方法」など、AIを活用するための具体的なスキルが求められます。AIはあくまで業務を支援するツールであり、最終的な判断と責任を持つのは人間です。この前提を組織全体で共有し、AIと協力しながら生産性を高める「協調的な働き方」を構築することが、今後ますます重要になっていきます。
( 5 ) これからのIT業界の動向
加熱するAI開発
ChatGPTのセンセーショナルな登場によって、IT業界ではにわかにAI開発が加速しています。2019年からOpenAIに投資を行ってきたマイクロソフトでは、OpenAIと連携することでさまざまなサービス・製品におけるAIとの融合を摸索しており、2025年6月現在、ChatGPTとの連携を自社製品群で一層強化しています。例えば「Microsoft 365 Copilot」では、Office製品にChatGPTの技術を組み込み、ビジネス文書の作成や会議内容の要約など、日常業務をAIが支援する仕組みが実現されています。また、サーバやネットワークなどの環境をクラウド上で提供する「Microsoft Azure(アジュール)」の導入も進み、中小企業でも高度なAIソリューションを利用できる環境が整いつつあります。2025年4月には、中小企業向けに最適化されたAIソリューションパッケージ「Microsoft AI Enterprise Suite」がリリースされ、大きな注目を集めました。また同社のブラウザ「Microsoft Edge(エッジ)」には、対話型のAI「Bing AI」が組み込まれ、チャットや文章作成が可能になっています。
参照:「Microsoft |AI最新情報」対抗する動きも活発化
一方で、ChatGPTに対抗する勢力も出てきています。
顕著な動きを見せているのはグーグルで、2023年3月21日からアメリカとイギリスで対話型AIサービス「Google
Bard(グーグル・バード)」の提供をスタート。日本国内からも4月18日よりアクセスが解禁されました。2025年6月現在では、画像認識の精度と日本語対応が大きく進化した「Gemini
2.5」が登場し、特に検索エンジンとの連携による情報検索機能では、ChatGPTを上回るという評価もあります。
また国内では、2025年5月にNTTデータと富士通が共同開発した日本語特化型の大規模言語モデル「日本AI」が発表され、日本の商習慣や文化に適した企業向けAIとして導入が広がりつつあります。
警鐘を鳴らす声も
このような加熱するAIの進化に警鐘を鳴らす声も上がっています。OpenAIの共同創設者の一人でもあったイーロン・マスク氏は、AIの専門家たちと共同発表した公開書簡の中で、「行き過ぎたAI開発は危険」と述べています。
さらに、セキュリティリスクの高まりも懸念されています。2025年前半だけでも、ChatGPTを悪用したフィッシング詐欺や偽情報の拡散事例が相次いでおり、なかでも中小企業が注意すべきは「プロンプトインジェクション攻撃」と呼ばれる新たな脅威です。これは、AIに意図的な指示を埋め込むことで予期せぬ動作を引き起こすもので、結果として情報漏洩や不正アクセスに発展するおそれがあります。こうした背景を踏まえ、総務省と経済産業省は2025年3月に企業向けの「生成AI安全利用ガイドライン」を公表し、リスクへの備えを呼びかけています。
生成AIに関するインシデント事例
ここではChatGPTをはじめとする生成AIに関連したセキュリティインシデントをご紹介します。
-
大手電子機器メーカーのChatGPTへの情報流出
社内のエンジニアが、機密情報のソースコードを誤ってChatGPTに入力したことで、情報漏洩リスクが浮き彫りになった事例です。ChatGPTはデフォルトで入力内容を保存し、モデル学習に利用する設定となっているため、機密情報や個人情報はアップロードしないようにしましょう。この件を受けて、大手電子機器メーカーは社内でのChatGPT利用が全面的に禁止されました。
-
生成AIでのマルウェア作成
2024年5月27日対話型生成AIを使ってマルウェアを作成したとして、国内で初の「不正指令電磁的記録作成」容疑による逮捕者が出ました。容疑者は専門的なITスキルを持たず、複数の生成AIを組み合わせて悪意のあるプログラムを作成したとされています。この事件は、生成AIが悪用されるリスクと、誰でもサイバー攻撃ツールを生成できる可能性を社会に強く印象づけました。
参照:IPA情報処理推進機構「テキスト生成AIの導入・運用ガイドライン(PDF)」
( 6 ) 中小企業がとるべき対策
DX(デジタルトランスフォーメーション)に対する投資をしっかりと
ChatGPTを活用することが自社においてどんな意味を持つか、今一度考えてみる必要があるでしょう。最新技術を単に導入するだけでなく、どのように業務に活かすかを見据えた全社的なDX戦略の立案・実行が重要です。単なるツールの導入にとどまらず、業務全体のフローや意思決定のあり方を見直し、デジタル技術と人の力をどう融合させるかという視点が必要です。
また、IT導入補助金やDX推進助成金といった支援制度を活用することで、コストを抑えながら効率的に最新技術を導入できます。
従業員のITリテラシーを高める
ChatGPTがどれだけ賢くても、結局それを使うのは人間です。安易に「便利そうだ」と飛びつくのではなく、従業員のITリテラシー向上も同時に取り組むことが大切です。そのためには定期的な研修なども必要になってきます。
特に重要なのは、「AIに何を任せるべきか」「AIの出力をどう見極め、必要に応じて修正するか」といった判断力です。単なる操作スキルではなく、AIの特性を理解し、人間とAIそれぞれの強みを活かすための視点を持った教育が求められています。
基本的な操作研修に加えて、先進的な活用事例の共有会やスキルアップのための定期セッションなどを実施することで、組織全体のAIリテラシー向上につなげることが成功の鍵となるでしょう。
自社のセキュリティ対策の現状を把握する
技術は日進月歩で進化しています。新たなサービスが生まれ、私たちを取り巻くIT環境の劇的な変化に伴い、企業を狙うサイバー攻撃もどんどん多様化・巧妙化しています。
経営者としては、自社の状況を把握しておくことが重要です。自社のセキュリティ対策の取り組み状況や、今後対策を立てるべき問題点などを把握できるサービスもあります。情報漏洩やデータ消失など、取り返しのつかないセキュリティインシデントを起こさないためにも、まずは自社の現状把握から始めてはいかがでしょうか。社内利用ガイドラインの策定や、アカウント管理の徹底、出力内容の検証体制構築など、できるところから始めていくことが重要です。
( 7 ) まとめ
ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、ビジネス環境は急速に進化しています。特に、限られたリソースで多様な業務をこなす中小企業にとって、ChatGPTは業務効率化や生産性向上を実現する強力なツールとなり得ます。
2025年の「GPT-4o」では、画像生成や音声対話といった機能も加わり、さらに幅広い業務領域での活用が可能になっています。文書作成やデータ分析、顧客対応など、さまざまな業務プロセスを効率化し、中小企業の競争力強化に貢献します。
一方で、情報セキュリティや著作権に関するリスクも無視できません。安全かつ効果的に活用するためには、社内での利用ルールの整備や、従業員への教育が欠かせません。加えて、AIはあくまで「道具」であるという認識も大切です。その真価を引き出すのは、使い手である人間の判断力と創造力です。
中小企業がChatGPTをはじめとするAIの力を最大限に活用するためには、「何ができるか」を知るだけでなく、自社の業務全体を見直し、人とAIが連携できる体制を構築することが重要です。本記事が、皆様のAI活用の一助となれば幸いです。
サクサでは、Web上で手軽にできる「情報セキュリティ現状診断」を提供しています。20の問いに「はい」か「いいえ」で答えるだけで、自社のセキュリティ状況が把握できます。このほかにもさまざまなソリューションを通して、中堅・中小企業の課題解決をサポートさせていただきます。ぜひ気軽にお問い合わせください。
課題解決に役立つ資料はこちら!
経営課題におけるトレンド情報や課題解決にお役立ていただける資料をまとめております。
ぜひ一度お読みください。