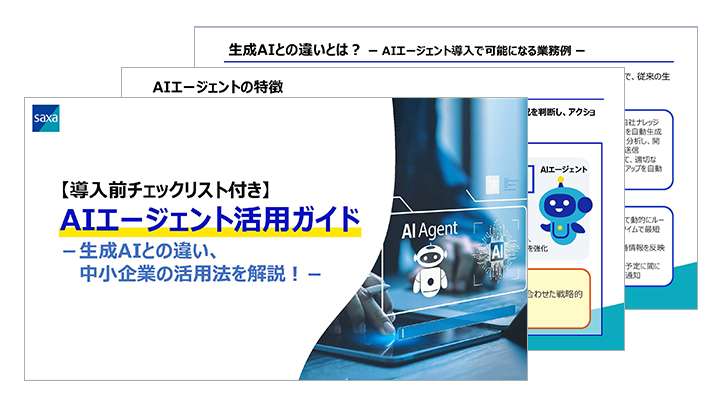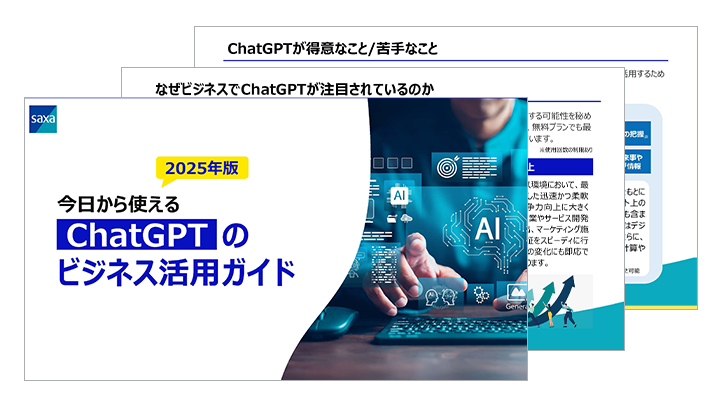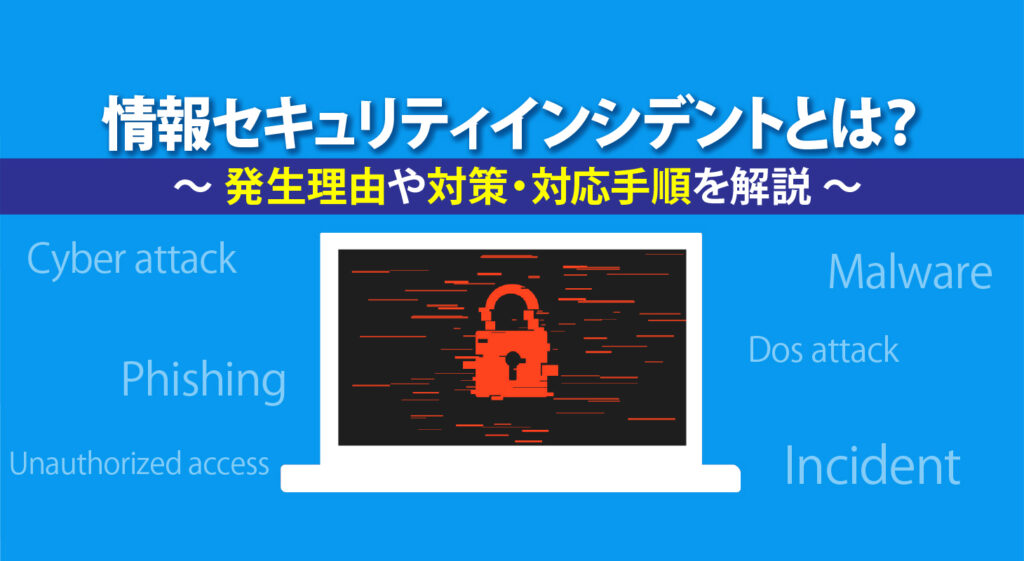▼課題解決に役立つ資料ダウンロードはこちら▼
→ 【導入前チェックリスト付き】AIエージェント活用ガイド → 2025年版今日から使えるChatGPTのビジネス活用ガイド → 中小企業のIT担当向け今日から始めるランサムウェア対策実践ガイド「従業員の意欲が低い」「若い人材が定着しない」など、雇用に関する悩みを抱えている経営者は多いのではないでしょうか。労働人口の減少が社会課題となる中、働きがいのある職場づくりに努め、従業員の意識を高める取り組みが重要になってきます。従業員のモチベーションは、就業環境の良し悪しによって大きく左右します。今回は、働きやすい職場とは何か、それを実現するにはどうすればよいのかを事例とともに解説します。自社の変革に向けて、ぜひ参考にしてください。

今回のお悩み
従業員の確保や定着を図りたいが、どのような会社が「働きやすい職場」と言えるのだろうか。特徴やメリット、事例などを理解したうえで、働きやすい職場づくりに取り組みたい。

私が解説します!
働きやすい職場をつくることは従業員の確保や定着だけでなく、さまざまなメリットがあります。その実現に向けて、取り組みのポイントや企業の取り組み具体例も紹介します。
目次
( 1 ) 働きやすい職場とは?
働きやすい職場とは、「心身ともに健康かつ快適に働ける環境」と「パフォーマンスをしっかり発揮できる環境」を両立させている会社と考えられます。つまり高い生産性を維持しながら生き生きと働ける就業環境が整っているかどうかが重要です。
従業員のやりがいやモチベーションは、その人の内的要因だけでなく、外的要因の影響も大きく受けます。例えば、
- 適正に評価される人事制度があるか
- 個々の事情に合わせて選べる多様な働き方が整っているか
- 福利厚生が充実しているか
といったことが大事な点になってきます。
国も「働きやすい・働きがいのある職場づくり」を推奨
わが国でも、早くから「働きやすい・働きがいのある職場づくり」が推奨されてきました。厚生労働省では、「職場の働きやすさ・働きがいに関するアンケート調査(従業員調査)」(平成25年)を受けて、以下のように述べています。
従業員の『働きがい』や『働きやすさ』の意識を高めると、働く意欲が向上し、職場での定着率が上がり、さらには会社の業績向上に効果があることが調査で明らかになっています。
(中略)
従業員の『働きがい』や『働きやすさ』意識を高めるには、評価や処遇、人材の育成、人間関係についての管理など、適正な雇用管理の実施が効果的です。
そのうえで「働きやすい・働きがいのある職場づくり」のポイントとして以下のような例が挙げられています。
効果のある雇用管理の例
| 「働きがい」意識を高める | 「働きやすさ」意識を高める | |
|---|---|---|
| ① | 仕事の意義や重要性を説明する | 希望に応じてスキルや知識が身に付く研修を実施する |
| ② | 従業員の意見を経営計画に反映する | 本人の希望をできるだけ尊重して配置する |
| ③ | 本人の希望をできるだけ尊重して配置する | 提案制度などで従業員の意見を聞く |
| ④ | 希望に応じてスキルや知識が身に付く研修を実施する | 従業員の意見を経営計画に反映する |
| ⑤ | 提案制度などで従業員の意見を聞く | 経営情報を従業員に開示する |
( 2 ) 働きやすい職場の特徴
自身が勤務する会社は働きやすいと従業員が感じる職場環境には、いくつかの特徴(傾向)があります。制度的なものから社風に関するものまで内容はさまざまです。自社の状況と照らし合わせてチェックしてみてください。
●コミュニケーションが円滑
人間関係のよい職場には、自然と働きやすさが生まれます。上下関係を含めた従業員同士のつながりや、部署の垣根を越えたコミュニケーションも重要です。それがチームとしての力を高め、ひいては組織としての強みになっていきます。
●意見が通りやすい
円滑なコミュニケーションと同様に重要なポイントです。人は、言われたことをこなすだけでは仕事にやりがいや達成感を得ることはできません。従業員が意見しやすく、業務などにも反映してもらえる風通しのよい職場は、意欲の向上にも効果的です。
●ワークライフバランスへの配慮がある
時代や社会の変化に合わせて、働き方の選択肢が増えています。フレックスタイム制、テレワーク、ハイブリッドワーク(※1)など、多様な働き方ができる職場は、従業員の生活状況に合わせた働きやすさや、ワークライフバランス(※2)への配慮が行き届いていると言えるでしょう。
●教育・研修体制が充実
新人研修はもちろん、階層別に個々のスキルアップを図る教育・研修制度が充実した会社は、定着率が高い傾向にあります。人材は企業にとって大切な財産です。多くの成長機会を提供することで優秀な人材が育ちます。
●適正な人事評価制度
会社が自分のことを正しく評価してくれるという安心感を従業員に与えることは大事です。業務内容を正当に評価して、給与、賞与、待遇などに反映する人事評価制度を整えておかなければなりません。
●福利厚生・休暇制度の充実
福利厚生や休暇制度が充実していることも、働きやすさの実現につながります。労災などの各種保険はもちろん、住宅手当などの各種手当、有給休暇や長期休暇の取得しやすさ、従業員が利用できる託児施設の設置、娯楽施設やスポーツ施設の割引利用など、その範囲は多岐にわたります。
●残業が少ない
長時間労働が慢性化して疲労が蓄積すると、社内の雰囲気が悪くなるだけでなく、健康被害や休職・退職という深刻な事態に発展しかねません。精神的な余裕を持って働いてこそ人間関係も良好になり、業務効率や生産性の向上にもつながります。
※1 ハイブリッドワーク:オフィスワークとテレワークを組み合わせるなど、状況に応じて働き方を選べるワークスタイル。※2 ワークライフバランス:仕事と生活の調和。やりがいを感じながら働き、家庭や地域生活でも充実感を得られる状態。
( 3 ) 働きやすい職場をつくるメリット
働きやすい職場環境の実現は、従業員の満足度が向上するだけでなく、会社にとっても多くのメリットがあります。ここでは働きやすい職場をつくることで得られるメリットとして、会社に発展をもたらす4つの「向上」について解説します。
① 従業員エンゲージメントの向上
働きやすい職場では、社員のモチベーションが高く、それだけ会社や仕事に愛着を持っているとも言えます。以前は「愛社精神」などと言われていましたが、近年では「従業員エンゲージメント」と呼ばれます。従業員が自発的に会社に貢献したいと考える意欲のことで、従業員と会社がウィン・ウィンの関係になることで、意欲の向上につながる傾向にあります。
② 生産性の向上
個々のパフォーマンスが最大化されると、チームとしても大きな力を発揮でき、会社全体として仕事の生産性が向上します。こうして「やりがいがある」→「利益が上がる」という好循環が生まれます。また集中力を高く保って働くことは業務の効率化につながり、残業の削減も期待できます。
③ 企業イメージの向上
従業員が生き生きと働き、利益を上げている会社には、自然と世間の注目が集まります。「働きやすい会社」というイメージは、企業の好感度やブランド力を向上させます。ブランドイメージが向上することで、従業員はより一層仕事や会社に誇りを持つようになり、さらに質の高いサービスの提供や新たな価値創造につながっていきます。
④ 定着率の向上
安心して働ける環境では、従業員のストレスが軽減され、メンタルヘルス(※3)も安定します。これにより、離職率は低くなり、長く活躍することで従業員エンゲージメントはさらに確かなものとなっていきます。こうした会社には優秀な人材が集まり、組織力がさらに強化されます。
※3 メンタルヘルス:心の健康状態を指す。世界保健機関(WHO)では、「自らの可能性を認識し、日常のストレスに対処し、 生産的かつ効果的に働き、コミュニティに貢献できる健全な状態」と定義している。( 4 ) 働きやすい職場を実現するために必要な取り組み
働きやすい職場を実現するには、どのようなことに取り組めばよいのでしょうか。ここでは、働きやすい職場の実現に向けた取り組みとして、5つの「変革」を紹介します。すべてを達成するのは難しいかもしれませんが、取り組みやすいものから始めてみましょう。
① オフィス環境と制度の変革
会社のハード面とソフト面の整備が必要です。まずはオフィス環境の変革として、レイアウト変更やリラックスルームの設置、フリーアドレス(※4)の導入などが考えられます。集中しやすい場所やリフレッシュする空間などを設けることで業務の効率化が図れます。
次に制度の変革として、時短勤務など働き方の選択肢を増やすこと、育休後の復職の仕組みづくりなどが大切です。近年、女性従業員がさらに活躍できる環境整備や、ワークライフバランスの充実は、企業にとって重要なテーマになっています。
② 人事評価・人材育成の変革
従業員を正当に評価するためには、評価項目を明確にしておく必要があります。人事担当者だけでなく、全従業員にわかりやすく示すことが、納得感を与えるポイントです。人材育成や研修についても、定期的な見直しが必要です。新人研修としてOJTを取り入れている会社は多いと思いますが、学習機会の創出や資格取得支援、メンター制度(※5)などのサポートも不可欠です。こうしたきめ細かい取り組みが、若手従業員の早期離職を防ぐことにつながります。
③ 福利厚生・休暇・健康管理の変革
福利厚生の充実は、安心して働くために必要な取り組みと言えます。心身のリフレッシュやストレス解消をするため、宿泊施設やフィットネスクラブがお得に利用できるようにするのもおすすめです。
また長期休暇を取る際には周りに気兼ねしなくてもいいよう、普段から仕事が属人化(※6)しない工夫が必要です。さらに健康管理については定期健診だけでなく、ストレスチェックや産業医との面談も積極的に活用しましょう。
④ 業務の変革
近年、企業には主にDXによって業務効率化を図ることが求められています。テレワークの導入やハイブリッドワークの推進もここに含まれるでしょう。
またデジタル化や業務管理ツールなどを導入し、業務効率化や生産性をアップすることで、長時間労働が解消・是正されることも期待されています。
⑤ コミュニケーションの変革
従業員同士が気軽にコミュニケーションがとれるツールを導入することもおすすめです。チャットツールを活用することで活発なコミュニケーションが促されるだけでなく、お互いの業務内容を把握することにもつながります。また、バーベキューやパーティーのような社内イベントの開催も、コミュニケーションの促進には有効です。
※4 フリーアドレス:固定の席を持たず、好きな席で働くワークスタイル。※5 メンター制度:上司ではない先輩従業員が、後輩従業員の相談に乗る制度。メンタル面も含めてサポートする。
※6 属人化:業務の内容や進め方が当人以外わからない状態。
( 5 ) 働きやすい職場の事例
最後に、中小企業の事例から働きやすい職場づくりのための施策を3つ紹介します。
【取り組み事例①】技能レベルに基づいて処遇
特殊な木材を加工する会社では、従業員の多能工化(※7)を目指してスキルマップによる技能レベルチェックおよび配置転換を実施。処遇はその技能レベルに基づいて行っており、技能習得に対するモチベーションの向上を図っています。
また現場での技能習得とは別に階層別の研修も行っており、一部では社外講習を活用。問題発見能力やリーダーシップ能力、業務改善能力の向上を目指しています。
さらに新入社員を対象として「新入社員フォローアップ懇談会」を実施し、定着率の向上を図っています。

【取り組み事例②】若手の育成、女性の活用に積極的
ある機械メーカーでは、中途採用中心だった雇用を新卒採用・内部育成型に変えてから定着率が向上しました。ミスマッチを防ぐため、技術職希望の学生には組立作業の手伝いをしてもらう「一日職場体験」を実施しています。
また、若手の育成を目的として、早期の権限委譲を行うほか、月間MVP・年間MVPなど、さまざまな表彰制度でモチベーションの向上に努めています。女性の積極活用にも力を入れ、継続雇用のための勤務制度に柔軟に対応。子育て中の従業員にも働きやすい環境を整えています。
【取り組み事例③】仕事の情報を全従業員間で共有
「オープンな会社」をモットーにするIT企業では、従業員への情報開示や従業員の意見をPDCAサイクルに反映する取り組みを通じて、目的の明確化ややりがいの向上を図っています。IT企業である強みを活かして情報共有システムを構築、各職場における仕事内容や状況について全従業員間で共有し、問題への対応に活用しています。
また、SE職はメンタルヘルス問題を抱えやすいと言われているため、リーダー研修の内容にメンタルヘルスを取り入れ、注意喚起を行っています。
( 6 ) まとめ
今回は、働きやすい職場の特徴や働きやすい職場がもたらすメリットについて、さらに働きやすい職場の実現のために必要な取り組み、具体的な事例について紹介してきました。働きやすい職場をつくることによって人材が定着し、従業員のモチベーション向上や会社全体の業績アップにつながるなど、多くのメリットがあることをご理解いただけたのではないでしょうか。今回紹介しましたように、働きやすい職場づくりには、環境整備や制度改革に加えて、ワークライフバランスの実現も重要となります。働きやすい職場によって仕事面が充実すれば、生活面にもよい影響を与えることができるでしょう。
サクサでは、従業員のワークライフバランスを実現するポイントをまとめた資料をはじめ、さまざまなお役立ち資料をご提供しています。ぜひご活用ください。
課題解決に役立つ資料はこちら!
経営課題におけるトレンド情報や課題解決にお役立ていただける資料をまとめております。
ぜひ一度お読みください。