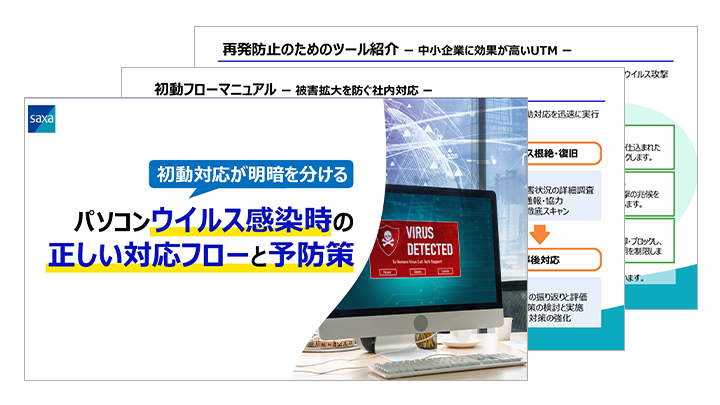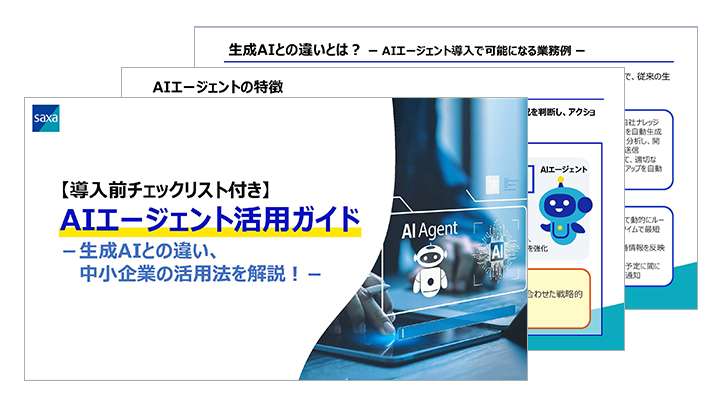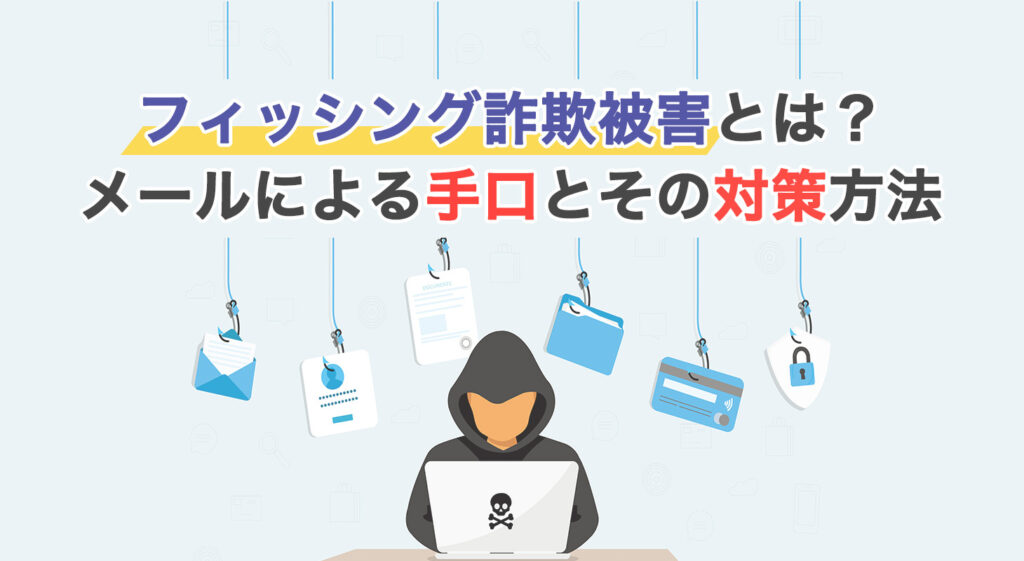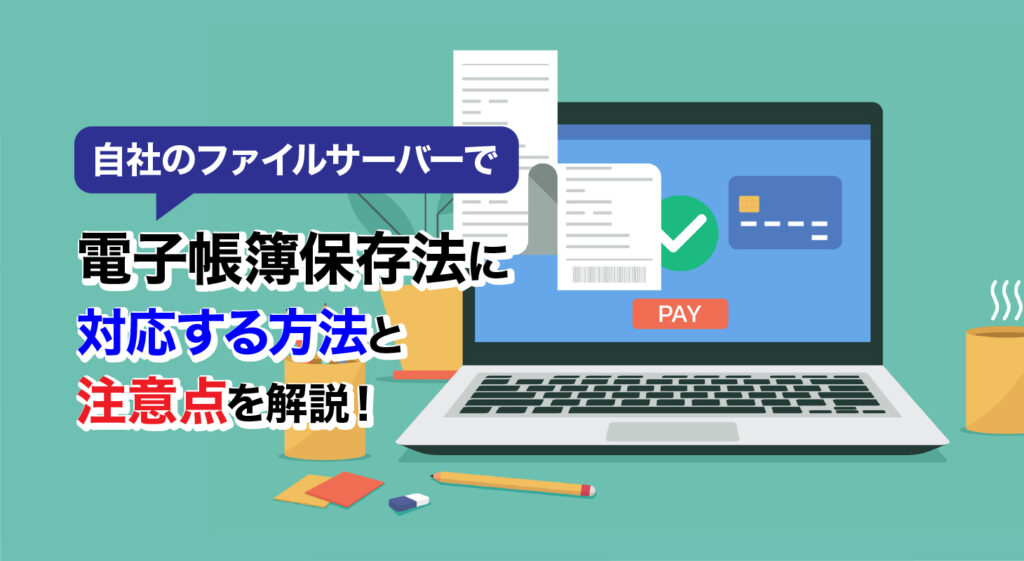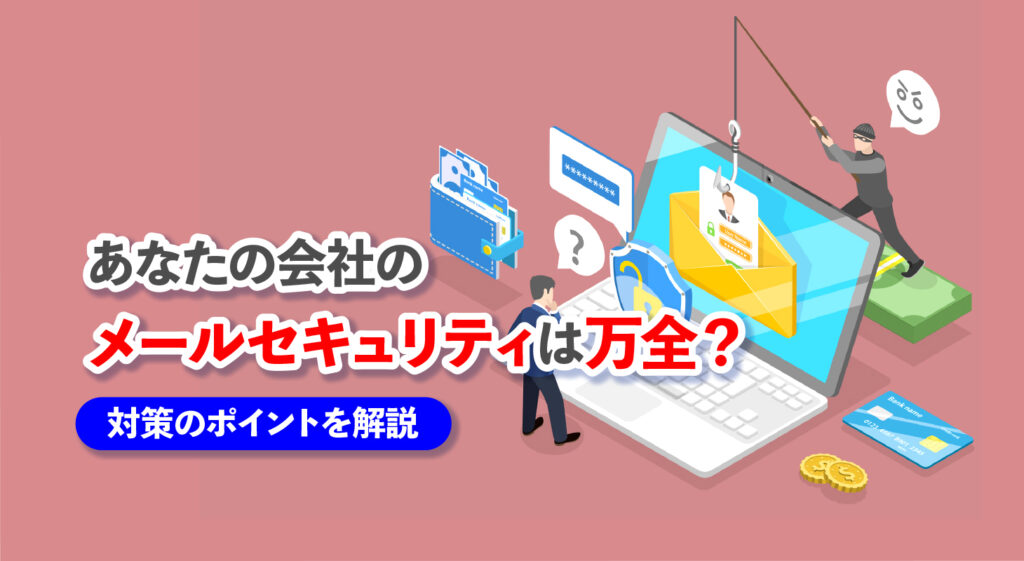みなさんは「ペネトレーションテスト(penetration
test)」をご存じでしょうか?
システムの脆弱性を検証するために実施されるセキュリティテストとして注目されている手法です。一方で、「脆弱性診断」とは具体的にどのように違うのかご存知でしょうか?また、ペネトレーションテストにはどのような種類や手法があり、その実施によってどのようなメリットが得られるのか、疑問に思う方も少なくないようです。
この記事では、「ペネトレーションテストとは?」という基本的な疑問にお答えするとともに、ペネトレーションテストと脆弱性診断の違いを解説します。さらに、テストの種類や手法、実施のメリット・注意点についても詳しく説明し、中小企業が取り入れるべき効果的なセキュリティ対策についても解説します。

今回のお悩み
「ペネトレーションテスト」という言葉は知っているけれど、その概要や有効性についてはよくわからない。自社に必要なセキュリティ対策を知りたい。

私が解説します!
ペネトレーションテストにはさまざまな種類があり、その具体的な手法や脆弱性診断との違いを理解することが重要です。また、実施にあたって得られるメリットや注意点を押さえることで、より効果的なセキュリティ対策を講じることができます。
今回は、ペネトレーションテストを中心に、セキュリティ対策の基本から実践的な取り組み方までを分かりやすく解説します。
目次
( 1 ) ペネトレーションテストとは?
ペネトレーションテストとは、ネットワークに接続されたパソコンやサーバなどの情報システムに対して、悪意のある攻撃者の視点から実際に侵入を試み、セキュリティ上の脆弱性が存在するかどうかを検証するテストのことです。日本語では「侵入テスト」や「侵入実験」とも呼ばれます。ペネトレーションテストを行うための無料ツールも存在しますが、一般的には専門的な知識を持つ第三者に依頼してテストを行います。
専門の技術者に依頼することで、多様な攻撃手法を駆使してシステムの防御力を検証できるため、どこに弱点があるのかを具体的に把握できます。これにより、セキュリティホール(※1)や不正アクセスのリスクを早期に洗い出し、効果的な防御策を講じることが可能です。
ペネトレーションテストの種類・手法
ペネトレーションテストは、その目的や対象範囲、テスト実施者が事前に保有する情報量によって、さまざまな種類や手法に分類されます。これらを適切に理解することは、効果的なテスト計画を策定するために欠かせません。
ペネトレーションテストを実施する際には、攻撃者の視点に立ち、システムへの侵入や脆弱性の発見を試みる手法が中心となります。以下では、代表的な種類と具体的な手法について詳しく解説します。
1.アプローチによる分類
- 外部ペネトレーションテスト
- 内部ペネトレーションテスト
2.事前情報のレベルによる分類
- ブラックボックステスト
- ホワイトボックステスト
-
グレーボックステスト
ブラックボックスとホワイトボックスの中間的なアプローチです。テスト実施者には、限定的な内部情報(例: 一般ユーザーアカウント、API仕様書の一部、大まかなネットワーク構成など)が提供されます。ユーザー権限を持つ攻撃者や、ある程度の内部知識を得た攻撃者による脅威シナリオを評価するのに適しています。
3.対象領域による分類
- ネットワークペネトレーションテスト
- Webアプリケーションペネトレーションテスト
- ワイヤレスネットワークペネトレーションテスト
- ソーシャルエンジニアリングテスト
-
物理ペネトレーションテスト
データセンターやオフィスなど、物理的な施設を対象としたテストです。施設への不正侵入や機密情報の物理的な窃取、不正なデバイス接続を試み、物理的セキュリティ対策の有効性を検証します。
具体的には、施設への侵入手口を模擬し、防犯カメラの死角や施錠不備を狙った侵入リスクを評価することで、物理的セキュリティの弱点を洗い出します。
4.標準的なフレームワーク
-
PTES(Penetration Testing Execution Standard)
ペネトレーションテスト全体のプロセスを定義した技術的ガイドラインです。事前準備、情報収集、脅威モデリング、脆弱性分析、攻撃、後処理、報告という一連のプロセスを体系的に整理し、テストの計画から結果報告までを網羅します。
このフレームワークを活用することで、標準化された手法でのテストが可能となり、テスト品質のばらつきを防ぐ効果があります。 -
OSSTMM(Open Source Security Testing Methodology Manual)
セキュリティテストに関する包括的な方法論を提供するフレームワークであり、ネットワーク、物理的セキュリティ、人的要素など、広範囲にわたる領域をカバーしています。特に、プロバイダーが機密データや認証に関する問題を洗い出し、脆弱性を解決することを目的としており、標準化された評価プロセスを提供します。OSSTMMに従うことで、テスト範囲や評価基準が明確になり、包括的なセキュリティテストが実現できます。
-
NIST SP 800-115
米国国立標準技術研究所(NIST)が提供する情報セキュリティテストと評価に関する技術ガイドラインです。特に、連邦政府や外部の組織が情報セキュリティ対策として従うべき指針を示しており、情報システムの評価プロセスを標準化する目的で活用されています。
このガイドラインは、情報セキュリティに関するベストプラクティスを具体的に示しているため、セキュリティ評価の信頼性を高める際に有効です。 -
OWASP(Open Web Application Security Project)
Webアプリケーションセキュリティに特化したフレームワークであり、テスト手法やチェック項目を網羅的に提供しています。特に、OWASP Top10に代表される脆弱性リストをもとに、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング(XSS)など、Web特有の脅威を評価するための具体的な手順を示しています。
Webアプリケーションのセキュリティ強化を目的とし、開発者やセキュリティ担当者にとって実践的なガイドラインとして広く利用されています。
脆弱性診断との違い
ペネトレーションテストと脆弱性診断はどちらもセキュリティに関する診断手法ですが、その目的や手法には大きな違いがあります。主な違いは以下の通りです。
|
ペネトレーションテスト |
脆弱性診断 |
|
| 目的 | サイバー攻撃への耐性がどの程度あるかを評価する |
システムの欠陥や脆弱性を網羅的に洗い出す |
| 手法 |
想定されるサイバー攻撃のシナリオを作成し、目的とする攻撃が達成できるかを診断 |
ガイドラインによる定型的な手法や、ツールなどを使用して網羅的に診断 |
| 報告内容 |
攻撃シナリオおよび検証結果(攻撃達成が可能な侵入経路など) |
診断で判明した脆弱性の一覧(すべてのリスク) |
脆弱性診断は、システムに存在する「既知の弱点」を網羅的にリストアップする予防的アプローチです。具体的には、セキュリティホールや設定ミス、不適切なアクセス制御などを洗い出し、潜在リスクを明確にします。一方、ペネトレーションテストは、攻撃者の視点で実際にシステムを攻撃し、「特定の攻撃シナリオに対する防御力」を評価する実践的なアプローチです。例えば、サイバー攻撃者が侵入可能な経路を模擬し、どこまで侵害が可能かを検証することで、現実的な防御策を見極めます。このように、脆弱性診断が「リスクの網羅」に重きを置くのに対し、ペネトレーションテストは「攻撃耐性の評価」に特化している点が特徴です。
( 2 ) ペネトレーションテストが有効な企業
ペネトレーションテストは、特に以下のような課題や目的を持つ企業にとって有効なセキュリティ対策です。

-
自社のシステム環境に対する客観的なセキュリティ評価を得たい企業
現在のセキュリティ対策がどの程度効果的か、攻撃者の視点から評価したいと考えている企業に適しています。
-
現状のセキュリティ対策で十分なのか不安があり、今後強化すべき点を把握したい企業
セキュリティインシデント(※4)のリスクを最小化するために、現在の防御力を検証し、改善ポイントを明確にしたいケースで有効です。
-
インシデントリスク(情報漏洩や不正アクセスなど)を具体的に示し、社内のセキュリティ意識を高めたい企業
実際に攻撃シナリオを試行することで、セキュリティホールや内部不正のリスクを可視化し、従業員の意識向上を図れます。
近年、サイバー攻撃はますます高度化・巧妙化しており、攻撃者は新たな手法を次々と取り入れています。攻撃者の視点を持つ専門家によるペネトレーションテストは、自社では気づきにくいセキュリティ上の弱点を発見し、より実効性のある対策を講じるための重要な手がかりとなります。 特に、中小企業においてはリソース不足からセキュリティ強化が難しいケースも多いため、第三者による客観的な診断がリスク低減につながります。
ペネトレーションテストの流れ
一般的なペネトレーションテストは、「準備」→「テスト」→「レポート作成」の3段階で進められます。それぞれの段階で適切なプロセスを踏むことで、セキュリティ上の弱点を効果的に洗い出すことが可能です。
①準備
- 対象システムのヒアリング:テスト対象となるシステムの構成や利用状況を詳しく確認します。サーバやネットワーク機器、アプリケーションの種類やバージョン、アクセス権限の範囲などを整理し、攻撃ポイントを特定するための基礎情報を収集します。
- 攻撃シナリオの作成:ヒアリング内容にもとづき、想定される脅威や攻撃経路を具体的に定義したシナリオを作成します。テストの目的、対象範囲、使用ツール、実施期間などもあわせて決定し、計画を明確にします。これにより、攻撃者の視点に立った現実的なペネトレーションテストが実現します。
②テスト実施
- 攻撃・侵入の試行:作成した攻撃シナリオにもとづき、さまざまなツールや手法を用いてシステムへの攻撃や侵入を試みます。ネットワークペネトレーションテストではポートスキャンや脆弱性スキャン、WebアプリケーションテストではSQLインジェクションやXSSの試行などが含まれます。
- 結果の記録・証拠収集:攻撃の過程や結果、発見された脆弱性や侵入成功の証拠を詳細に記録します。これにより、後続の分析で攻撃経路を特定しやすくし、再現性を確保します。特に、脆弱性が悪用された際のリスク評価を正確に行うため、証拠データを整理して保存することが重要です。
③レポート作成
( 3 ) ペネトレーションテストのメリットと注意点
ペネトレーションテストを実施することには、多くのメリットがあります。 最大のメリットは、想定されるリアルな攻撃シナリオにもとづいてテストを行うため、机上の空論では見つけられないセキュリティホールを早期に発見できる点です。これにより、攻撃者視点でシステムの防御力を評価し、潜在的なリスクを具体的に洗い出すことができます。
その他のメリットとしては、以下が挙げられます。
-
安全性を確保しながら強度を調査できる
ペネトレーションテストは、実際の攻撃をシミュレートして実施しますが、あくまでテスト環境での実行であるため、実際の被害を発生させるリスクを回避できます。これにより、安全な方法でシステムの強度を評価できます。
-
個別ニーズに対応したテスト設計が可能
テストは、企業のシステム環境やビジネスリスクに応じてカスタマイズできるため、オーダーメイドのテストが実現します。業種特有の脅威や環境要因を考慮したテストが可能であり、汎用的な診断では見つけにくい弱点も検出できます。
-
具体的なセキュリティ強化策の策定が可能
テスト結果をまとめた報告書は、発見された脆弱性とその深刻度、攻撃手法や侵入経路を詳細に示します。これにより、管理者は具体的なセキュリティ強化策を立案しやすくなり、改善計画の客観的な根拠として活用できます。
ペネトレーションテストの注意点
多くのメリットがある一方で、ペネトレーションテストを実施する際には、以下の点に注意が必要です。
-
コストと時間
ペネトレーションテストは、テスト対象の規模や範囲、シナリオの複雑さによって、必要となるコストや所要時間が大きく異なります。特に、大規模なネットワークや多様なシステムを対象とする場合、テストの計画と実施に相応のコストがかかることがあります。
事前に見積もりをしっかりと確認し、費用対効果を検討した上で、計画的に実施することが重要です。 - 定期的な実施の必要性
- 実施者のスキルへの依存
( 4 ) 最新のセキュリティ脅威と今後必要な対策
近年、サイバー攻撃の手口はますます高度化・巧妙化しており、特に中小企業を狙った攻撃が増加傾向にあります。
セキュリティ対策が比較的脆弱と見なされがちな中小企業をターゲットとし、ランサムウェア(身代金要求型ウイルス)やサプライチェーン攻撃(取引先を経由した攻撃)(※5)などが頻発しています。これらの攻撃は、従来の防御策では十分に防ぎきれないケースが多く、深刻な被害を引き起こしています。
「ウイルス対策ソフトを導入しているから安心」と考える企業も少なくありませんが、残念ながらそれだけでは今日の複雑なサイバー攻撃を完全に防ぐことは難しいのが現実です。
ランサムウェアはネットワークの脆弱性を突いて内部に侵入し、ファイルを暗号化して身代金を要求します。また、サプライチェーン攻撃では、取引先システムを介してマルウェアを拡散し、機密情報の漏洩や不正アクセスを引き起こすリスクが高まります。
このように、従来型のウイルス対策ソフトでは、未知の脅威や複雑な攻撃手法を検知しきれないケースが多発しているため、さらなるセキュリティ強化が求められています。
こうした状況を受け、ペネトレーションテストを実施し、自社のセキュリティ対策を見直す企業が増えています。ペネトレーションテストは、攻撃者視点でシステムへの侵入や不正アクセスを試みることで、現実的な攻撃耐性を評価できる手法です。
特に、ランサムウェア攻撃を模倣して内部侵入経路を洗い出したり、サプライチェーン経由での脆弱性を検証したりすることで、従来のセキュリティ対策の見落としを補完します。
これにより、セキュリティホールを特定し、現実的な攻撃シナリオにもとづいた防御策を講じることが可能になります。
<ネットワークセキュリティの課題に応えるUTM>
自社のセキュリティ対策に不安がある、より強固なセキュリティ対策を講じたいという企業に、注目していただきたいのがUTMです。UTMは複数のネットワークセキュリティを集中管理するツールで、一台に多くのセキュリティ機能が搭載されており、多層的な対策に適しています。
例えば、サクサのUTM「SS7000Ⅲ」はウイルスのデータパターンを自動更新することで最新のネットワークウイルスに対応。不正アクセス、ウイルス侵入など、インターネットから来るさまざまな脅威から統合的に社内ネットワークを守ります。また外部からの攻撃を防ぐだけでなく、内部からの情報漏洩リスクも抑えることができます。 さらにウイルス感染時は無料でPCウイルス駆除サービスが受けられます。専任の情報システム担当者を置く余裕がない会社でも、UTMを導入することで複雑化するサイバー攻撃のリスクに対応が可能です
( 5 ) まとめ
この記事では、「ペネトレーションテストとは?」という基本的な問いから、その種類や手法、メリット、注意点、さらに脆弱性診断との違いについて解説しました。
また、近年のサイバー攻撃の動向を踏まえ、中小企業が取り組むべき効果的なセキュリティ対策として、UTM(統合脅威管理)についてもご紹介しました。
ペネトレーションテストは、自社のセキュリティ強度を客観的に評価し、潜在的なリスクを洗い出すために有効な手段です。実際に攻撃者視点で侵入を試みることで、現実的な攻撃シナリオを検証し、セキュリティホールを早期に特定できます。
テスト結果をもとに、UTMのような統合的なセキュリティソリューションを導入することで、サイバー攻撃による被害を未然に防ぐことが可能です。特に、中小企業においては、リソース不足を補うためにも、UTMを活用した多層防御が鍵となります。
<UTM「SS7000Ⅲ」のご紹介>
サクサでは、UTM「SS7000Ⅲ」の詳細や、UTMの基礎知識、最新の脅威について解説する特設ページや動画コンテンツをご用意しています。UTMは、ファイアウォールやアンチウイルス、IPS/IDS(侵入防止/検知システム)を統合し、多角的なセキュリティ対策を実現します。
ぜひ、貴社のセキュリティ対策強化の参考にしてください。最新情報をチェックし、サイバーリスクに備えた適切な防御策を講じましょう。
課題解決に役立つ資料はこちら!
経営課題におけるトレンド情報や課題解決にお役立ていただける資料をまとめております。
ぜひ一度お読みください。