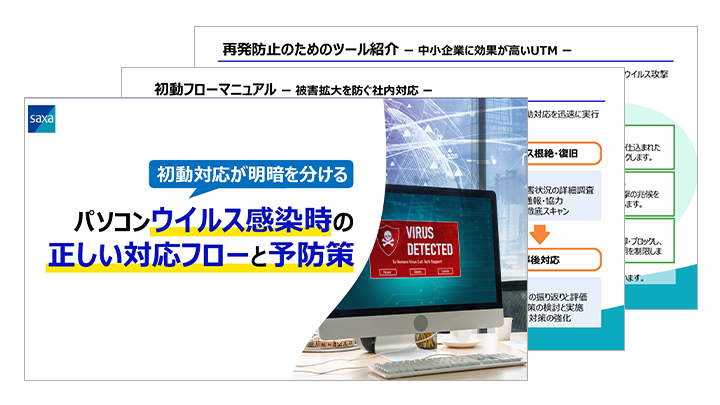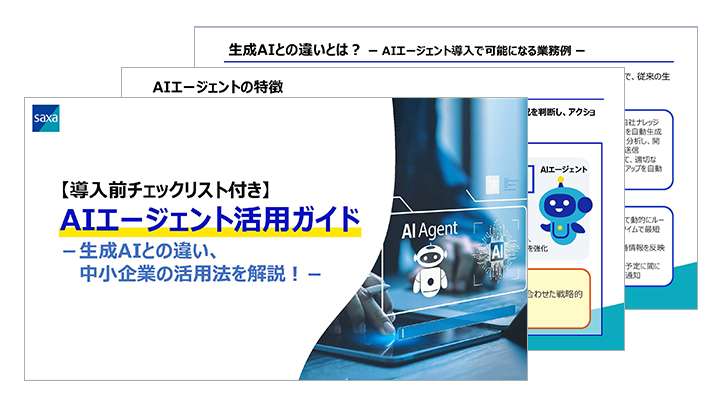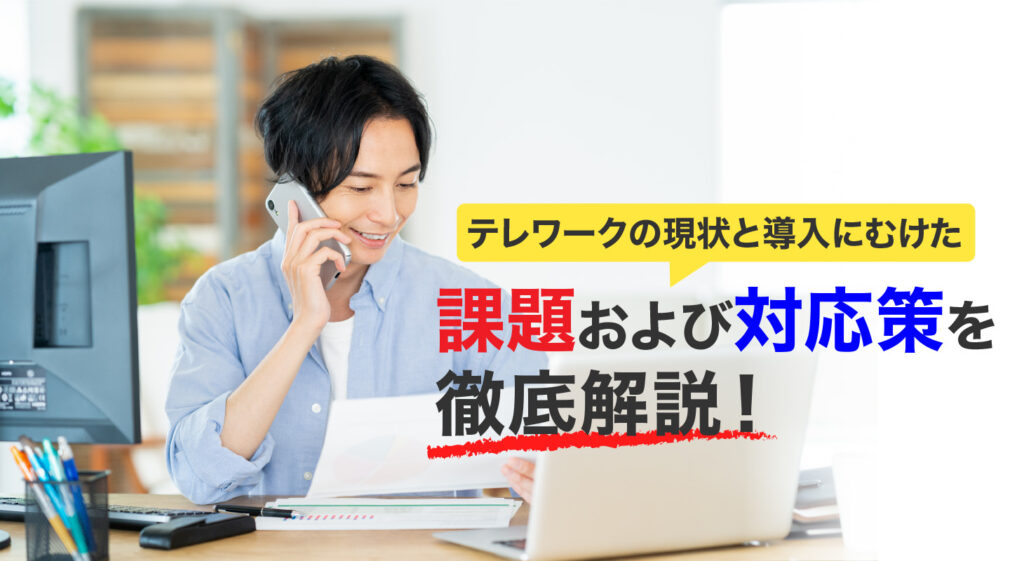「業務効率化を図る」ことは、企業にとって重要な課題の一つです。もちろん多くの経営者がそのことは承知しており、さまざまな取り組みを実践されているでしょう。しかし、なぜ業務効率化が必要なのか、業務のどの部分を効率化すればよいのかといった意識を持たないまま取り組んでいるケースも多いのではないでしょうか。今回は業務効率化とは何かを改めて考察するとともに、メリットや進め方について解説します。業務効率化を進める際の参考になさってください。

今回のお悩み
「業務効率化を図る」とは具体的にどのようなことか、メリットやポイント、手順が知りたい。業務効率化を図る方法や、どのようなツールがあるのかも詳しく知りたい。

私が解説します!
業務効率化を図る重要性を知り、自社でできるアイデアを取り入れていきましょう。手順が具体的にイメージできるよう、詳しく解説します。
目次
( 1 ) 業務効率化を図るとは?3つの重要性も紹介
「業務効率化」とは、業務における無駄をなくし、より少ない労力でより多くの成果を出すことであり、「業務効率化を図る」とは、そのための取り組みを指します。
業務効率化を図るにあたっては、業務を行う際に「ムダ」「ムリ」「ムラ」がないかを見定めることが重要です。そのうえで最適化や改善に向けて取り組むことにより、業務は効率化されます。
業務の「ムダ」 業務の「ムリ」 業務の「ムラ」
「業務効率化」とは、業務における無駄をなくし、より少ない労力でより多くの成果を出すことであり、「業務効率化を図る」とは、そのための取り組みを指します。
業務効率化を図るにあたっては、業務を行う際に「ムダ」「ムリ」「ムラ」がないかを見定めることが重要です。そのうえで最適化や改善に向けて取り組むことにより、業務は効率化されます。
| 業務の「ムダ」 | 業務の「ムリ」 | 業務の「ムラ」 |
|---|---|---|
| 通例として行われている形式的な段取りや会議、オフィスのレイアウトや導線の使いにくさ など | 長時間労働の常態化による社員への負荷、キャパオーバーな生産体制、過密なスケジュール など | 業務プロセスやフローが標準化されていない、情報共有が図られておらず従業員の理解度が異なる など |
業務効率化における3つの重要性
業務効率化は、なぜ企業にとって必要なのか、主な重要性を3つ挙げてみましょう。
競争力の強化
企業としての競争力を強化するためには、新たな商品やサービスの開発に時間をかけて取り組む必要があります。業務効率化によって、これまで1時間かかっていた業務が半分で済むようになれば、残りの時間を新たな取り組みに使用することができます。
働き方改革の推進
「働き方改革」は、今や企業にとって重要なテーマです。仕事にやりがいがあり、プライベートも充実している。そんなワークライフバランス(※1)の実現に向けて、長時間労働を是正するなど、労働環境を改善する方法としても業務効率化は有効です。
人材不足の解消
生産年齢人口(※2)の減少を背景に、人材不足が大きな社会課題となっています。さらに中小企業においては、人材の確保が難しいことも深刻化しています。少ない労力で成果をあげる業務効率化は、これらの課題を解消するためにも欠かせません。
※1 ワークライフバランス:働くすべての人が仕事と生活(育児・趣味・休養など)の調和をとり、その両方を充実させる生き方のこと。※2 生産年齢人口:生産活動を中心になって支える15歳以上65歳未満の人口。少子高齢化の進行により、減少が続いている。
( 2 ) 業務効率化を図るメリット
業務効率化を実現することによって、さまざまなメリットが得られます。そして、そのメリットを最大化するために欠かせないのが、デジタル化(IT化)です。デジタル化とは、アナログで行っていた手法をデジタルに変換することを指します。従来、紙ベースで行っていた契約や請求業務を電子化する、手作業をシステム化するといった例が挙げられます。また、
生成AIの活用もさまざまな分野で広がっています。業務をデジタル化すれば、効率化は一気に加速します。
コスト削減
業務効率化によって作業時間が短縮されると、人件費をはじめさまざまなコストが削減できます。デジタル化によってミスやトラブルが発生するリスクも軽減されるため、その対応にかかるコストも大幅に減らすことができます。
生産性の向上
生産性の向上とは、ものづくりの話だけに限りません。サービス業でも顧客対応のスピードアップを実現することで、高収益へとつなげることができます。また、近年はIT化からさらに進んだDX化(※3)に取り組む企業も増加しています。デジタル技術を活用することで、生産性の向上だけでなく、新たな価値創造にもつなげることができるようになります。
従業員の満足度向上
残業が減り、ストレスが軽減されることで、従業員の満足度は向上します。高いモチベーションで働ける職場では、従業員エンゲージメント(※4)の向上はもちろん、求職者の増加や定着率の向上も期待できます。従業員もワークライフバランスが充実するという好循環が生まれます。
※3 DX化:DXは「Digital Transformation」の略。デジタル技術を使って、生活や社会をトランスフォーメーション(変革)することを指す。※4 従業員エンゲージメント:従業員が自社に対して誇りと愛着を持ち、自発的に貢献したいと思うこと。会社に対して高い信頼度がある状態。
( 3 ) 業務効率化を図るアイデア
業務効率化を図るにあたっては、漠然と取り組むのではなく、目的意識を持って着手することが大事です。何をどこから着手すればいいのかわからないという方のために、「個人でできること」と「企業が取り組むこと」に分けて、アイデアを示します。これらをヒントにして、できることから始めてみてください。
【個人でできる業務効率化】
自分が日常的に行っている業務を見直すことで、時間短縮や負担軽減が図れるだけでなく、新たな業務へのチャレンジやスキルアップなどに活用できます。
- タスクのリスト化
- 業務の期限の設定
- 適度な休憩を取る
- デスク周りの整理
- 情報共有の徹底
まずはやるべきタスクをリスト化し、優先順位をつけることから始めましょう。期限が設けられていない業務も、自ら設定することで効率的に処理できます。また、適度な休憩を取ることで集中して業務に取り組めます。見落としがちなところですが、デスク周りを整理しておくこともポイントです。気持ちよく業務ができるだけでなく、大事な書類や資料が紛失することも防ぎます。さらに、報告・連絡・相談などの情報共有を適切に行うことで、ミスや属人化(※5)の防止にもつながります。
【企業として取り組むべき業務効率化】
組織的に業務効率化を図ることで、コスト削減や生産性向上、従業員の満足度アップなどが期待できます。
- ペーパーレス化の推進
- 定型業務の自動化
- コミュニケーションツールの導入
- テレワークの活用
- 業務のマニュアル化
デジタルツールを活用し、紙ベースで行っていた業務をデジタル化することで、時間短縮、コスト削減につながります。RPA(※6)ツールによる定型業務の自動化は、昨今問題となっている人材不足の解消にも有効です。ビジネスチャットの利用で、外出先やテレワーク中でも円滑なコミュニケーションが可能となり、情報共有や部門間の連携もスムーズになります。また、暗黙の了解などの明確化されていないルールや業務フローをマニュアル化することにより、業務のムラやミスをなくし、業務効率化を促進することができます。
〈こちらもオススメ!〉
業務効率化に役立つアイデアについて詳しく解説しています。
※6 RPA:「Robotic Process Automation」の略で、「業務プロセスの自動化」の意。パソコン上の作業を、ソフトウェアロボットが人の代わりに自動で行う。
( 4 ) 業務効率化を図るツール
業務効率化を図るために欠かせない8つのデジタルツールを紹介します。
| ビジネスチャット | 社内だけでなく、社外の人も含めてスムーズなコミュニケーションを図ることができるツール。リアルタイムでの迅速なやりとりが可能 |
| グループウェア | コミュニケーションツールの一種。プロジェクトの管理、ドキュメントの共有、スケジュールの調整など、広範な業務プロセスにおいて有効 |
|
VPN
(Virtual Private Network) |
特定の人だけが利用できる専用ネットワークを構築し、社外から社内ネットワークに安全にアクセスできる。テレワークや外出時でもセキュアなアクセスが可能 |
|
RPAツール
(Robotic Process Automation) |
自動化ツールとも呼ばれ、日常的に行う定型業務を自動化する。業務の流れを登録し、AIなどによって作業を自動で行うもので、主に事務的な業務に用いられる |
| 勤怠管理システム | 出勤や退勤時間を正確に記録し、従業員の勤怠状況を「見える化」するツール。企業が従業員の働き方を把握し、管理するうえで有効 |
| クラウドサービス | インターネット上でデータの保管や作業に必要なソフトなどが利用できる。テレワークや外出先での作業や情報共有を容易に行うことができるサービスもある |
|
CRMツール
(Customer Relationship Management) |
顧客管理ツールとも呼ばれ、顧客情報を把握・一元管理することで顧客との良好な関係性を構築する。営業活動だけでなく、マーケティングにも活用される |
|
SFAツール
(Sales Force Automation) |
営業支援システム。顧客や案件の情報を一元管理し、リアルタイムで営業活動や進捗状況を把握できる。営業ノウハウや知見の共有によりパフォーマンス向上が図れる |
| 生成AI | 膨大なデータから学習し、テキストや画像、動画、音声などを自動生成。文書作成、市場分析、プログラミング、カスタマーサポートなどに活用されている |

〈お役立ち資料はこちら〉
生成AIの解説をはじめ、セキュリティリスクや対策までを詳しく解説しています。
( 5 ) 業務効率化を図るためのステップ
業務効率化は具体的にどのように進めればよいのでしょうか。以下の4つのステップによって業務効率化は円滑に進めることができます。
ステップ01
問題を抽出する まずは現状把握に努め、問題点を洗い出す必要があります。先にも述べた「ムダ」「ムリ」「ムラ」がどこにあるのかという視点で、業務プロセスや職場環境を今一度見直してみることからスタートしましょう。
ステップ02
改善計画を策定する 問題点が洗い出せたら、どう改善したいか、またそれを達成するためには何が必要かを検討します。中には実現に時間のかかるものもあるでしょう。「できる」「できない」の判断も含め、着手する優先順位をつけながら、改善計画を策定します。
ステップ03
計画を実行する 改善計画に沿って、選定したツールの導入や新たな業務プロセスなどを実行します。ツール導入後は従業員研修などを実施し、効果的に活用できるよう促します。また、自社だけで実行することが困難な場合は、外部の専門家に協力を求めることも重要です。
ステップ04
効果を検証する 導入したらそれで終わりではありません。定期的に効果検証を行い、必要に応じて見直しや改善を行います。業務効率化を評価する際には、工数や残業時間、売上の変化など、定量化できるデータを用い、強化すべきポイントなども検討しましょう。
( 6 ) 業務効率化を図る際に押さえておきたいポイント
業務効率化を進めるにあたって、押さえておきたいポイントを紹介します。業務効率化は一つの問題をクリアしたからといって、すぐに結果が出るとは限りません。潜在的な問題点などもあるため、よりよいものへとブラッシュアップを図っていくことが重要です。
労働環境の見直し
業務プロセスの見直しだけでなく、オフィスなどの労働環境に改善すべき要素が潜んでいる場合もあります。「資料が整理されずオフィス内が雑然としている」「動線が複雑になっている」「使用する機器がどこにあるかわからない」などの問題を解決することで、働きやすさは向上し、業務効率化につながります。
人間関係への配慮
問題が「人」にある場合も考えられます。仕事で思うような結果を出せず悩んでいるというケースもあれば、人間関係がうまくいかずメンタルヘルスが不調になっているというケースもあるでしょう。従業員へのヒアリングやアンケートの実施などによって、不満や悩みを把握し、適切な対応を行うことが大切です。
部門間の連携強化
業務効率化には部門間の連携も重要です。関連する業務を行う部門はもちろん、複数の部門で取り組むプロジェクトでは、特に連携が欠かせません。円滑なコミュニケーションによって知識の融合や新たなアイデアの創出も期待できます。部門間の連携が強化されることで、業務効率化も促進されます。
改善意識の醸成
実際に業務を行わない経営層は、現場の問題に気づきにくい側面があります。そこで重要なのは、現場の従業員一人ひとりの「改善意識」と、それを経営層に伝える「対話の場」の設定です。対話を通じて、業務効率化が働き方改革につながり、個々のワークライフバランスを充実させることをしっかり理解してもらうことが大切です。
( 7 ) まとめ
今回は、業務効率化を図るとは何かを考えるとともに、3つの重要性や手順などを紹介しました。業務効率化のメリットや押さえておきたいポイント、どのような手法で進めればよいのかなどがご理解いただけたのではないでしょうか。
業務効率化を図るためには、業務のデジタル化が有効です。SAXA-DX Naviでは、デジタルシフトによる業務効率化が求められている理由や、デジタルシフトのポイント、成功事例などをまとめた資料をはじめ、さまざまなお役立ち資料をご提供しています。ぜひ、ご活用ください。
課題解決に役立つ資料はこちら!
経営課題におけるトレンド情報や課題解決にお役立ていただける資料をまとめております。
ぜひ一度お読みください。