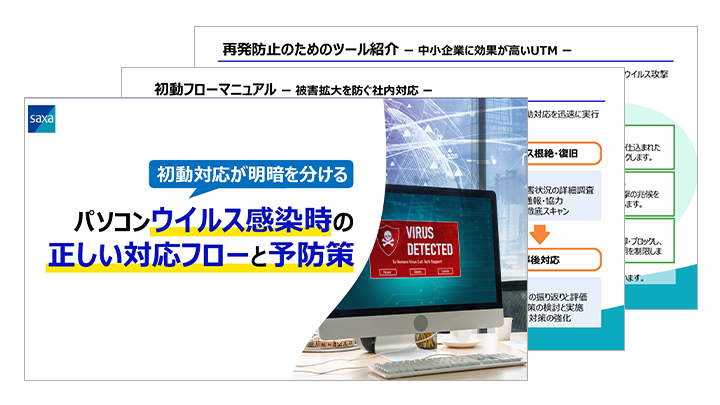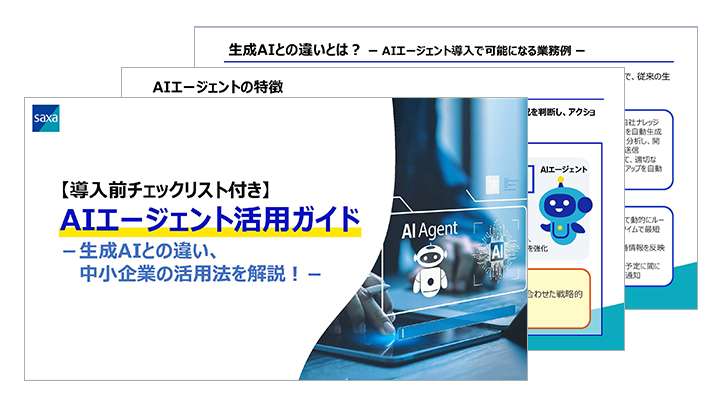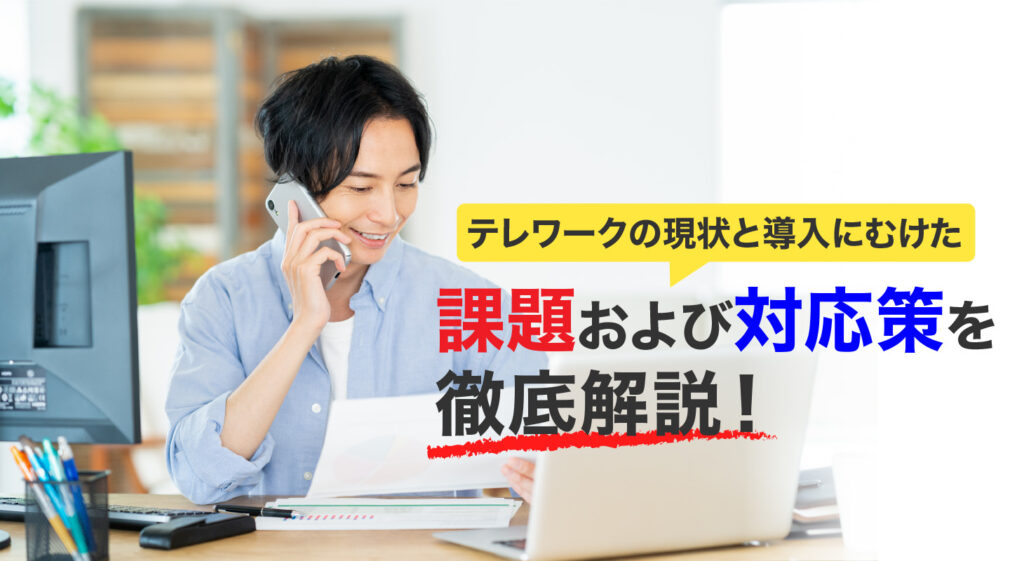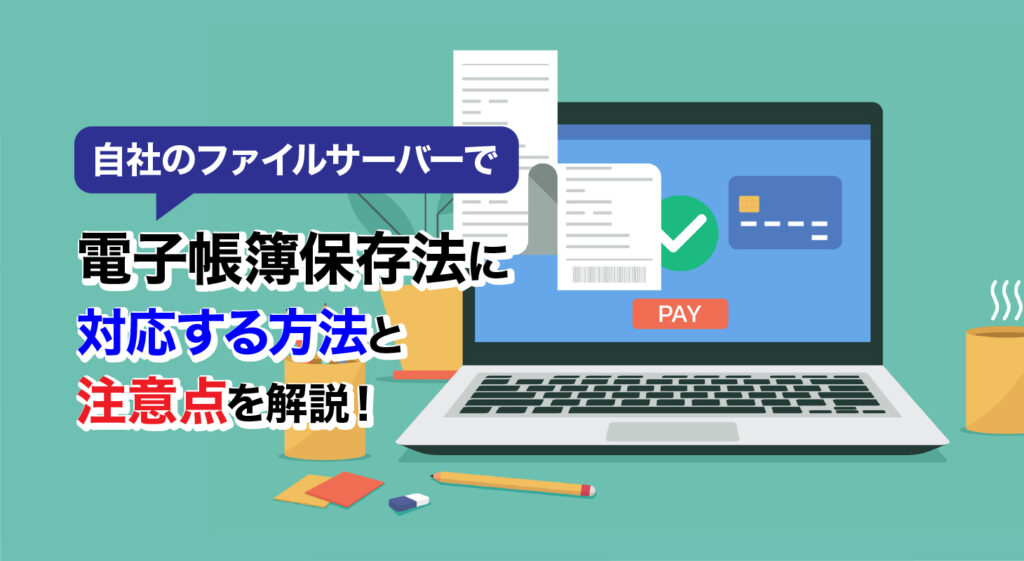ビジネスシーンにおけるデジタル化が加速するとともに、情報セキュリティインシデントも多発するようになっています。情報セキュリティインシデントの要因には、不正アクセスなど外部からの攻撃だけでなく、従業員によるヒューマンエラーも挙げられます。近年は、テレワークなどの多様な働き方が進み、従業員一人ひとりの情報セキュリティに対する正しい理解と適切な対策が求められます。
今回は、従業員のセキュリティ意識の低さが引き起こすリスクと、企業が行うべき対策について解説します。ぜひ自社のセキュリティレベルを高めるための参考になさってください。
〈こちらもオススメ!〉
情報セキュリティにおけるリスクや必要な対策を解説しています。

今回のお悩み
従業員のセキュリティ意識が低いことで、情報セキュリティインシデントのリスクが高まると聞き、自社の対策について不安を感じている。具体的にどのようなリスクがあるのか、従業員の意識を高めることができる対策方法なども知りたい。

私が解説します!
従業員のセキュリティ意識の向上は、情報セキュリティインシデントのリスクから自社を守るために欠かせない取り組みです。今回は、従業員のセキュリティ意識の低さが招くリスクと、意識向上のために必要なポイントについて、対策方法を交えて詳しく紹介します。
( 1 ) なぜセキュリティ意識が低くなるのか
企業における情報セキュリティの強化は、重要な経営課題でもあります。しかし、情報セキュリティ対策が適切に行えていない企業も少なくありません。その原因の一つが、従業員のセキュリティ意識の低さです。その理由として、以下の4つが考えられます。
|
セキュリティ
リスクへの理解不足 |
情報漏洩やサイバー攻撃のリスクがどのような影響を与えるのか具体的にイメージができておらず、セキュリティ対策の必要性を認識できていない。企業の規模や業種によっては、セキュリティリスクによる被害が直接的な影響として感じにくい |
|
セキュリティの
知識不足 |
セキュリティに関する知識が不足しており、適切な対策を取れない。不審なメールの見分け方、インターネットの安全な利用方法、特定されにくいパスワード設定など、基本的な知識が不足し、無意識のうちにリスクを招く行動を取ってしまう |
|
セキュリティ対策が
面倒 |
期的なパスワードの変更やソフトの更新など、セキュリティ対策を面倒に感じている。業務に追われている場合や、業務が集中する繁忙期など、目の前の業務を優先してセキュリティ対策を後回しにしてしまう |
|
セキュリティ管理が
不十分 |
テレワークなど外部から社内システムにアクセスする際のルール策定や従業員への教育がされていない。マルウェア感染や情報機器の紛失などのリスクに対して、十分な対策や運用体制がとられておらず、セキュリティ管理が行き届いていない |
( 2 ) セキュリティ意識が低いことによるリスク
企業としてセキュリティ対策を講じていても、従業員のセキュリティ意識が低いとさまざまなリスクが発生します。主なリスク4つをそれぞれ解説します。
情報漏洩
情報漏洩は、セキュリティ意識が低いことで起こりやすいリスクです。例えば、「不審なメールやWebサイトを開く」「安全性が低いフリーWi-Fiを使用する」「予測されやすい安易なパスワードを使用している」といった行動は、マルウェア感染や不正アクセスの要因となり、情報漏洩のリスクが高まります。また、従業員によるメール誤送信やデバイスの紛失など、ヒューマンエラーによって個人情報や機密情報が流出してしまうケースもあります。
〈お役立ち資料はこちら〉
自社の情報漏洩対策の現状や取り組むべき対策がわかるチェックリストを提供しています。
デバイスの乗っ取り
セキュリティ意識が低く、不審なメールやWebサイトにアクセスしてしまうと、パソコンやスマートフォンなどのデバイスがマルウェアに感染し、乗っ取られるリスクがあります。乗っ取られたデバイスから他のデバイスへと感染が広がり、組織全体に大きな影響を与えることもあります。また、気づかないうちに遠隔操作され、取引先への侵入の「踏み台」や、迷惑メールの送信元などに悪用される恐れもあります。
社会的信頼の低下
情報漏洩は、企業の社会的信頼に大きく影響します。従業員のミスによるものであればなおさらで、取引先や顧客は不信感から情報を預けることに対して不安を感じ、取引中止や顧客離れにもつながります。一度イメージが低下してしまうと信頼回復に時間がかかり、深刻なダメージを受けるリスクがあります。また、株価の下落や新規顧客の獲得が難しくなるなど、経済的損失を招く可能性もあります。
金銭的被害の発生
サイバー攻撃の多くはメールやWebサイトを通じて行われます。セキュリティ意識が低いとマルウェア感染や不正アクセスのリスクが高くなります。ランサムウェアもその一つで、感染すると保有するデータが暗号化され、解除と引き換えに金銭(身代金)を要求されます。データのバックアップを取っておくことが対策の一つとされていますが、これを怠ると復旧費用や業務停止による損失が大きくなり、多額の金銭的損害を被る可能性があります。
( 3 ) セキュリティ意識を高めるポイント5選
セキュリティ意識が低いことで生じるリスクを防ぐためには、従業員一人ひとりのリテラシーや意識向上が不可欠です。従業員のセキュリティ意識を高めるポイントとして、以下の5つが挙げられます。それぞれについて詳しく紹介します。
情報セキュリティポリシーの策定
情報セキュリティポリシーを策定し、従業員にも周知徹底しましょう。情報セキュリティポリシーとは、組織全体で情報を守るための方針や行動指針を明文化するものです。一般的に、「基本方針(理念・目的・目標の明示)」「対策基準(ガイドラインづくり)」「実施手順(マニュアルづくり)」の3つに分けて策定します。誰もが正しく実践できるように、何をどうすればいいのか具体的に示し、わかりやすい記述にすることが重要です。
〈こちらもオススメ!〉
改正個人情報保護法のポイントについて詳しく解説しています。
従業員へのセキュリティ研修
日ごろから情報セキュリティに関する従業員教育や研修を定期的に行うことで、対策の効果を高めることが期待できます。
例えば、研修では「不審なメールを受信した」「セキュリティソフトやツールの警告があった」などの場合にどう対処すべきか、ノウハウを教えることを基本とします。さらに守るべきルールについて指導し、情報セキュリティインシデントに関する予行演習なども行うとよいでしょう。
人事評価への反映
日々の業務において適切なセキュリティ対策ができているか、従業員の取り組みを人事評価に反映させることも有効です。例えば、データ管理の適切さ、研修の参加状況や理解度などをポイント化することによって、評価しやすくなります。従業員は自身のセキュリティ対策が評価されることでモチベーションが高まり、より積極的にセキュリティ対策に取り組むことが期待できます。
社内アカウント管理の徹底
社内アカウントは、従業員が社内システムにアクセスするための重要な認証情報です。アカウント管理を徹底することで、情報漏洩のリスクを大幅に軽減できます。定期的なパスワード変更をはじめ、業務に応じたアカウントの設定、アクセス権限の付与などを実施しましょう。退職者などの不要なアカウントは不正利用されるケースが多いため、定期的な精査・削除が必要です。
セキュリティ対策ツールの活用
高度なセキュリティ機能を備えた対策ツールの導入により、組織全体のセキュリティレベルを高めることができます。特にコストをあまりかけられない中小企業には、1台に複数のセキュリティ機能を備えたUTMがおすすめです。社内外を問わず、さまざまな脅威から社内システムを守ることができ、従業員の誤操作による情報漏洩を防ぐことも可能です。また、セキュリティ対策は、一度実施すれば終わりというものではありません。システムや運用状況に問題がないか、定期的に確認することが重要です。
( 4 ) まとめ
今回は、従業員の情報セキュリティ意識が低い原因や、意識を向上させる効果的な取り組みについて、さまざまな角度から解説してきました。これらのポイントを押さえ、継続的に従業員への教育やセキュリティ対策を講じることで、セキュリティリスクを最小限に抑えることができます。
サクサでは記事で紹介したUTMをはじめ、情報セキュリティの課題を解決するツールや、情報セキュリティ対策のご提案を通して中堅・中小企業のサポートをさせていただきます。ぜひ気軽にご相談ください。
また、SAXA-DX Naviでは、情報セキュリティの動向や必要な対策についてさまざまなお役立ち資料をご提供しています。ぜひご活用ください。
課題解決に役立つ資料はこちら!
経営課題におけるトレンド情報や課題解決にお役立ていただける資料をまとめております。
ぜひ一度お読みください。