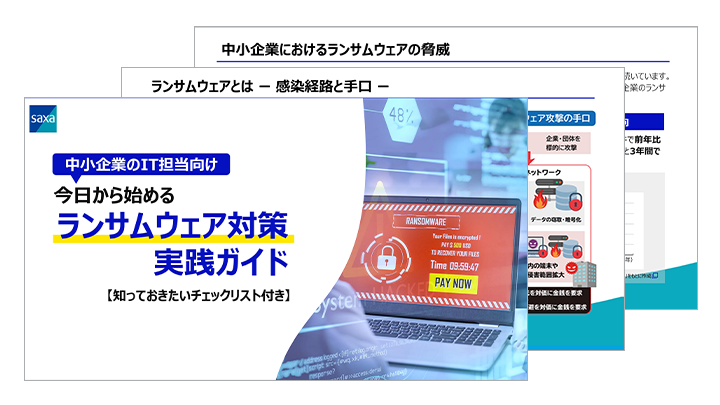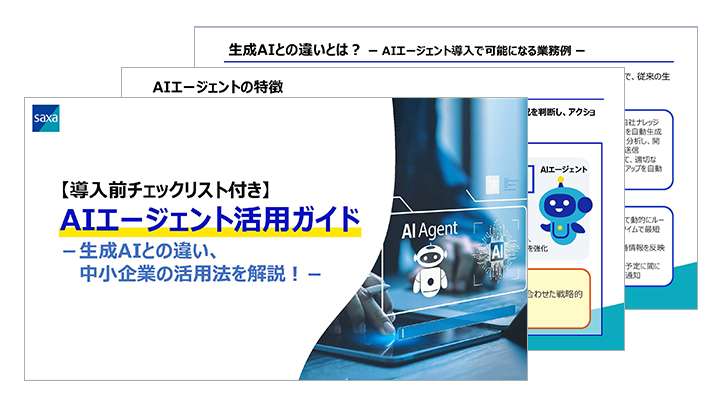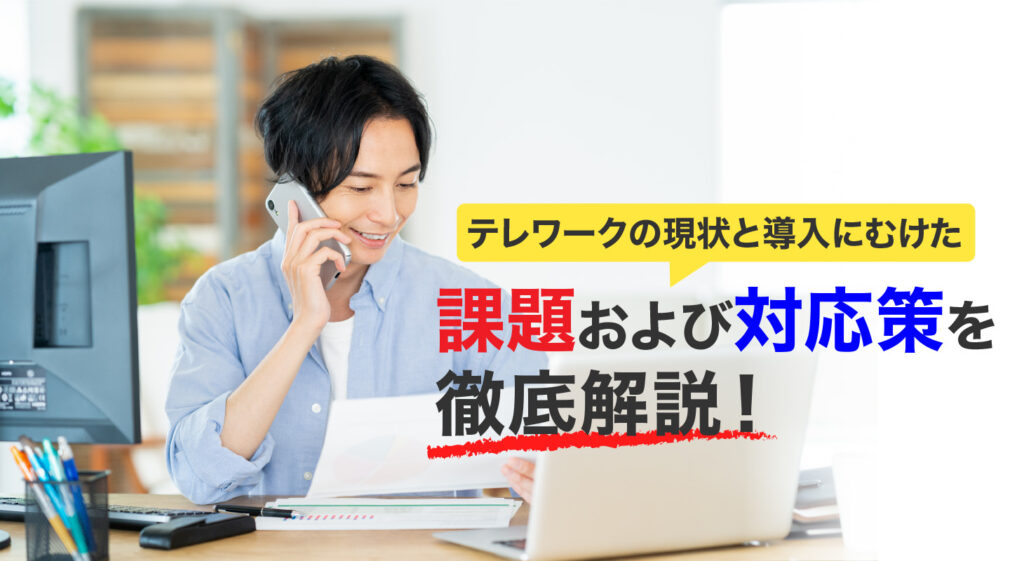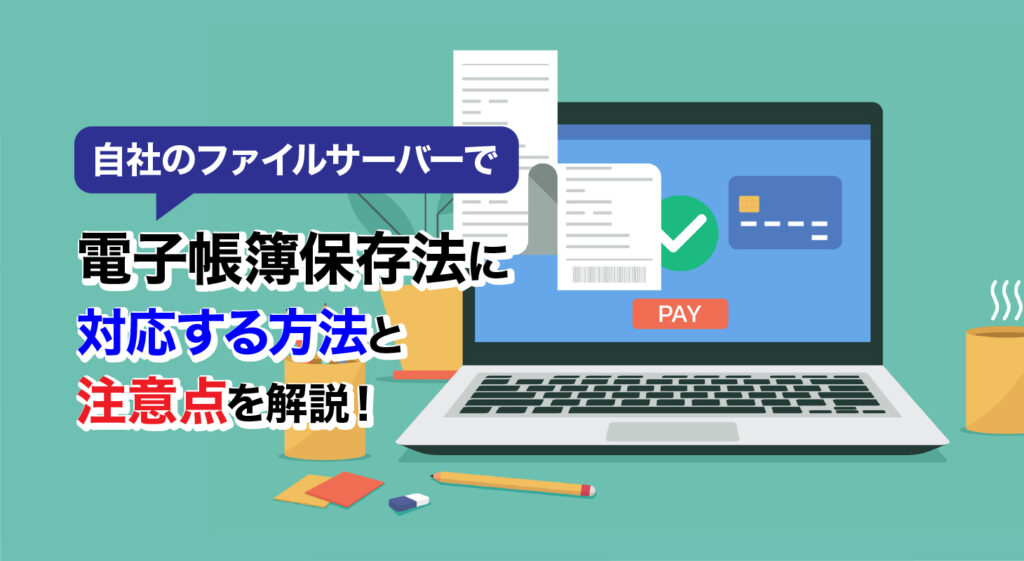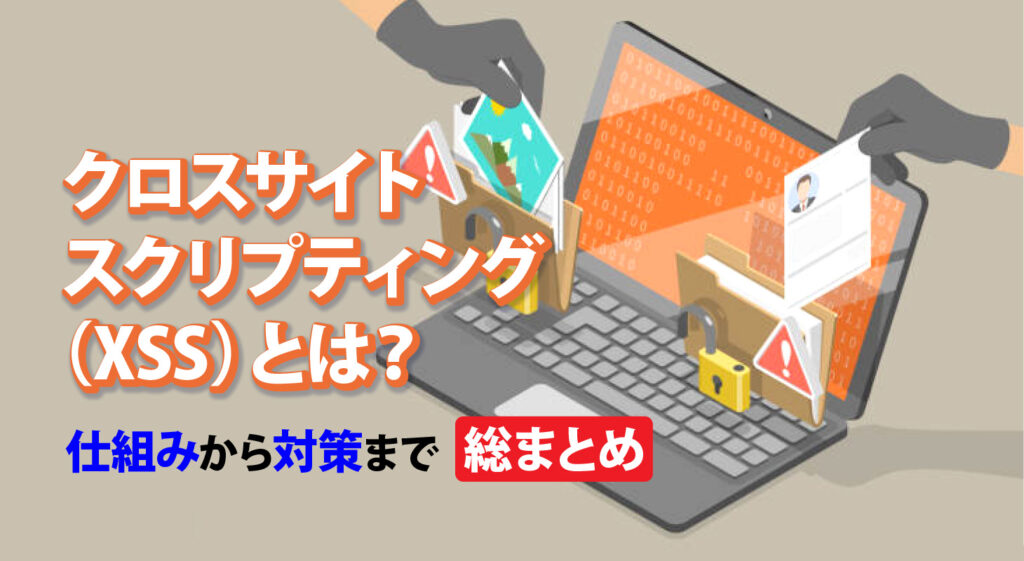サイバー攻撃の増加や複雑化により、企業はセキュリティリスクの課題に直面しています。また、セキュリティ対策に関する法的規制が厳格化し、企業におけるネットワーク・セキュリティ対策は急務となっています。しかし、中小企業はセキュリティ対策に多くのコストや人員を割けないのが現状です。そこで今回は、複数のセキュリティ機能を一つに統合した「UTM(統合脅威管理)」について、機能や導入メリット、選び方などをわかりやすく解説していきます。導入費用やランニングコスト、導入方法に関してもご紹介します。
目次
( 1 ) UTM(統合脅威管理)とは?
UTM(Unified Threat Management)は、複数のセキュリティ機能を一台の専用機器(アプライアンス)に統合した「統合脅威管理」システムです。従来は個別に導入していたファイアウォールやアンチウイルス(ウイルス対策)、Web/コンテンツフィルタリングなどの機能を一元管理でき、コストを抑えながら包括的なセキュリティ対策が可能になります。UTMは通信の送受信を一元監視し、コンピューターウイルス(computer virus)やスパイウェア(spyware)、ワーム、botなど有害トラフィックを検出・排除します。単体ツールの寄せ集めではなく、アプライアンス1つで運用できる点が特長です。
この記事を読んでいる方には 【UTM丸わかりガイド】 もおすすめです。基本機能や導入メリット、選び方をまとめた資料を無料でダウンロードできます。
( 2 ) UTMの主な機能
UTMには、主に6つの重要なセキュリティ機能が備わっています。それぞれの機能は以下の通りです。
ファイアウォール機能
ファイアウォール機能は、UTMの基盤となる最も重要な機能です。外部ネットワークと内部ネットワークの境界で通信の許可と拒否を判断し、不正なアクセスを遮断します。例えば、在宅勤務(リモートワーク)中の端末を外部攻撃から守る際に効果的です。具体的には、IPアドレスやポート番号、セッション状態を監視することで、許可されていない通信を自動的にブロックします。
アンチウイルス(ウイルス対策)機能
アンチウイルス機能は、シグネチャとヒューリスティック(振る舞い)で既知のマルウェアやワーム、スパイウェアの検知・除去を行います。この機能は、ファイルのダウンロード時やメールの添付ファイル、HTTP通信を通じて送受信されるデータを常時監視し、危険なソフトウェアを発見すると即座に隔離または削除します。例えば、見積書を装った不審なExcelを受信した際、ゲートウェイ側でパターン照合とサンドボックス実行を行い、悪性マクロの挙動が確認された時点でユーザー受信箱へ届く前に検出する、といった前段対策が可能です。
アンチスパム・メール保護機能
アンチスパム・メール保護機能は、年々巧妙化する迷惑メール経由の攻撃から企業を守るための保護機能で、送信元の信頼性、メールヘッダーの情報、本文の内容、含まれるURLなどを総合的に分析し、スパムメールやフィッシングメールを自動的に除外します。例えば、契約更新のお知らせなどの業務メールを装うメールについて、差出人ドメイン認証(SPF/DKIM/DMARC)とURLレピュテーションを組み合わせ、検知スコアが閾値を超えたものを隔離ボックスへ送ることができます。
Webフィルタリング機能
Webフィルタリング機能は、URL、サイトのカテゴリ、評判データベースを活用し、マルウェアを配布する有害サイトや詐欺サイト、業務に不適切なサイトへのアクセス、閲覧を遮断します。また、暗号化されたHTTPS通信の内容も検査することで、隠蔽された脅威も発見できます。例えば、設計部門のPCでは動画配信・ファイル共有カテゴリを業務時間中はブロックしつつ、広報部のみ公式配信サイトをホワイトリスト登録といった部門別ポリシーを適用できます。
IDS/IPS機能(侵入検知・防御システム)
IDS/IPS機能は、ネットワーク上を流れるデータを監視し、既知の攻撃パターンを検知します。脆弱性を狙った攻撃、ポートスキャン、ブルートフォース攻撃などの不正な活動を発見すると、自動的に通信を遮断します。例えば、勤怠サーバに対する短時間での多回数ログイン試行(ブルートフォース)を署名で検知したら、発信元グローバルIPを一定時間自動でシャドウBANし、同時に管理者へアラートとパケットキャプチャ(証跡)を送付する、といった即応運用が可能です。このように、共通脆弱性識別子(CVE)に登録された既知の攻撃手法に対して高い効果が期待できます。
アプリケーション制御機能
アプリケーション制御機能は、ネットワーク上で使用されているアプリケーションを可視化し、必要に応じて制御します。DPI(Deep Packet Inspection:深度パケット検査)技術を使用してアプリケーションを識別し、P2Pファイル共有ソフトや匿名化ツール、業務に不適切なアプリケーションの使用を制限できます。
この機能ではコールセンターの席ではチャット/通話アプリ以外のクラウドストレージ・匿名化ツールを通信レベルでブロックし、管理部の端末のみ一時的な例外ルール(承認フロー付き)で許可する、といった使い分けができます。
以下にそれぞれの機能の役割、検査対象、効果まとめます。
| 機能 | 役割 | 主な検査対象 | 主な効果 |
|---|---|---|---|
| ファイアウォール | 通信の許可/拒否・NAT | IP/ポート/セッション状態(L3/L4) | 外部からの不正アクセス遮断、不要ポート閉塞 |
| アンチウイルス | マルウェアの検出/排除 | ファイル/HTTP(S)/メール添付 | 既知マルウェア・ダウンロード型感染の阻止 |
| アンチスパム/メール保護 | 不審メールの抑止 | 送信元/ヘッダ/本文/URL | スパム/フィッシングの流入抑制 |
| Webフィルタリング | 危険サイトへのアクセス制限 | URL/カテゴリ/SSL/TLS(複合)インスペクションが有効な場合のHTTPSトラフィック内容 | マルウェア配布/詐欺/危険なサイト遮断 |
| IDS/IPS | 既知手口の検知/遮断 | シグネチャ/脆弱性攻撃 | 既知CVE(脆弱性)悪用、スキャン/ブルートフォース遮断 |
| アプリケーション制御 | アプリ通信の可視化/抑止 | DPIによるアプリ識別 | P2P/匿名化/非業務アプリの抑制 |
| ファイアウォール | |
|---|---|
| 役割 | 通信の許可/拒否・NAT |
| 主な検査対象 | IP/ポート/セッション状態(L3/L4) |
| 主な効果 | 外部からの不正アクセス遮断、不要ポート閉塞 |
| アンチウイルス | |
| 役割 | マルウェアの検出/排除 |
| 主な検査対象 | ファイル/HTTP(S)/メール添付 |
| 主な効果 | 既知マルウェア・ダウンロード型感染の阻止 |
| アンチスパム/メール保護 | |
| 役割 | 不審メールの抑止 |
| 主な検査対象 | 送信元/ヘッダ/本文/URL |
| 主な効果 | スパム/フィッシングの流入抑制 |
| Webフィルタリング | |
| 役割 | 危険サイトへのアクセス制限 |
| 主な検査対象 | URL/カテゴリ/SSL/TLS(複合)インスペクションが有効な場合のHTTPSトラフィック内容 |
| 主な効果 | マルウェア配布/詐欺/危険なサイト遮断 |
| IDS/IPS | |
| 役割 | 既知手口の検知/遮断 |
| 主な検査対象 | シグネチャ/脆弱性攻撃 |
| 主な効果 | 既知CVE(脆弱性)悪用、スキャン/ブルートフォース遮断 |
| アプリケーション制御 | |
| 役割 | アプリ通信の可視化/抑止 |
| 主な検査対象 | DPIによるアプリ識別 |
| 主な効果 | P2P/匿名化/非業務アプリの抑制 |
UTM導入のメリット
UTMの導入はセキュリティ強化だけでなく、さまざまなメリットがあります。
1.導入や管理コストの軽減
- 複数のセキュリティ機能を一台で管理
- 初期投資とランニングコストの削減
- 保守・サポート窓口の一本化
従来のセキュリティ対策では、ファイアウォール、ウイルス対策ソフト、スパムフィルター、Webフィルタリングツールなどを個別に導入する必要がありましたが、UTMを導入することでこれらの機能を一台で管理でき、コストを抑えることができます。
2.業務に支障なく導入が可能
- ゲートウェイ(※1)への機器設置のみ
- 既存ネットワークの大幅変更不要
- 短期間での導入が可能
UTMの場合、基本的にはインターネット接続点(ゲートウェイ)に機器を設置するだけで導入が完了するので、導入により業務停止リスクを最小限にできます。導入作業も通常は数時間から半日程度で完了するため、業務への影響を最小限に抑えることができます。
※1ゲートウェイ:日本語では「玄関」「出入り口」の意。通信手段の異なるネットワークを中継する機能を持つ。3.トラブル時の対処が容易
- サポート体制の一本化により復旧時間の短縮が可能
- 統一されたサポート体制
- ログ管理の一本化
UTMの場合、すべてのセキュリティ機能が一台の機器に統合されているため、サポート体制を一本化することができます。また、ハードウェア障害が発生した場合でも、機器全体を交換することで全機能を一度に復旧させることができます。
UTMのデメリット・注意点
UTMの導入は多くのメリットがある一方で、いくつかデメリットもあります。UTMの導入を考えている場合、以下の点を考慮したうえで検討しましょう。
1.故障やダウン時の影響が⼤きい
- 機器故障時にすべてのセキュリティ機能が停止
- インターネット接続への影響
UTMの最も大きなデメリットは、一台の機器にすべてのセキュリティ機能が集約されていることです。これは「単一障害点(Single Point of Failure)」(※2)と呼ばれるリスクを生み出します。機器の故障やシステム障害を起こした場合、すべてのセキュリティ機能が同時に停止してしまいます。さらにUTMが完全停止した場合、インターネット接続自体が遮断される可能性があります。
※2 単一障害点:システムを構成する要素のうち、そこが停止するとシステム全体が停止してしまう部分のこと。2.セキュリティ機能の選択範囲が制限される
- 搭載機能の範囲内での運用
- 細かな設定変更が困難
UTMは、あらかじめ統合されたセキュリティ機能を提供するため、個別のセキュリティツールと比較して設定の自由度が制限される場合があります。さらに、一度UTMを導入すると、特定の機能だけを他のツールに置き換えることが困難になるため、将来的な拡張性についても慎重に検討する必要があります。
3.トラフィック負荷による通信速度の低下
- 複数機能の同時稼働による負荷
- 大容量通信時の遅延発生
UTMは複数のセキュリティ機能を同時に実行するため、ネットワークトラフィックに対する処理負荷が高くなります。大容量のファイル転送、動画ストリーミングなどを業務で使用する場合や同時接続ユーザーが多い環境では注意が必要です。
4.製品による性能差
- メーカーごとの得意分野が異なる
- 万能ではない点への留意が必要
UTMは製品によって機能や特性が異なります。必要なセキュリティ機能を明確にし、各製品の機能や特性を⽐較検討することが重要です。複数の機能を搭載しているとはいえ、UTMの主な役割は「ネットワークの監視」です。「UTMの導入=対策は万全」ではないことに留意し、必要な対策を検討しましょう。現代のサイバー攻撃は多様化・高度化しており、「UTMを導入すれば安心・安全」という考えは危険です。EDR(Endpoint Detection and Response)やSOC(Security Operation Center)サービスなど、他のセキュリティ対策との組み合わせが重要になっています。
さらに短時間で概要を知りたい方は、【5分でわかるサクサUTM】をご覧ください。主要な機能やサポート体制をコンパクトにまとめています。
( 3 ) UTMと他ツールの違い【比較表付き】
現代のセキュリティ市場には多様なソリューションが存在し、それぞれが異なる目的と特徴を持っています。UTMの位置づけを正しく理解するために、主要なセキュリティツールとの違いを詳しく解説します。

| 製品・サービス | 主な目的 | 保護対象 | 導入位置 | テレワーク適合 | 運用主体 |
|---|---|---|---|---|---|
| UTM | 統合脅威管理 | 拠点ネットワーク全体 | ゲートウェイ | △ (VPN併用で○) |
社内IT担当/委託 |
| ファイアウォール(FW) | アクセス制御 | ネットワーク境界 | ゲートウェイ | △ (設定複雑) |
社内IT担当 |
| WAF | Webアプリ保護 | Webサーバ | サーバ前段 | ○ | 社内IT担当 |
| NGFW(次世代ファイアウォール) | 高度化する脅威への多層防御 | ネットワーク境界 | ゲートウェイ | △ (管理複雑) |
専門IT担当 |
| EDR | 端末監視・対応 | PC/サーバ等端末 | 各端末 | ○ | SOC/専門業者 |
| XDR(Extended Detection and Response) | 統合検知・対応 | 端末/ID/メール/クラウド/ネットワーク | SaaS中心の統合基盤 | ○ | 専門業者 |
| SASE(Secure Access Service Edge) | セキュア接続 | ネットワーク全体 | クラウド上 | ◎ | サービス提供者 |
| SSE(Security Service Edge) | セキュアWebゲートウェイ | インターネット接続 | クラウド上 | ◎ | サービス提供者 |
従来型ファイアウォール(FW)との違い
従来型のファイアウォールは、ネットワーク境界でのアクセス制御に特化したツールです。主にIPアドレス、ポート番号、通信プロトコルにもとづいて通信の許可・拒否を判断します。設定はシンプルで理解しやすく、処理速度も高速ですが、機能は基本的なアクセス制御に限定されています。
UTMは、このファイアウォール機能を基盤として、アンチウイルス、Webフィルタリング、アンチスパム、IPS機能などを統合したソリューションです。一台でより包括的なセキュリティ対策が可能になります。
次世代ファイアウォール(NGFW)との違い
次世代ファイアウォール(NGFW:Next Generation Firewall)は、従来のファイアウォールに高度な脅威検知機能を追加したエンタープライズ向けソリューションです。アプリケーション識別、ユーザー識別、高度なIPS機能、SSL復号化などの機能を搭載し、非常に詳細なセキュリティポリシーの設定が可能です。
NGFWとUTMの最も大きな違いは、ターゲット市場と運用の複雑さです。NGFWは大企業や高度なセキュリティ要件を持つ組織向けに設計されており、専門的なセキュリティ知識を持つ担当者による運用を前提としています。設定項目が非常に多く、最適な設定を行うためには相当な専門知識と経験が必要です。一方、UTMは中堅・中小企業を主要ターゲットとして、導入・運用の簡便さを重視して設計されています。
( 4 ) 2025年の脅威動向から見るUTMが有効な領域
UTMが高い効果を発揮する脅威
1.ランサムウェア攻撃
ランサムウェア攻撃は、現在最も深刻なサイバー脅威の一つです。UTMは、ランサムウェアの感染経路である悪意のあるメールの添付ファイルやWebサイトからのダウンロードを、入口段階で効果的に遮断できます。ただし、UTMの限界も理解しておく必要があります。未知の攻撃手法(ゼロデイ攻撃)を使用するランサムウェアや、正規のアプリケーションに偽装して内部ネットワークに侵入後、横展開を行う高度な攻撃に対しては、UTMだけでは対応が困難です。EDRやXDRの併用を検討してください。
2.サプライチェーン攻撃
-
UTMの効果:
外部通信の監視・制御
-
検知が難しいケース:
正規アプリに偽装された攻撃は検知困難
サプライチェーン攻撃は、信頼できる取引先や業界パートナーを経由して行われる攻撃で、近年急激に増加しています。UTMは、このような攻撃における外部との不審な通信を監視・制御することで、被害の拡大を防ぐ効果があります。しかし、すでに信頼関係のある通信経路を悪用した攻撃については、検知が困難な場合があります。
3.内部不正・情報の流出
-
UTMの効果:
不審な外部通信の検知・遮断
-
検知が難しいケース:
物理的な情報持ち出しは対応不可
内部の悪意ある行為者が機密情報を外部に送信しようとする際、一部のUTMはDLP(Data Loss Prevention)機能や通信監視機能により、不審な大容量データの転送や、許可されていない外部サービスへのアクセスを検知・遮断できます。ただし、物理的な記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクなど)を使用した情報の持ち出しや、個人のデバイスを利用した情報漏洩に対しては、UTMでは対応できません。
UTMでは対応困難な脅威
-
ゼロデイ攻撃
ゼロデイ攻撃は、まだ発見・対策されていない脆弱性を悪用する攻撃で、従来のシグネチャベースの検知手法では発見が困難です。UTMのアンチウイルス機能やIPS機能は、主に既知の攻撃パターンにもとづいて動作するため、全く新しい攻撃手法に対しては検知率が低下します。
-
ソーシャルエンジニアリング攻撃
この攻撃は技術的な脆弱性ではなく人間の心理的な隙を突く手法です。巧妙に作成されたフィッシングメールや偽の電話などにより、従業員を騙して機密情報を盗み出したり、マルウェアをインストールさせたりします。UTMの技術的な防御機能だけでは、このような人間を標的とした攻撃を完全に防ぐことはできません。
-
内部での横展開攻撃
横展開攻撃とは一度内部ネットワークへの侵入を許した攻撃者が、ネットワーク内を移動しながら権限昇格や情報収集を行う攻撃手法です。UTMは主にネットワーク境界での防御に特化しているため、内部ネットワーク内での活動については可視性が限定的です。
( 5 ) UTMの月額料金の目安
UTMの導入を検討する際、最も重要な要素の一つがコストです。企業規模や要件に応じて適切な投資判断を行うために、詳細な費用構造を理解することが重要です。以下の表の料金レンジは目安で、実価格はスループット(全機能ON時の実効値)/拠点数/保守SLA/回線同梱/ライセンス構成で大きく変動します。
企業規模別の月額料金相場
| 企業規模 | 同時接続数 | 月額料金相場 |
|---|---|---|
| 小規模(~30名) | 50~100セッション | 5,000~20,000円 |
| 中規模(30~100名) | 100~500セッション | 20,000~50,000円 |
| 大規模(100名~) | 500セッション~ | 50,000円~ |
※料金は目安であり、ベンダーや契約条件により変動します。
小規模企業(従業員30名以下)の場合、UTMの月額利用料は5,000円から20,000円程度が目安です。この価格帯では、同時接続数50~100セッション程度に対応したモデルが中心となります。
初期費用については、機器購入の場合は100,000円から300,000円程度、レンタルやクラウド型サービスの場合は設定費用として30,000円から50,000円程度が必要になります。小規模企業の場合、初期投資を抑えられるレンタルやクラウド型サービスを選択するケースが多く見られます。
中規模企業(従業員30~100名)では、月額20,000円から50,000円程度の投資が必要になります。この規模では、同時接続数100~500セッションに対応でき、より高度なセキュリティ機能を搭載したモデルが適しています。
中規模企業では、セキュリティ要件が複雑になるため、導入・設定費用も100,000円から200,000円程度と高くなる傾向があります。また、この規模になると専任のIT担当者が存在する場合が多いため、より詳細なカスタマイズや運用が可能になります。
大規模企業(従業員100名以上)では、月額50,000円以上の投資が一般的で、場合によっては数十万円に達することもあります。500セッション以上の同時接続に対応し、高速処理能力と豊富な機能を搭載したモデルが必要になります。冗長構成用の対機器(スタンバイ機)、高可用性、詳細なログ分析機能なども重要な要件となります。
導入形態別の費用構造
スクロールできます| 導入形態 | 初期費用 | 月額料金 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 購入 | 100,000~1,200,000円 | 保守費:5,000~30,000円 | 長期的コスト削減 | 初期投資大・陳腐化リスク |
| レンタル | 設定費:30,000~100,000円 | 7,000~50,000円 | 初期投資軽減 | 長期的コスト増 |
| リース | 設定費:30,000~100,000円 | 5,000~50,000円 | 設備投資の分散 | 途中解約制約 |
| クラウド型 | 設定費・導入構築費:10,000~200,000円 | 端末1台当たり月額600円前後/または月額10,000~30,000円 | 初期設備なし/運用管理の負荷軽減 | 通信遅延・SLA依存リスク |
※料金は目安であり、ベンダーや契約条件により変動します。
購入形態は、長期的な運用を前提とした場合に最もコスト面での効率がよい選択肢です。初期投資は100,000円から1,200,000円程度と高額になりますが、月額料金は保守費用の5,000円から30,000円程度に抑えられます。5年以上の長期運用を計画している企業にとっては、総保有コスト(TCO:Total Cost of Ownership)が最も低くなる選択肢です。
レンタル形態は、初期投資を大幅に抑制できる利点があります。設定費用として30,000円から100,000円程度の初期費用で導入でき、月額7,000円から50,000円程度の利用料で最新のUTM機能を利用できます。機器の老朽化リスクをレンタル会社が負担するため、常に最新の機能を利用できる安心感があります。しかし、長期的な運用コストは購入形態と比較して高くなる傾向があります。
リース形態は、購入とレンタルの中間的な特徴を持ちます。設定費用は30,000円から100,000円程度、月額5,000円から50,000円程度で利用できます。会計処理上は費用として計上できるため、設備投資予算の制約がある企業にとって有利です。 ただし、リース契約には通常、途中解約に関する制約があります。事業環境の変化により早期にシステム変更が必要になった場合、解約金が発生する可能性があります。安定した事業運営を行っており、中長期的な計画が立てやすい企業に適しています。
隠れたコスト
-
ライセンス費用:年間30,000~200,000円
ライセンスにはセキュリティシグネチャ・パターンファイルの更新、新機能の提供、脅威インテリジェンスの配信などが含まれます。
-
シグネチャ・パターンファイル更新費用:月額3,000~15,000円
最新の脅威情報を常に反映するために不可欠です。この更新が停止すると、新しい脅威に対する防御能力が著しく低下するため、継続的な投資が必要になります。
-
保守サポート:購入価格の10~20%/年
通常、機器購入価格の10~20%程度が年間費用として発生します。24時間365日のサポート、障害時の代替機提供、定期的な健康診断などのサービスが含まれます。
-
導入・設定費用:100,000~500,000円
ネットワーク構成の複雑さや要求されるカスタマイズレベルによって大きく変動します。専門的な設定が必要な大規模環境では、この費用が予想以上に高額になる場合があります。
-
トレーニング費用:50,000円~200,000円
UTMを効果的に運用するためには、管理者の適切な知識とスキルが必要です。ベンダーが提供するトレーニングプログラムや認定資格の取得に、一人当たり50,000円から200,000円程度の投資が必要になる場合があります。
( 6 ) 導入手順【チェックリスト付き】
UTMの効果的な導入のためには、計画的で段階的なアプローチが不可欠です。以下の詳細な手順に従って進めることで、導入リスクを最小限に抑え、期待される効果を確実に実現できます。
① 現状把握(チェックリスト)
資産の棚卸し
-
保護対象システム・データの洗い出し
サーバ、ワークステーション、ネットワーク機器、クラウドサービス、データベース、重要なファイルサーバなど。
-
現在のセキュリティ対策状況の確認
アンチウイルスソフト、ファイアウォール、バックアップシステムなど。
-
既存機器・ソフトウェアとの互換性確認
UTMとの重複や互換性の問題があるか。
通信経路の分析
-
インターネット接続環境の調査
インターネット接続の帯域幅、通信量のピーク時間、主要なアプリケーションの通信パターンを調査。
-
内部ネットワーク構成の把握
VLAN構成、サブネット設計、ルーティング設定など内部構成の確認。
脅威リスクの評価
-
業界固有の脅威動向調査
所属する業界団体や関連する政府機関、セキュリティベンダーが公開しているインシデントレポートや脅威レポートを収集・分析。
-
過去のインシデント履歴の確認
自社で過去に発生したセキュリティインシデント(ウイルス感染、不正アクセス、情報漏洩の未然防止・既遂など)の記録を確認することで、自社のセキュリティ上の「弱点」や「傾向」を具体的に把握。
-
コンプライアンス要件の整理
セキュリティ強化だけでなく、個人情報保護法を始め国内外の法令を遵守するためにコンプライアンス要件を確認。
② 要件定義
技術要件
-
同時セッション数の算出
通常は、現在のピーク時通信量の1.5~2倍程度の余裕を持った設計とすることを推奨。
-
必要スループットの決定
処理負荷を考慮した実効スループットを計算。UTMはすべての機能を有効にした場合のスループットが大幅に低下するため、この点を十分に考慮した製品選択が重要。
-
搭載機能の優先順位付け
脅威リスク評価の結果をもとに、自社にとって最も重要なセキュリティ機能を特定し、優先付け。
運用要件
-
管理体制・担当者の決定
管理体制と担当者を明確にすることで、設定変更、ポリシー更新、障害対応などが迅速かつ適切に行われ、セキュリティホールの発生を防止。
-
監視・保守方針の策定
監視・保守の方針を定めることで、運用のムラをなくし、予期せぬトラブルや性能低下を未然に防止。
-
障害時対応手順の検討
重大なセキュリティインシデントが発生したりした場合、迅速かつ的確な対応が被害の拡大を防ぐ鍵。事前に手順を定めておくことで、緊急時の混乱を防ぎ、システムの復旧時間を最小限に抑える。
③ 構成設計
-
ネットワーク構成図の作成
UTMをどこに配置し、どのような通信フローとするかを詳細に設計。一般的には、インターネット接続ルータの直後にUTMを配置。
-
冗長化・バックアップ方式の検討
UTMが単一障害点となるリスクを軽減するため、アクティブ・スタンバイ構成やクラスター構成などの冗長化オプションを検討。
-
セキュリティポリシーの策定
UTMの各機能に対する具体的な設定ルールを定義。ファイアウォールルール、Webフィルタリングのカテゴリ設定、アプリケーション制御の許可・禁止リスト、アンチウイルスの動作モードなどが含まれる。
④ PoC(概念実証)
-
候補製品の選定(2~3製品)
単純なスペック比較だけでなく、実際の使用環境に近い条件でのテストが重要。
-
評価環境での動作検証
本番環境と同様のネットワーク構成でテストを行い、設定の容易さ、管理画面の使いやすさ、レポート機能の有用性、サポート体制の質などを実際に評価。
-
パフォーマンス・機能評価
各製品の実際の処理能力を測定し、理論値と実測値の差を確認。誤検知(正常な通信を脅威として検知してしまう)の発生率や、各種脅威に対する検知率も重要な評価項目。
⑤ 本番展開
-
段階的な導入計画の策定
すべての機能を一度に有効にするのではなく、まずは基本的なファイアウォール機能から開始し、徐々にアンチウイルス、Webフィルタリング、IPS機能などを追加。
-
移行時の影響最小化対策
業務時間外での作業スケジューリング、影響を受ける可能性のある業務システムの事前調整、緊急時の切り戻し手順の準備。
-
導入後の動作確認
すべての重要な業務システムとアプリケーションが正常に動作することを確認。UTMの各機能が期待通りに動作し、セキュリティポリシーが正しく適用されていることを検証。
⑥ 運用設計
-
シグネチャ・定義ファイル更新の自動化
通常は日次または週次での自動更新が推奨されているが、重要なシステムへの影響を考慮して、事前テストを行う仕組みも重要。
-
ログ監視・分析体制の構築
UTMが生成する大量のログデータから重要な情報を抽出し、セキュリティインシデントの早期発見につなげる仕組みを構築。アラート設定の最適化、レポートの自動生成、ダッシュボードによる可視化などが含まれる。
-
定期的な設定見直しサイクルの確立
月次または四半期ごとに、UTMの設定とパフォーマンスを評価し、必要に応じて調整を行う。脅威環境の変化や業務要件の変更に応じて、セキュリティポリシーを継続的に改善していくことも重要。
自社のセキュリティ体制が十分かどうか気になる方は、導入前に【情報漏洩対策チェックリスト】で自社の現状を確認してみましょう。
( 7 ) UTMはどんな企業に向いている?
セキュリティ対策に有効なUTMですが、万能なセキュリティソリューションではありません。企業の規模、業種、セキュリティ要件、IT管理体制などによって、UTMの適合性は大きく変わります。ここではUTMの導入をおすすめする企業と、その理由について紹介します。
セキュリティ担当者がいない企業
情報システム部⾨やエンジニアなど専任の担当者がいない企業は、設置や運用が容易でアップデートなどの更新の手間がないUTMの導⼊が有効です。UTMは、複数のセキュリティ機能が事前に統合・調整されているため、専門知識がなくても効果的なセキュリティ対策を実現できます。導入後のサポートが受けられる製品であれば、担当者が不在でも安心です。また、自動更新機能により、最新の脅威定義やセキュリティパッチが自動的に適用されるため、管理者の作業負荷を大幅に軽減できます。
小規模から中規模の企業
近年のサイバー攻撃は中⼩企業を標的にするケースが増加し、中⼩企業を「踏み台」として利⽤するサプライチェーン攻撃は「情報セキュリティ10⼤脅威2025」でも上位にランクインしています。セキュリティ対策に大きなコストをかけることができない中小企業は、ファイアウォール、アンチウイルス、Webフィルタリング、メール保護などのセキュリティ機能が一つに集約され、導入・運用コストが抑えられるUTMの必要性が高いと言えるでしょう。
参照:IPA(独⽴⾏政法⼈ 情報処理推進機構)「情報セキュリティ10⼤脅威 2025」すぐにセキュリティを強化したい企業
セキュリティインシデントの発生、法規制への対応、監査での指摘、大型契約の獲得要件などの理由でセキュリティ強化が急務とされる企業にもおすすめです。導入する際に⼯事やネットワークの変更は不要で、さまざまなセキュリティ機能を備えているため、1台で複数のツールの役割を担うことができます。基本的にネットワーク機器の追加設置のみで完了するため、既存システムへの影響を最小限に抑えながら迅速にセキュリティレベルを向上させることができます。
顧客情報を多く取り扱う企業
2022年4月に改正個人情報保護法が施行され、個人情報が漏洩した場合の報告の義務化や、違反時の罰則が強化されました。顧客情報などの個人情報を管理する企業には、社内外のさまざまな脅威から自社の資産となる情報を守るUTMのような、強固で包括的なセキュリティ対策が求められています。
クラウド型UTMという選択肢
近年、従来のオンプレミス型UTMに加えて、クラウド型UTMサービスが注目されています。この新しいサービスは、従来のUTMの利点を保ちながら、現代の働き方に適応した機能を提供しています。
クラウド型UTMはオンプレミス型UTMに比べ、短期間で導入でき、初期費用も大幅に抑えられます。運用業務をサービス提供者が担当するため、自社の運用負担も減少させることができます。また、クラウド型UTMはテレワーク環境にも対応しています。
しかし、すべてのトラフィックがクラウド経由となるため通信遅延の問題があり、業務に影響する場合があります。また、オンプレミス型では機器障害の影響は単一拠点に限定されますが、クラウド型ではサービス障害が全拠点に同時に影響する可能性があります。
| 比較項目 | オンプレミス型UTM | クラウド型UTM |
|---|---|---|
| 導入速度 | 2〜4週間 | 即日~4週間 |
| 初期費用 | 高(機器購入) | 低(設定費のみ) |
| 運用負荷 | 高(社内管理) | 低(業者管理) |
| テレワーク適合 | △(VPN設定必要) | ○(クラウド経由) |
| 通信遅延 | 低 | やや高 |
| 拠点追加 | 機器調達必要 | 設定変更のみ |
| 障害影響範囲 | 単一拠点 | 全拠点(リスク分散要) |
( 8 ) 失敗しないUTMの選び方
UTM製品の選択は、単純な機能比較や価格比較だけでは不十分です。企業の現在の状況、将来の成長計画、セキュリティ要件、運用体制などを総合的に考慮した選択基準が重要です。
⾃社に必要な機能を備えているか
UTM製品の多くは、導入後の機能追加や拡張が難しい場合があります。UTMを導⼊する際は、まず⾃社のセキュリティ要件を明確にし、どのような機能が必要か、自社に合ったコストであるかなどを洗い出すことが大切です。将来も見据えたうえで、製品スペックが自社の規模に適しているかを検討しましょう。例えば、現在は従業員50名の企業でも、3年後に100名に拡大する計画がある場合、将来の規模に対応できる拡張性を持ったUTMを選択する必要があります。
充実したサポートが受けられるか
UTM導入後、トラブル発生時だけでなく、不明点を相談できるサポート体制が整備されているかを確認しておきましょう。特に社内にセキュリティの専門部署や担当者を置かない場合、サポートが充実している製品を選んでおくと安心です。単純な問い合わせ対応だけでなく、設定支援、トラブルシューティング、パフォーマンス最適化、セキュリティ相談など、どこまでのサポートが提供されるかを詳細に確認する必要があります。
わかりやすく使いやすい製品か
機能や操作性のわかりやすさもUTMを選ぶうえで重要なポイントです。表示に専門的な用語が使われているような製品は設定や運用に手間取り、業務効率の低下にもつながります。また、海外メーカーの製品は⽇本語に対応していない場合もあるため、機能を⼗分に活⽤できない可能性も考えられます。自社のIT担当者のスキルレベルに適した製品選択が重要です。可能であれば、デモ環境や評価版で実際に操作して確認してください。
耐久性がありメンテナンスしやすいか
耐久性の項目はUTMが単一障害点となるリスクを考慮すると極めて重要です。MTBF(平均故障間隔)、冗長化された電源、ファンレス設計、工業用部品の使用など、信頼性を高める設計が採用されているかを確認します。また、ソフトウェアの更新頻度と継続性も重要な要素です。
実績・信頼はあるか
同業界・同規模企業での導入事例を確認することで、自社環境での有効性を予測できます。また、UTMは長期間使用する設備投資であり、ベンダーの経営状況、技術開発力、市場でのポジション等確認が必須です。評価の基準としてセキュリティ製品の評価機関による認証、業界団体での推奨、政府調達での採用実績などが指標となります。
( 9 ) よくある質問
UTMについて、よくある質問にお答えします。
Q1. UTMは古い・不要って本当?
A. いいえ、UTMは今も多くの企業で有効なセキュリティ対策です。
「UTMは古い技術で不要」という議論は、クラウド化とテレワークの普及により境界型セキュリティの限界が指摘される中で生まれた誤解です。
実際には、多くの企業でオンプレミスとクラウドが混在し、オフィス勤務とテレワークも併存しています。こうした環境では、UTMは依然として外部からの攻撃を防ぐ重要な防御層として機能します。
重要なのは、UTM
を単独で使うのではなく、多層防御の一部として組み合わせて運用することです。
< 詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめです。>
UTMはもう古い? 必要ないと言われる理由や導入すべき企業の特徴Q2. UTMとファイアウォール・NGFWの違いは?どっちを選ぶべき?
A. 中小企業にはUTM、大企業にはNGFWがおすすめです。
UTM・ファイアウォール・NGFWはいずれも不正アクセスを防ぐ仕組みですが、提供する機能と運用負荷が異なります。
・ファイアウォール(FW):通信の許可・遮断を行う基本的な防御。シンプルな構成で、社内にセキュリティ専門人材がいる環境に適しています。
・NGFW(次世代ファイアウォール):アプリケーション制御や脅威検知などの高度な機能を備えた上位モデル。中〜大規模企業や専門チームのある組織向け。
・UTM(統合脅威管理):複数のセキュリティ機能(FW・IPS・ウイルス対策など)を一台に統合したオールインワン型。中小企業やIT専任者が少ない環境に最適です。
目安として、従業員100名以下 → UTM、100〜500名 → NGFW、500名以上 → 高機能NGFW+個別製品の組み合わせが一般的な選び方です。
より詳細な違い・比較表はこちら
(3) UTMと他ツールの違い【比較表付き】Q3. UTMとEDR/XDRは両方必要?役割分担は?
A. UTMとEDR/XDRはどちらも必要で、補完し合う関係です。
UTMは「入口防御」、EDR/XDRは「内部監視・対応」を担い、役割が異なります。
・UTM(統合脅威管理):ネットワークの境界で外部からの攻撃を遮断する「入口対策」。既知のマルウェアや不審通信をブロックし、社内に侵入する脅威の量を大幅に減らします。
・EDR/XDR:端末やクラウド上での挙動を継続的に監視し、UTMをすり抜けた攻撃を検知・対応する「内部対策」。未知の脅威や内部感染の拡大を防ぎます。
これらは競合ではなく、多層防御(Defense in
Depth)を実現するための両輪です。
予算に限りがある場合は、まずUTMで外部対策を固め、次の段階でEDRを導入するのが一般的です。
Q4. 中小企業の費用相場は?
A. UTMの導入費用は月額5,000~50,000円程度が一般的です。
従業員30名以下:月額5,000~20,000円、30~100名:月額20,000~50,000円が相場です。いずれも、初期費用(機器代・設定費)として、導入形態により3~170万円程度が別途発生します。クラウド型UTMやレンタルプランを利用すれば、初期費用を抑えて導入することも可能です。
詳しくは
(5) UTMの月額料金の目安Q5. ランサムウェア対策にUTMはどこまで効果的?
A. UTMはランサムウェアの初期侵入防止に有効ですが、感染後の拡大までは防げません。
UTMはネットワークの入口での防御に強く、
・不審な添付ファイルの通信遮断
・マルウェア配信サイトへのアクセス防止
・感染端末の外部通信検知・遮断
など、初期侵入や外部通信の段階では高い効果を発揮します。
一方で、未知のランサムウェアや内部拡散(横展開)は検知が難しく、UTM単体では防ぎきれません。そのため、EDR/XDRによる端末監視やバックアップ対策を組み合わせた多層防御が不可欠です。
Q6. クラウド型とオンプレミス型、どちらがおすすめ?
A. テレワーク中心ならクラウド型、通信量が多い業務ならオンプレミス型がおすすめです。
企業の働き方・IT管理体制・通信量・コスト方針を踏まえて判断します。
クラウド型UTMが向いている企業
・テレワークや外出先アクセスが多い
・IT専任者が少ない/不在
・初期費用を抑えたい
・複数拠点を統合管理したい
オンプレミス型UTMが向いている企業
・動画制作やCADなど、大容量通信を日常的に行う
・セキュリティ要件が厳しく、社内で制御したい
・長期利用(5年以上)で総コストを抑えたい
また、両方の利点を活かすハイブリッド構成も有効です。たとえば、一般業務はクラウド型で保護し、機密データはオンプレミスで守ることで、柔軟かつ効率的な運用が可能になります。
( 10 ) まとめ
今回は、複数のセキュリティ機能を一元化して効率的に運用できるUTMについて解説しました。導入・管理コストを抑えてセキュリティ強化したい企業にとって、日々多様化するサイバー攻撃から自社を守ってくれるUTMは優れたセキュリティツールと言えます。
UTMはファイアウォール、アンチウイルス、Webフィルタリング、メール保護、IPS、アプリケーション制御などの機能を統合的に提供し、複雑な設定や管理を必要とせずに効果的な多層防御を実現できます。特に、IT専任者が限られている中小企業にとって、この統合性と簡便性は決定的な利点となります。
2025年の脅威動向を踏まえると、UTMは基本的なセキュリティ対策の土台として依然として重要ですが、完全な対策には他のセキュリティソリューションとの組み合わせが必要です。
UTMの仕組みやメリットをもっと詳しく知りたい方は、 【UTM丸わかりガイド】 をぜひご覧ください。また、記事の中でも紹介した最新モデルのUTM「SS7000Ⅲ」の詳細もご覧いただけます。ぜひ自社のセキュリティ対策の参考にしてください。
課題解決に役立つ資料はこちら!
経営課題におけるトレンド情報や課題解決にお役立ていただける資料をまとめております。
ぜひ一度お読みください。